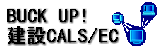 Monday, 06-Apr-98 12:27:47
Monday, 06-Apr-98 12:27:47 THE pinkhip WORLD 「中小建設業情報化講座」 |戻る |著作権|
■現況
建設省が策定した1995年「建設産業政策大綱」「構造改善戦略プログラム」(表1参照)では、情報化推進事業は「戦略的推進事業」と位置づけられています。この文脈の中で「建設CALS/EC」の導入推進も行われるものであることは、建設業界に身を置く方なら既にご存知のことだと思います。しかし、この「建設CALS/EC」対応を当面の目標とした中小建設業における情報化推進作業は、一部の例外を除いては遅々として進まないのが現状のようです。
曰く、経営陣の情報化戦略への理解不足、業界の古い体質(ルール)の存在、情報リテラシイの欠如等々。
現在、中小建設業(中小ゼネコン)の最大の問題点は、本来「建設CALS/EC」対応作業とともに進めるべき「差別化戦略」を行えない状況にあることだと考えます。「差別化戦略」とは「コア・コンピタンス(核心的競争力)」を源泉とする経営ですが、公共工事の削減、長引く民間需要の冷え込みと建設需要の減退は、分母(業者数)が依然として減少しないこともあって、価格競争と違法行為(談合)での目先の受注確保を第一義の経営目標にせざるを得ず、「差別化戦略」へ目を向ける余裕を経営陣に与えていないのが現状のように思えます。
しかし、それは何の問題解決にも成り得ない事は明らかです。
私は、「建設CALS/EC」時代の経営戦略は「差別化戦略」しかないという立場をとります。これからの建設業は、横並びの「護送船団方式」ではなく、建設省が何とかしてくれるものでもないでしょう。これは金融ビックバンに見られる金融業界の自由化を見れば明らかです。
■情報化の位置付け
自社の経営戦略における「情報化」の位置付けは、「情報化」に対する経営陣の期待度によって変わらざるを得ません。言い換えれば「情報化」になにを望むのかということですが、当面の課題として「建設CALS/EC」への対応は避けて通れない道です。
それでは、「建設CALS/EC」への対応を踏まえた「情報化」とはなんでしょうか。それは、「企業文化の変革」であることを理解してほしいと思います。「建設CALS/EC」の根底にあるものは、「オープン(解放性)」「ボトムアップ(平等性)」「ボランティア(自律性)」といった、いわば「グラスルーツ(草の根)」の文化です。この文化は、これまでの建設業の特徴であった「クローズ(閉鎖性)」「トップダウン(階層性)」「オーダー(他律性)」といった文化とは、本来相容れないものであるとは容易に理解できるかと思います。
「建設CALS/EC」時代に活躍できる中小建設業者のキーワードは社員の自由な「想像力」と「創造力」に基づく「知識」と「知恵」を生み出す「企業文化」です。この「知識」と「知恵」こ基づく「企業文化」こそ「差別化戦略」、「コア・コンピタンス経営」の源だといえるでしょう。
「情報化」は当然に「知識」と「知恵」の想像のために、言い換えれば、社員が「想像力」と「創造力」を遺憾なく発揮できる「企業文化」創造のために行われるものであると言って良いでしょう。
次回からは、中小建設業における情報化への取り組みを、より具体的に述べて行きたいと思います。
Monday, 06-Apr-98 12:27:47
| 7つの重点課題 | 15の推進事業 |
| 1.雇用労働条件の改善と人材確保 | 1.基幹的技能者育成推進事業(戦略的推進事業) 2.総合的人材確保・育成事業 3.雇用労働条件改善事業 |
| 2.生産性の向上 | 4.経営基盤強化事業(戦略的推進事業) 5.生産工程改善・技術開発促進事業(戦略的推進事業) 6.情報化推進事業(戦略的推進事業) |
| 3.建設生産システムにおける合理化推進 | 7.建設生産システム合理化推進事業 |
| 4.建設産業における品質、安全性の確保 | 8.総合的品質向上推進事業(戦略的推進事業) 9.総合的安全対策事業 10.総合的環境対策事業 |
| 5.建設産業の国際化への対応 | 11.建設市場国際化事業 |
| 6.不良不的確業者の排除 | 12.建設業法等尊守促進事業 13.共同企業体適正化事業 |
| 7.建設産業に対する理解の増進 | 14.建設産業広報推進事業 15.建設産業文化創造事業 |
【コア・コンピタンス】
企業形態の大小に関わらず、かならず「コア・コンピタンス」は存在します。
自社がここまでやってこれたその基盤はなんだろうかと、自問してみてください。
問題は、その答えがこれからの時代に通用するかどうかです。
![]()
桃知商店
(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998.All rights reserved
ご意見・ご感想はメールにてお願いいたします。
pinkhip@dc4.so-net.ne.jp