
店主戯言00212_01 2002/12/01〜2002/12/10(上旬)
"There goes talkin' MOMO"
About桃知|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言 |2002年11月後半へ| 2002年12月中旬へ|著作権|店主へメール
2002/12/10 (火) ▲ ▼
【津】
■津にて目覚めました。
外は寒そうなのですが、ホテルの部屋にいる限りでは、日も当りもよく、気持ちのいい朝です。
■熊本県議会議事録
昨日の移動は新幹線内爆睡(笑)のようで、切符をいつ確認に来たのかもわからず・・・
でもちゃんと名古屋の前で目覚めるのは習性のようなものでしょうか。
出掛けにポストに郵便物が入っていたのですが、それは「平成14年9月定例会
熊本県議会会議録」でした。
これは大西県議が、熊本県のCALS/ECに対する取組みに対しての質問をしたときに、私の名前を出してくださったもので、ちゃんと私の名前が活字になって熊本県議会議事録に刻まれた、というものなのです。
その記念に(?)大西県議が手配をしてくださったものです。
大西さま、お心遣いありがとうございます。
そして35回目の誕生日おめでとうございます。
新幹線での移動中に読もうと思ったのですが、先にも書いたとおりのていたらくでございまして・・・
■昨日の北海道からのメールの続き
それはさておき、軽い気持ちで「可笑しい」なんて言ってしまったことに、深く恥じ
入っております。
あらためてニュース等を見ますと、かなり大変な事になっているようですね・・・
「転倒事故相次ぐ」とか「通勤の足混乱」の文字を目にする度、自分の視野の狭さに
落ち込んでおります。
自分の家族や同僚にそんな事態が及ぶと思ったら・・・です。
特に飛行機のダイヤの乱れが続くことは先生にとっても、とても深刻なことでした。
無神経な発言に自己嫌悪であります_(._.)_ |
正直なところ、私も、他人さまの不幸を喜んでいたりするときがあって、そして自己嫌悪に陥るときがあります。
そして、自分自身が同じような目で見られていたら・・・と思うとたまらなく悲しくなります。
多くの方々は、地場型中小建設業の置かれている立場を、まるで昨日の雪で苦労する首都圏のように感じているかもしれません。
私はそれを悲しいことだと思っています。
2002/12/09 (月) ▲ ▼
【雪】
寝覚めれば浅草は雪です。
浅草寺の五重塔はモノクロにけぶっていて、アサヒビールの黄金のう○こは、雪のカーテンに視界をふさがれて見ることはできません。
最近ですと雪は北海道でしか見ていませんが、東京は雪に弱いところですので、今日の移動に支障がなければよいのだが、と心配しておりました。
早速、北海道からのメールです。
東京は朝から雪のようですね。
ニュースに「積雪のおそれ」と表示されるたびに、「ああ、東京ではおそれる」のだ
な、と思いなんだか可笑しくてたまりません。
こちらでは「明日は氷点下20度の見込み」とか、「積雪1mが予想される」と、ぼちぼ
ち「おそれ」だす程度です。 |
ああ、その通りでして、私はこのまま降り続けて積雪してしまうと、雪道を歩くための「靴」が無いことを恐れているのです。
【エイジ・オブ・アクセス】
■桃論ハンドタオル&切手送付手続き完了しました
桃論ハンドタオルが出来上がってきましたので、切番ゲッターの皆さんへ桃論ハンドタオル&切手の送付手続きを昨日完了いたしました。
お近くの方には本日中に到着予定、九州と北海道の皆様には明日には届くと思います。
■浅草桃塾1回目終了
土曜日(7日)は浅草桃塾の第1回目でした。
今回は、塾生である八木沢さんから栃木建協さまの取組み、吉川さんから空知建協さまの取組みの事例を発表してもらうことから始めました。
浅草桃塾は、私にとっては実験的なもので、狙いは「桃論」以降への展開です。
その意味で、「自らを自らの言葉で語る」ということの理解を、事例発表を通して最初に理解していただければと思ったのですが、私の整理不足もあり、ちょっと空回り気味でしたので次回は若干の方向修正と、補習を準備することにしました。
といっても、桃塾ですから飲みニュケーションを欠かすことはできません。
米久での牛鍋から始まり、2次会、3次会と、きっちりとつながりを作っていただきました。
まずはここから始めるのが桃塾の流儀でございます。
次回は午後1時15分開始の6時間の授業(延長あり)という形になります。
聴いている方々ももちろんですが、話す方(つまり私)もハードな授業となりますので、体調を整えておかなくてはなりません。
受講生の皆様次回も宜しくお願いいたします。
■ということで、7日の浅草桃塾で紹介した二冊の本
ソーシャル・キャピタル―人と組織の間にある「見えざる資産」を活用する−
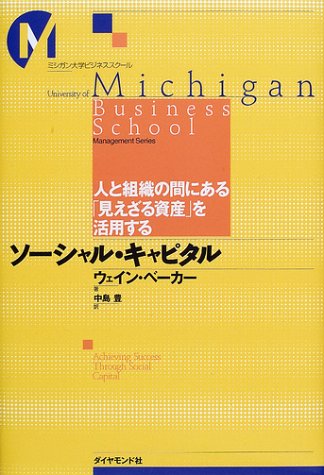 ウェイン・ベーカー(著) 中島豊(訳)
ウェイン・ベーカー(著) 中島豊(訳)
人間同士の関係性、つまり相互に価値を生み出すネットワーク(ソーシャル・キャピタル)こそが、競争優位の資産(コア・コンピタンス)だという視点から書かれた本であることで紹介しました。
内容的にはいかにもアメリカのビジネススクールの臭いが充満するハウツー本になってしまっているところもあるのですが、今という時代に、「強い個人」を前提とする国である米国で、このような人間同士の「関係性」に注目したビジネスの授業が行われていることに注目していただきたいのです。
エイジ・オブ・アクセス ジェレミー・リフキン(著) 渡辺康雄(訳)
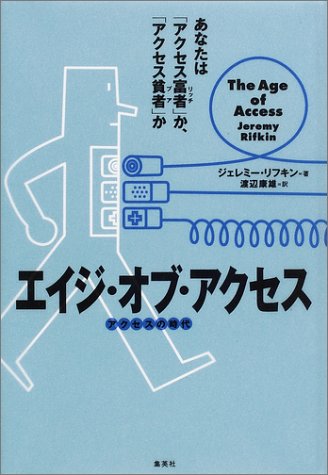
「と学会」というはご存知でしょうか。この本は20年前なら、間違いなく「とんでも本」といわれているはずのものですが、仮説などというものは、いつもとんでもなくてシンプルなほうが力があるものです。
経済合理性を追求する「電卓にすこし毛の生えたような経済人」(フリードマンのことば)という仮説を証明するために、経済学が科学として発展してきたように、時代や社会という概念に対するある仮説を立ててそれを検証しようとすることで、私たちは「今という時代」を理解できるのだと思います。
この本は、「今という時代」を「アクセスの時代」だといいます。それは脱モノ化の時代であり、所有することを絶対としない時代であるとする仮説なのです。
『桃論』は今という時代をインターネット社会である、という仮説を立てた上で展開されていますが、それは「アクセスの時代」という仮説に通じるものがある、というよりもアスセスの時代そのものなのです。
ですから、「アクセスの時代のビジネスの成否は、市場でモノを売りさばくのではなく、顧客と如何に長期的な関係を維持するにかかる」というリフキンの主張と、そこにソーシャル・キャピタルという「人と組織の間にある見えざる資産」の存在を重ね合わせたとき、ITはなにを扱うものかが見えてくるはずです。
リフキンはフランスの経済学者アルベート・プレサンの言葉を引用してこういっています。
「その機械が処理するのはモノではなく関係だから」
■つまり、浅草桃塾は・・・
つまり、浅草桃塾は、今という時代の仮説の把握と、ソーシャル・キャピタルという「人と組織の間にある見えざる資産」の存在の理解から始まったのですが、それには私自身の整理不足があった(説明することばが自らのモノになっていなかった)というのは否めなかったのは確かだと感じています。(反省)
でも、飲みニュケーションがそれを補ってくれたと感じています。
偉大なり、「ヒューマン・モーメント」(F2F:こんな略語ありか?、フェイス・ツー・フェイスのことです)
■今日は津へ
今日は明日午前中の仕事にあわせて、午後から津へ移動です。
2002/12/08 (日) ▲ ▼
【完全休養】
休養の為お休みをいただきました。
2002/12/07 (土) ▲ ▼
【早朝の戦い】
早朝の戦いを制したのは、
409999 熊谷さま@世話人代表
410001 平田さま@岩見沢
41万は申請なしでございます。
今回は、デジはん屋の古田さまのご好意でこんなのもついております。
(↓)
 |
竹炭小袋さん
これに桃論デジはんラベルをつけます
パソコンの電磁波を防ぐものです。
(健康に注意してパソコンを使いましょう!?)
マイナスイオン探知機で証明された一品です。
(強引添付)
By デジはん屋の古田さま |
ということであります。
ここ数日一お連カウンターが不調のようで、逆に切番で遊ぶには楽しかったのではないでしょうか?
次は42万となります。カウンターの不調が無ければ(笑)クリスマスと重なる頃になるかと思います。
また遊んでやってくださいませ。
それで、最近の月に二度の切番ペースは、私も少々つらくなってきましたので、年明けからは2万単位で参りたいと思います。
今日は浅草桃塾です。東京は雨ですけれども熱く一日を過ごしたいと思うのでした。
2002/12/06 (金) ▲ ▼
【41万告示】
桃知@札幌です。これから帰り支度なのであれこれ書いている時間がありません。
なので、恒例によりまして、「41万ヒット間近です」のお知らせです。
今回の景品は『桃論』デジハンでございます。
これを前後賞を含め3名さまに贈呈いたしたいと思いますので、遊んでやっていただければ幸いでございます。
ということで今日はこれからばたばたと東京へ戻ります。
そうそう、昨日講演をしましたニューカントリー21さまより、『桃論』150冊のご注文をいただきました。
深く深く感謝申し上げます。m(__)m
では、続きは東京についてから・・・
2002/12/05 (木) ▲ ▼
【@札幌】
■イントロダクション
今はといえば午前2時50分、昨日の朝の早起きが効いて、昨晩は10時前に眠ってしまったものですから、目覚めたらこの時間だったわけです。
振り返ってみると当日の送迎を受け持たせてもらったお陰で、約2時間
車の中や昼食しながら桃知先生といろいろ話が出来て良かったなあと
いうのが実感です。
「自分や会社がご近所と、どの様な関係なのか。都会の側から見ると
地方都市には残っているだろうと思われた義理人情や近所付き合い
(コミュニティ)が、以外と稀薄なってきている。しかし東京の下町には
まだまだそういった雰囲気が残っているんです。」と言う事や、
「インターネット上のバーチャルな世界ではお金を取るのが難しい、
やはりリアルな世界からしか金は取れない。」
「子供に炭坑を見せたいので、この冬は一緒に北海道へ行く」 など等
何も分からずに桃熊会のお手伝いをさせていただきながらコミュニティ・
ソリューションやミームを伝えていく事の意味がやっと少しずつ理解でき
るようになってきました。
桃知先生、桃熊会ほかご参加の皆様へ感謝です。 |
これは、桃熊会のメーリングリスト(そういうものが最近できました)に、「熊本独演会2」終了後に投稿されていたものですが、今日はこの投稿をイントロダクションにして書き始めたいと思ったのです。
ところで、投稿主の馬場口さま、当日は大変にお世話になりました。
遅くなりましたが御礼申し上げます。m(__)m
■偉大なる産業の遺跡
この投稿にある「子供に炭坑を見せたいので、この冬は一緒に北海道へ行く」を実行しに、昨日は三笠市にあります砂子炭鉱三笠露天鉱を訪問して参りました。
 |
 |
| 砂子炭鉱 |
中央に写っているのは私(笑) |
→三笠市の概要
砂子炭鉱は、北海道でも数少なくなった炭鉱で、それも露天掘りをしている炭鉱です。
国内最後の炭鉱であった太平洋炭鉱は今年閉山してしまいましたが、北海道では、こうした露天掘りの炭鉱がまだ10箇所程度残っているそうで、供給先は火力発電、つまり北海道電力がほとんどということになります。しかし、この需要さえも価格競争力のある外国産の石炭に押され気味とのことです。
昨日は、砂子組石炭事業部の皆さんに大変お世話になり(というよりもご迷惑をおかけしながら)、発破の瞬間を見せていただいたり、弩級の重機をお見せいただきました。
「石炭」や「炭鉱」ということばが、われわれの日常から消えてしまったのはだいぶ前のような気がします。今の若い人たちに石炭という燃える石を実際に見たことのある方々は少ないはずです。
私たちの世代は、小学校は石炭ストーブが当たり前でしたが、時代のうつろいというのは、エネルギーうつろいであるのだなぁ、とそんなことを考えておりました。かつては炭鉱の街として賑わったであろう三笠市も今は人口2万人を切る「市」となってしまっています。
露出している立坑での採炭跡を見たとき、「偉大なる産業の遺跡」という言葉がふと出てきました。
■さて、そして都市部のコミュニティ志向へ
さて、次は先ほどの紹介したメールにもあった、都市部でのコミュニティ志向についての論文を紹介しておきましょう。
「都心生活者はなぜコミュニティ志向が高いのか−ネットコミュニティ論考」
この論文はある程度「コミュニティ」についての知識がないと読めないかもしれませんが、そういう方は結びの部分に注目していただければよいかと思います。
『人々は「多様」さと「自由」を求めて都市型ライフスタイルを送っているのだが、生活していくのに本当に必要な「情報」の「質」(その一例として「直接会う」ことを通じて確かめる)というものが、「継続的」な関係から生み出されているということに気付きつつあるのが現在である。その顕れがコミュニティ志向であり、現段階では「セグメント化」と「ステージ化」されたネットを中心としたコミュニティなのである。ただし、継続的な関係を構築するためには何らかの制約が必要であり、「代替」が容易という意味で制約が少ない現段階のコミュニティではその関係構築への道程は遠い。ネットコミュニティはこの段階であるが、徐々に共同体志向を併せ持ったコミュニティが顕現していくものと思われる。何故なら、人は「強い個人」だけでは生きていけないということを、次第に認識しはじめていると筆者は考えるからである。
』
ソーシャル・キャピタルを主眼としたコミュニティ・ソリューションを考えていくと、結局このような立場になってしまいます。それが正しいのかどうかはわかりませんが、とにかく世の中の動きは、市場原理主義がはびこる程に、コミュニティ志向が強まることは否定できないものだと考えています。
それは、どのような人間でもそうなのですが、自分自身という存在を考えたときに、『人は「強い個人」だけでは生きていけないということを、次第に認識しはじめている』という事実は否定しようもないことだからです。
自助・自立を強いる社会は、実は本来の人間社会からは遠く推理した社会でしかない、ということだと考えています。
我々人間社会とは、情報の相互作用で成り立っている社会的交換の場であり経済取引−つまり経済的な交換というのは、社会的交換の一特殊形態にすぎない、というのが『桃論』の主張ではありますが、そこで大切になってくるのは、情報の量ではなく質なのであって、その情報の質を担保できるもの、つまり交換の潤滑済こそが「ソーシャル・キャピタル」ということになります。
なので私は自分自身が自らの職業において競争する者であることは否定しませんが、その競争での私自身のコア・コンピテンシーがなにものであるかといえば、それは私自身が多くの方々との間に築いてきた「ソーシャル・キャピタル」なのだろうと考えているのです。
それだからこそ、私の立場は「反古典の経済学」なのです。
そしてこのソーシャル・キャピタルの実践は、「バーチャルな空間」と「リアルな空間」での活動のハイブリッド化されたものだということ、つまり、「インターネット上のバーチャルな世界ではお金を取るのが難しい、やはりリアルな世界からしか金は取れない。」なのです。
わかるでしょうか?
■そして『桃論』
相変わらずamazonでの販売は順調なようで、今朝は2,363位におりますが(これでも凄い!)昨日は200位代に上がっていた時もあったようで、これも9位にランクインのおかげでしょうか。
昨日は空知建協さまから100冊の追加注文を承りまして、著者としては感謝しまくり状態なのでありました。m(__)m
岩手から。
じゃじゃ麺ファンクラブ名誉会長みるきいでございます。
先日お知らせしたみたけのエムズ書店に今日行ったところ相変わらず
新刊平棚コーナーでしたが、先日は2冊あったのが1冊になっていまし
た(^^)/と、いうわけで桃論、岩手県盛岡市のエムズ書店にまだ一冊は
あります。 |
ということで、岩手でも1冊は売れたらしいですし、(↓)熊本でも売れたようです。(笑)
実は今日『桃論』2冊目、紀伊國屋書店熊本店にてゲットしました。
熊本市内で2店目、2冊目です。山崎さんの本、初めて見ました。5冊ありました。
(大村さん、一般の方の眼にとまる機会奪ってスイマセン)
やはりトーハンONLINEでも在庫なしだそうで、怪でございます!
先日買った1冊目、家に帰って開いてみたら、しっかりP.16に真っ黒な
指紋大のシミがついておりましたので、再度保存用に購入しました。
(学生時代アイドルの写真集も2冊は買った事がないのに…)
まだじっくり読んでないのですが、まず気付いたのはレイアウトの大胆さ。
これまで俳句や詩集以外で、行間を取った書物あまり見た記憶がありません。
デジタル時代の桃知先生らしい表記方法なのでしょうが、きっとこれは
桃知先生ならではの「行間を読め!」と云う事かと勝手に解釈しております。
「これってどういう意味」、「うちの会社だと何の事」、「本当にそうかしら」
などと、足りない頭でメモを書込みながら自分のものにしたいと思います。 |
『桃論』は、その表題と、です、ます調の文体に「軟弱な」本だと勘違いされるかもしれませんが、実はかなり「硬質」なものです。
ですから読み解くには相当な「力」が必要となります。
例えば、まにあ1号はこういいます。
桃知さんは「答えは無い」とおっしゃられているので
多分、解釈の「正解」は無いとも思いますが・・・
「町にでる」とは「動き出せ!」ということだと受け止めています。
ここでいう「町」の定義はいろいろかもしれませんね。
市岡常務のおっしゃるとおり「桃知コミュニティ」でもいいでしょうし、
私は「地域住民と各社のコミュニティ」をつくる・・・でもありだと考えますし、
「役所と空知建協の各社のコミュニティ」でもありとも考えます。
または「各社の社内コミュニティ」でもいいのかな・・?と考えます。
とにかく「人と人がつながる場所」ならどこでも・・・じゃあないでしょうか?
動き出せ・・・はつながり(コミュニケーション)を構築すべく動き出せ!
と受け止めています。
これは、われわれベンダーもまったく同じですよね。
「書を捨てずに」・・・・というのは「いつも常に考えて」
と言う風に私は受け止めています。
「勉強しないとだめだよ」と言われているよう感じててます。
めくらめっぽうに動き出すのもよいけれど、
つねにより良いコミュニケーションを得られるよう「知識武装・理論武装のため、
勉強しなさい」といっていると受け止めています。
桃知さんは「イントラネットの存在」を「前提条件」にされていますので、
経営者の皆さんは、「外出先からでも社内としっかりコミットできるように
PCを持って出かけなさい。」とおっしゃられているのかもしれませんね。
また、モバイルがあれば外出先からでも、インターネットというミームプールに
接する事ができます。
つまり、ミームをつくり、受け止め、なすりつける・・・という作業をはじめなさい!
といわれているのかなあ・・・という解釈をしています。
書をすてずに・・・・自ら勉強して考えてミームを醸成し、
町に出る・・・動き出す。
パソコンを捨てずに・・・ミームをみずから作り出し、
町に出る・・・ミームの散布、なすりつけに動き出せ!
なんかちょっと違うかも知れませんねぇ・・・もう少し考えないとだめですね。(笑) |
そしてA木さまはこういうのです。
例えば、「桃論」を探すためにみんなが
書店に行く。たとえ桃論が見つからなくても
並んでいる本を眺めると「今という時代」がほんの少し透けて見えてくる。
このプロセスがすごく大事なことであり、「書を捨てずに町に出よう」
の第一歩なのだと思います。
また、硬質な「桃論」を読破できれば、
「桃論の背景〜25冊」も少しずつ読みこなせるようになるでしょう。
知らず知らずのうちに「読力」がつき、必然的に「なぜ?」を考えるように
なると思います。
そこに行き着く「ち密な制度設計がある」から桃知さんは他の経営コ
ンサルタントとはまったく違うのです。
縮小均衡時代の「解答らしきモノ」を持ち合わせた、日本で唯一の
コンサルタントなのです。そして、その出発は「分からない」から始まる
のです。 |
ほめすぎです。
2002/12/04 (水) ▲ ▼
【結果がでるということ】
■『桃論』、9位にランクイン!
『桃論』ですが、<『桃論』瞬間風速ベストセラープロジェクト>への皆様からの多大なるご協力のおかげで、八重洲ブックセンター売り上げランキングの、ビジネス書部門の9位にランクインすることができたようです。
速報版としては、次の二つで確認できました。
→yahooニュース
→gooニュース
でも八重洲の階数別のベストセラーには出てきてはおりません。
これは、インターネットだけでも540冊程の売り上げ(店舗でも250冊程出ているということなのですが、八重洲は一括大量買いを低カウントしてしまいますので・・・)の結果だと理解しております。
昨日いただいておりました川さんからの速報メールです。
何気なくネットでニュースを見てましたら、
八重洲ブックセンター本店(11月24日―30日)
【桃論】 ビジネス書第9位堂々登場!
並み居る出版社(エクスナレッジさんスイマセン)や
特にトヨタや日本経済、世界金融のタイトル文字の中で
ひときわ三千と輝く
【中小建設業】の文字!!!
これだけでも、地域の人々や納税者の方々に
よく見えていなかった地場の中小建設業者の存在とその
構造的な問題点を見えるようにして下さった功績は
とてつもなく大きいものだと確信しました。
時間が少少経ちますと様々な方々から反響の声が返ってくると思います。
その波紋はきっと、さざなみになり、小波大波になり。。。
「打倒ハリーポッター作戦」は、大成功ですね!
「窮鼠猫をかむ」ということもありますから、
ハリポーッターさんにはこの辺でしゃんしゃんとよしなにしては
いかがでしょうか?!
桃知先生、おめでとうございました。
追伸
建設業の不祥事の嵐の中、
タイトルの【サバイバル】の内容にどれだけ多くの人々が
内容を理解して、共感をしてくださるのだろうか?
ネット+本>口コミ は間違いないでしょうね! |
私の素直な感想は、「やってみるものですなぁ・・・」というものです。
これはある意味、私とベストセラープロジェクトに参加くださった方々のソーシャル・キャピタル(そう言えるのならですが)の結果なのだろうと思います。
そして、これは皆さんが実際に動くことによってもたらされた結果なのであって、動かなかったらなにも起きなかったものであることを是非に感じていただきたいと思います。
つまり、(すべてのことは)思っているだけでは結局なにも伝わらないままに終わってしまいます。
思ったら行動すること、それも闇雲にではなく、その目的を達成するためにはどうしたらいいのかを常に考えながら、そして、そこでソーシャル・キャピタルがどう機能するのかを考えながら・・・、つまり、動きながら考え、状況に応じて動きを調整する。
そのようなことを実感しております。
今回のプロジェクトは遊びであり祭りでもあります。
でも、そこには遊びなりの戦略が存在していたわけで、その戦略がネットの中だけで伝えられ(実際に集まって宣伝されることも無く)、でもこうして結果が出てくること、それが、ソーシャル・キャピタルの大切さを私に確信させているのでした。
プロジェクトに参加していただいた、そして『桃論』を購入してくださったすべての皆さんに感謝申し上げます。
そして、今後とも尚一層のお引き立てをお願い申し上げます。m(__)m
まだ戦いは始まったばかりで終わったわけじゃありませんから。
■しかし、『桃論』は現在入手困難な模様です
新潟の田中さまからのメールです。
先生、田中です。大変な人気じゃあないですかぁ。
新空衛で100冊の承認がおりましたので早速申し込もうと、但し、インターネット申し込みではベストセラーにカウントされないと戯言がおっしゃるので、近くの書店に安易に頼みましたがそんなに集められない、キャンセル待ちになるでしょうと。
それでは「やっぱ天下の紀伊国屋デショ」と頼みましたがこちらも返事は、「売れ行き抜群で出版元にも在庫ナシとのツレナイご返事。
一体どうなってんノォーー???としょうがなく、
amazon.com桃知に申し込みしました。在庫はどこに隠れているんでしょうかねー?
こんなことなら100万部ぐらい刷っておくんでしたねーーー。
いんや〜〜〜、楽しいことです。
新潟はきのう、きょうといいお天気で平和でーーす。
では。 |
新空衛さま、『桃論』100冊の大量購入まことにありがとうございます。m(__)m
心より感謝申し上げます。
しかし、本当に『桃論』はどこへ行ってしまったのだろうか?
こうなれば予約するしか方法がないのですが、amazonもここのところ「お取り寄せ扱い」状態が続いておりますし、発売2週間程で「お取り寄せ」はないだろうなぁ、と著者は素直にそう思うのです。
■ソーシャル・キャピタル
ところで、昨日は久しぶりに門倉組さんへいってきましたが、最近ご担当がかわってしまっているので、どうもうまくコミュニケーションができないもどかしさを感じてきました。
共通の言語で話せないものどかしさと、居心地の悪さを体感してきましたが、私にとっての居心地の悪さ、というのは決してネガティブなものではなく、ソーシャル・キャピタルがなくなってしまっていることを教えてくれているとても大切なものです。
ですので、まずは新しいご担当とコミットすることが先決であることを感じてきました。
このソーシャル・キャピタルという概念こそが、『桃論』の中枢にあるもので、それが自社のコア・コンピタンスであることを、そして、ミームによって運ばれる感動こそがソーシャル・キャピタルのエンジンであり、ITで扱う情報がミームのことであることを理解できないと、私との共通の言葉をもてないことになってしまいます。
そこには発展的なコミュニケーションが存在するわけもないのです。
なので、『桃論』を送ってあげることにしました。
ちゃんと『桃論』読んでくれれば嬉しく思うのでした。
この事例は、私を取り巻くすべての人間関係において共通の大切なことを言っています。
それは「居心地の悪さ、というのは決してネガティブなものではなく、ソーシャル・キャピタルがなくなってしまっていることを教えてくれているとても大切なものです。」
さらに言えば、「居心地の悪さ」を中小建設業は実感しているはずです。
その問題解決方法を私たちは考えているのですから、「居心地の悪さ」を避けることは問題解決の前に問題を投げ出しているに過ぎないのだと思います。
■そして本日は北海道へ
今日はANA 057 東京(羽田)(0900) - 札幌(千歳)(1035)で北海道へ飛びます。
砂子組さんに無理を言って、露天掘りの炭鉱を見せてもらうことになっています。
その後、空知建協でIT化推進委員会の会議です。
夜は、札幌の超ごひいきの鮨屋「ふじ田」で一献の予定です。
明日は、午前中にA木さまの取材を受け、午後からニューカントリー21さんの会合で講演をいたします。
では、行って参ります。
2002/12/03 (火) ▲ ▼
【『桃論』】
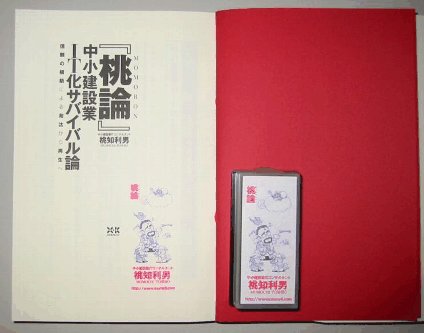 |
■『桃論』デジハン
なんだかわかんないものが次から次へと登場する『桃論』グッズなのでございました。
これは製品でしてちゃんと販売してくれるものでございます。
但し、限定10個とか・・・(注:桃知商店が売っているわけではありません。デジハン屋こと古田さん@宇佐美組%岐阜県大垣市が販売者でございます)
だれが買うのか?という大きな問題も抱えておりますが、洒落がわかる人でしたら使えるかもしれませんね(笑)。 |
上(↑)の画像クリックしてみてください。
大きな画像&注文画面が開きます。
|
■一方『桃論』はといえば
amazonでは、現在「お取り寄せ」の扱いです。
品薄というよりは流通がうまくいっていないような感じでございます。
書店では手に入りにくい『桃論』でございますので、amazonを利用される方も多いかと思いますが、ご迷惑をおかけいたしております。m(__)m
「無名」というのはつらいものでございます。
とにかく、私は世間一般では「無名」なのでございます。
それを超える力の源泉は皆様のご支援でしかございません。
・・・ってだんだん選挙の演説じみてきのでやめましょう。(笑)
それでも今朝の売り上げランキングは2,568位。
上がったり下がったりしてはおりますが、まだまだ元気なようです。(笑)
■川さんからのメール
桃知先生、こんばんは。川です。
素晴らしいパーティー本当にありがとうございました。
発起人の皆さんも大変素晴らしかったです。
集まった皆さんも誠に素晴らしい。
素晴らしいの究極かたまり状態でした。
全国から集まった物産品の物的相互作用も素晴らしかった。
全国から集まった人々の第一種情報的相互作用も素晴らしかった。
それとなんといっても凄かったのは。。。
全国から集まった人々や無念にも集まることが出来なかった人々を含む
第二種情報的相互作用であり、これがまた素晴らしかった。
>そんな新 しいコミュニティを作れれば楽しいなぁと思うのです。
たぶんその胎動を皆さん全員共有して感じ取ることが出来たと思います。
これが最高に素晴らしかった。
かくもこんなに集まった(ネガ)写真を今日送りました。
でも桃知先生はそれを見る間もなく、余韻を味わうことなく、
吉田拓郎のあの祭りの曲も変わり
「空を飛ぶ事よりは地を這うために、口を閉ざすんだ臆病者として」
「超えるものは全て手探りの中で、見知らぬ旅人に夢よ多かれ」
「越えてゆけ そこを 越えて行け それを今はまだ 人生を 人生を語らず」
といった感じなのでしょうね?
私も現実に向き合って、思考して、それを少しでも実行して行こうと思います。
桃知先生、エネルギーを沢山いただきまして、本当にありがとうございました。
心を込めて感謝致します。
追伸
皆さんもしかしてお土産袋に(サイン入り【桃論】のみならず)色紙が入ってたんで
すか?
私の袋には、なかった。。。
もしそうであったら、私も。。。ほっ、欲しいー!(涙) |
ということで、今日は午後から門倉組さんへ。
2002/12/02 (月) ▲ ▼
【momoZ】
今朝方見た夢で「おとりさま」がでてきたものですから、お参りに行ってきたら、午後3時半だというのに浅草の空には雲が立ち込め、雨が降り出しそうでございます。
さて、その夢見のおかげか、凄いもの(画像)が届きました。
まずは見てやってくださいませ。
(↑)は熊谷@葉月会(空知建協)さまの作品でございます。
わたしゃこれを見て狂喜乱舞いたしまして、さっそく「くれ〜」と、メールを打ったのでございますが、ご快諾のメールが届いておりました。
ありがとうございます。m(__)m
こういうなんだかわからないけれども凄いもの、っていうのはもうたまらないわけでございます。
うちの家宝にしたいと思います。
皆さんにこうして遊んでいただけることを心より感謝いたしたいと思うのです。
【『桃論』を踏み台として】
■祭りは終わり・・・
A木@札幌です。
昨日はとても素敵な時間を共有させていただきました。ありがとうございます。
みなさんが地元に帰られ、月曜日からまた厳しい現実に向かって
戦うことを考えた時、桃知さんは「心の楔(くさび)」なんだと感じました。
出版パーティーに出席された方々はそれぞれ感度の高い人たちばかりで、
真剣に「今という時代」を考えておられますが、これが日常に戻ると
感度の鈍い人たちや、「志」も何もない人々と一緒に何かをやっていかなければ
ならない状況に身を置くときに、段々と気が萎えてくると思います。
そんなときに、桃知さんを含めた「薄い関係」に身を置くことで、ずり落ちそうに
なった自分を奮い立たるため、「桃知さん」という楔を心に打ち込むのでしょう。
(勿論私もそうですが…)。
なぜ、中小建設業の経営者たちが桃知さんに心惹かれるのか?その謎を解くカギ
が日本経済再生のカギなんだ、とあらためて感じました。
(ざっくり) |
このA木さまのメールは、今回の出版記念パーティというイベントの性格をうまく表現していると思います。さすがに、ジャーナリストはするどいものです。
特に、『出版パーティーに出席された方々はそれぞれ感度の高い人たちばかりで、真剣に「今という時代」を考えておられますが、これが日常に戻ると感度の鈍い人たちや、「志」も何もない人々と一緒に何かをやっていかなければならない状況に身を置くときに、段々と気が萎えてくると思います。』というフレーズには共感を覚えます。
私は建設業界しか知らない人間ですが、その業界に限っても、建設業界で働く方々の特徴は、業界もしくは自社というストロングタイズ(玄田のことば)、つまり強いつながりの持つ「安心の担保」に浸りきりの状況が続いているのだと思うのです。
→それが「危機感の共有」を邪魔しているように思えます。
→共有できる危機感のなさは、社内的、業界内的な問題認識感覚の欠如を生み出してしまい、全体としての行動が伴わないという、閉塞の大きな原因となってしまっているようです。
その原因は沢山あるかもしれないのですが、そのひとつは「世間知らず」ということに尽きるのではないかと、そう思うのです。
それは特に、経営層ではなく、従業者層でそうであることによって、変化を拒む閉塞感が組織内に充満し続けているように感じます。
(もちろん、安心の担保以外を知ろうとしない経営者さまがたくさんおられることも知ってははおりますが・・・)
経営層の方々は、少なからず業界外の方々とのお付き合いを持てる機会もあるでしょうから、まだ「うすい関係」を築くことの大切さを比較的容易に理解できるのではないかと思いますが、こと従業者層となると、閉じた組織が自分のすべてとなっている方々が多いのではないでしょうか。
私は、経営者が「今という時代」に自社の社員に与えるべき機会のひとつは、自社の枠を超えた「うすい関係」を構築する機会なのだと思うのです。(当然に自らもそうではなくてはなりませんが)
そういう意味で、今回、岩手の向田さまは、社員さまをお二人連れになってきていましたしたが、これはいい機会を作ってあげているなぁ、と関心いたした次第なのです。
そして、11月30日にも書いた玄田のことばが意味をもってきます。
『うすくて広い関係には、おカネと時間がかかる。しかしそれよりもっと大変なことがある。自分と近いが遠い非日常の人々に、自分の日常を、けっして自慢ではなく、かといって卑下でもなく、自分の言葉で語る必要が自然と出てくるからだ。「自分は、どう生き、どう仕事をしてきたか」を簡潔に、下手でもいいから(いや本当は下手なほうがもっといい)、日ごろから考えていないと、その言葉は出てこない。』
『人と人とをうすいけれども切れずにつなげてくれるのは、結局、言葉でしかない。自分から言葉を発しようとしなければ、言葉は返ってこない。そして返ってきたことばに心を空しくして耳を澄ます。そこには自分の限界と可能性について、思いがけず気付かせてくれる、日常のなかの非日常が隠れている。』
(玄田有史、文芸春秋特別版、12月臨時増刊号、p141、「うすくつながって生きる」より引用)
そこにITがあることで、私たちは「うすくて広い関係」の可能性を考えることができますし、「うすくて広い関係」がアルマティア・センのいう共感やコミットメント(使命感・・・by佐和隆光−これについては後の機会に)や、ソーシャル・キャピタルという見えない価値をを生み出す源泉になれることで、IT化は必要なのだというのが『桃論』のいうところなのです。
IT化を単なるツールだと言う方々が多いのも事実であり、私もそう思ってはいますが、実は、私のいうツールとしてのIT化と、多くの方々が言われる「ITはたんなるツールだ」との間には、その背景認識に大きな隔たりがあると感じております。
2002/12/01 (日) ▲ ▼
【感謝】
■楽しい宴会でございました。
昨晩は『桃論』の出版記念パーティを口実に、全国から100名を超える方々においでいただき楽しい一時を過ごせましたこと、深く感謝申し上げます。
沢山の花束、沢山の一升瓶、そして全国から寄せられた名産品に囲まれて、楽しい宴会となりました。
それから、出席の皆様からは多大なるご祝儀をいただきまして誠にありがとうございました。
発起人の皆様、そしてお集まりの皆様、祝電、祝メールをお寄せくださいました皆様に深く感謝申し上げます。
■御礼のご挨拶
本日はかくも盛大に『桃論』の出版を祝う会を開催していただき誠にありがとうございました。今回の『桃論』の出版は「公共工事という問題」を活字メディアにて世に出し問うことができた、ということで、私にとっては喜ばしいものではありますが、これも長い道程のほんの一歩と肝に銘じております。
今後とも力の限り皆様のお役に立ちますよう精進することをお誓い申し上げ、あわせてご参加の皆様、発起人の皆様方のご多幸をお祈りし、お礼のご挨拶に代えさせていただきます。 桃知
利男 |
ということで、今日はゆっくり休みましょう。
▼
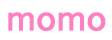
■桃知商店謹製■
(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2002.All
rights reserved.
About桃知|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言 | 2002年12月後半へ | 2002年12月中旬へ|著作権|店主へメール
![]()
ウェイン・ベーカー(著) 中島豊(訳)
![]()