

店主戯言0030502 2003/05/16〜2003/05/31 "There
goes talkin' MOMO"
About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言 | 2003年5月前半へ| 2003年6月前半へ|著作権|店主へメール
2003/05/31 (土) ▲ ▼
【自己意識(その2)、若しくは、ところで飛行機は飛ぶのか】
7月に長野県(たぶん松本)で、大きな講演会をすることが、昨日の打合せで内定いたしました。
これから詳細を決定していきます。期待してお待ちくださいませ。
ところで、本日の問題は、東京(羽田)(0925)
宮崎(1105) ANA 603は飛ぶのか、ということです。
今の所は大丈夫みたいなのですが、台風は一箇所にじっとしているものでもありませんので、羽田に行ってみないと分からないかもしれません。
■公的自意識
さて、今日の店主戯言に書かれていた「自意識について」ですが、私は3個しか○がつきませんでした・・・普通じゃないんでしょうか(;_;)
たぶん他の人からみれば「そんなことはない」と言われそうですが、自分自身で○をつけたのは1.4.9ですね。6が△という所でしょうか。
髪型や服装なんかは全く気をつけていないし、他人が自分の事をどう思うかも 気になることはありません。と、いうか「気にしてもしょうがない」と思っているからです。
人それぞれ価値観が違い、こちらがよい対応をした、と思っていても、それが逆に相手を怒らせる事だってありうると思っているからです。だから他人がどう思うかを気にするより「自分がベストをつくす」事を目標にしています。
もちろん、それが他人にとってはよい対応ではないかもしれませんが、それは 次の段階でまずければ反省してよりよい形に持って行こうとするだけです。
5番目の「自分の事を理解しようと努力している」には思わず頭を抱えました。
「理解できるのかなぁ」と考えた瞬間に頭が爆発しかけました(^^:
とても自分の事は理解できません(笑)
ガーランド(ピンクハウスよりカントリー系が入った西麻布の一軒ブランド。
BATUというアパレルが昔やっていた、ストリートオルガン・田園詩のスタッフが立ち上げた)の小花模様のピコフリル満載ワンピースにレースふりふりのエプロンドレスをつけて、みちのくプロレスを見に行き、キティのぬいぐるみ抱いて、日本酒の4合瓶をあけている主婦なんて誰も理解できないです(^^; |
という、なんとも凄まじい主婦さまからメールをいただきました。
たぶん(私は心理学者ではないので確実なことはいえない、という意味で)、確かに凄いなぁ、としか表現できない部分も、見事に自己観察されて書かれておりますので、本当は○の数はもっと多い方なのだろうと思います。
ところで、昨日は何気に「自意識」と書きましたけれども、正確には「自己意識」の方が正解らしいので、まずは訂正いたします。
では、昨日の続きです。
この自己意識ですが、大きく次の二つに分類することができるらしいのです。
1・公的自己意識
2・私的自己意識
公的自己意識が強い人とは、人からどう見られているのかが、いつも気になっている人(齊藤,p13)ということになりますが、その判断材料は、既に皆さんに提供されています。
つまり、昨日のテストで、偶数番号についている○の数が、貴方の「公的自己意識」度なのです。
(↑)の凄まじい主婦さまは、(とりあえず自己採点の範囲では)偶数番号の○はひとつだけですから、公的自己意識度はかなり低い、ということになります。
『公的自己意識の強い人は、悪い言い方をすれば、他人の目ばかりを気にする人ですが、別の見方をすれば、相手のこと、まわりのことに気配りをするタイプの人です。日本伝統の和を大切にする人ともいえます。』
『つまり、このテストで、偶数に○がなかったり一つしかない人は問題です。このタイプの人は他人のことを考えないで自分の思い通りにする、いわゆる自己チュウの人、人の和を乱す人となりかねません。』
『その意味では、公的自己意識のあまりに低い人は、日常生活や人間関係で、公的自己意識を多少とも高める必要があります。その方が日本の職場などの人間関係は、うまくいくのではないかと思われます。』(齊藤,p37)と齊藤先生はいうのです。
つまり、この公的自己意識は、人間関係と関係が深いらしくて、私たちが使ってきた言葉では、「ソーシャル・キャピタル」となにやら関連性があるるように感じます。ですから『偶数に○がなかったり一つしかない人は問題です』ということになるのでしょう。
それでは、どうやって公的自己意識を高めたらいいのか、というと、齊藤先生曰く、
『ちょっとした小道具があれば、それで十分なのです。』
その小道具とは、鏡です。』(齊藤,p37)
というのです。
鏡・・・
■私的自己意識
さて、「鏡」のはなしはペンデングして、もう一方の自己意識である、私的自己意識について簡単にまとめておきます。
これはつまりは「自己チュウ」度なのですが、この程度を自己採点する方法は、昨日のテストの奇数番号の○の数なのです。
私的自己意識も公的自己意識も、意識が外にではなく、内に向かっている点は同じです。
見ている先が自分で、自分が意識の対象です(齊藤,p54)が、公的自己意識とは、人からどう見られているか、つまり、視点が自分の外に移って、他人の眼で自分の外側を見ることであるのに対して、私的自己意識は、視点は自分の眼あるいは脳、つまり自分の内側にあり、そこから自分の内側を見ているわけです。
つまり、簡単な例でいえば、『私的自己意識とは、日記に自分ことを書こうとしたときの視点です。このときの対象は、自分の考えや感情です。今日あった出来事に対する気持ちなどについて考えることです。みじめな自分や嫌なことをしてしまった自分です。どうしてそんなことをしたんだろうと、自分の内面にある欲求や動機を考え、省みるときの意識状態です。』
『ここには自分の価値観や現実認識などが関わっています。それらによって、自分で自分を評価するわけです。ここでは、公的自己意識とは対照的に、他の人との関わりは弱くなり、自分自身の基準や感情が中心的な役割をもっています。』
『ですから、私的自己意識の高い人というのは、いま、はやりの言葉でいえば、「自己チュウ」、自己中心的な性格の人といえます。』(齊藤,p54)
ということで、これがなぜにIT化につながるのかは、全然不明のまま(まあ、勘の良い人は「鏡」が出てきたところで気が付いてはいるだろが)、このはなしは、まだまだつづくのであります。
2003/05/30 (金) ▲ ▼
【自意識過剰の自己反省なし】
■51万
51万ゲッターは、岐阜県の島さま。
+1は、岩手県の工藤さまでございました。
-1は申告がございませんでしたので、このお二人様に、特性「ももちどっとこむポロシャツ」をお送りしたいと思います。おめでとうございます。m(__)m
とは言いましても、現在在庫がありませんから、これから発注をします。(笑)
少々お時間をくださいませ。
■実践モード状態の不満のようなもの(お祭り好き)
5月も明日で御仕舞い。
なんて時間が経つのがはやいのでしょう。
5月になって(選挙の影響もなくなって)、私の活動はすっかり実践モード(コンサルテーション中心)に入ってしまっております。
昨年は、6月から9月ごろまでは『桃論』執筆モードであり、それこそ自閉症の少年のように、毎日日記のような文章を書いているばかりで、ほとんど外に出ることもなく過ごしておりましたが、今年は、しっかりと躁鬱を繰り返しながら(まあどっちかというと躁状態である時間が長いようですが)、元気にあちこち徘徊させていただいておりました。
しかし、この実践モードという状態は、当然に関与先さんでの時間を最優先しますので、オープンセミナーがほとんどないわけで(といっても講演がないわけではなくそこそこにあります。しかしオープンにできるものは皆無なのです)、これがどうも(私の芸人根性からすると)物足りない日常になりつつある。
まあ、それも予想通りといえば予定(予想)通りなのですが、私は、不特定多数の方々との接点が少なくなってしまっているようで寂しいなぁ、と、根っからのヒューマン・リレーション依存型人間の特徴的性向発揮状態なわけで、近々みんなでね、ぱぁ〜っとやれるようなイベントを浅草でやろうかしらと考えておりました。
まあ、昨年の暮れにやった出版記念パーティの、何も記念するものがないようなもの、つまり、単なる暑気払いと称したただの酒飲み、そんなものを、ただひたすらに馬鹿みたいにやろうかな、と考えておりました。
■台風4号
ところで、問題は台風4号なのです。
私は明日、宮崎にお邪魔する予定でおりましたが、台風4号が近づいて来ておりまして、果たして、明日、飛行機は飛ぶのか?というのが目下の大問題なのです。
すべては飛ぶ予定で準備していますが(当然ですね)、飛ばなかったときの代替日を考えると、しばらく行けない・・・なのでありまして、5月に台風にいじめられるなんてことになると、今年はなにか台風につきまとわれる(ストーカー行為だわね)ような予感がして、いやだなぁ・・・と。
■自意識について(その1)
次の各質問にイエスなら○を、ノーなら×をつけてください。
- 自分のしたことについて反省することが多い
- 人が自分をどう思っているのか気になる
- 自分の気持ちに注意を向けていることが多い
- 人に良い印象を与えているかが気になる
- いつも自分のことを理解しようと努力している
- 人に自分をどう見せるかに関心がある
- いつも自分がなにをしたいのかを考えている
- 自分の外見が気になる
- 自分自身の感情の変化に敏感である
- 自分の髪形や服装にはいつも気をつけている
これは今読んでいる、『自己チュウにはわけがある』齊藤勇(著)文春新書、という本からの引用なのだけれども、単純に○が多ければ多いほど自意識が強い、ということです。
ちなみに私は全部○であり、世間一般的に見れば、私は自意識過剰のとんでもないやつ、ということになっております。
私を良く知っている皆さんであれば、おい、10の髪形や服装・・・って、あれで気をつけているのか?という疑問が沸くかと思いますが、まあ気にしないでください。
それで皆さんはどうでしたでしょうか?
多分、○は5個以上はあるはずです。普通はそれでいいらしいのです。
それで、問題はなにかというと、『しかし、ここで不思議なことが分かってきたのです。意外なことに、自己意識の強い人は、本気で自己反省しないことがさまざまなデータによって明らかになってきたのです。』(齊藤,p23)ということです。
これは、私は、自意識過剰の自己反省なし、という最悪の性格の持ち主だ、ということなのです。
大変なことになってきました(笑)。多分、皆さんもそう(自意識過剰の自己反省なし)なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
と、ようやく話題をつくったところで、続きは後日。
まるで紙芝居のような終わりかただ、といっても紙芝居を知らない人も多いのだろうね。
それから、てるてる坊主つくらなくちゃいけませんね。
2003/05/29 (木) ▲ ▼
【昨夕岐阜から戻りました】
■51万
まずは、一お連カウンターでございますが、まもなく51万、ということで、まあ、カウンターの調子がよければ(時々表示されませんので)、夕方までには51万ということになるかと思います。
景品は恒例のももちどっとこむポロシャツです。色はこれから考えます。前後賞を含めて3名様ということで遊んでやってくださいませ。
ういえば、50万ゲッターの次郎さんへは、この間北海道へ行った時に渡しそびれてしまい、それからまだ送っていないという体たらく。すみません>次郎さん
■建築士の仕事
岐阜から戻りました。
昨日の岐阜は、蒸し暑い、という表現が一番似合うような、そんな日でございました。
建築士事務所協会さんのシステム設定を終え、お昼ごはんをご馳走になってから、向井先生(向井建築事務所)の車に同乗させていただいて、大垣の建設CALS/EC研修センターにちょっと顔を出し、その後、岐阜羽島駅まで送っていただいて、17時丁度に、東京駅に着くのぞみに名古屋駅で乗換えて帰ってきました。
その事務所協会、CALSセンター、そして岐阜羽島駅までという移動の道すがら、向井先生が管理されている現場を二箇所拝見させていただきました。
どちらも、若いご夫婦からのご依頼、コンクリート打ちっぱなし部分を持つ、そして、私のいうソーシャル・キャピタル的な受注経過、という共通した特徴があり、設計的にもかなり楽しく(向井建築事務所の作品例はホーム・ページに詳しい)、これがそのまま、今の向井建築事務所の仕事を象徴しているように感じてまいりました。
私は、久しぶりに建築現場へ入らせていただきましたが、きちんと管理されている現場は、見ればわかるでして、向井先生から出る小言の一つも、若い監督員にとっては勉強になるだろなぁ、と素直に思えるし、こうして伝承される技術というのも、またミームなのだな、といつもの職業病的発送をフル回転させられたのでした。
しかし、向井先生が言うと、「今頃の現場監督は技術が落ちた」「昔は、わしらが現場の監督から色々と教わったぐらい、(経験的。技術的に)しっかりした人が多かったものだよ」という言葉も、なるほどなぁ、と思わせられますし、「勉強が足りんのや」という言葉も、自然と重みを感じるのでございます。
6月7日の法大の講座では、向井先生はこのあたりのお話をいただく予定でございます。向井先生は岐阜県建築士事務所協会の会長ではありますが、今回は、事業者団体ベースのIT化の話ではなく、ひとりの建築士(プロフェッショナル)の仕事についてのお話をお願いしています。そして、そこには当然にITがあるのですが・・・まあ、こんな話、学校では絶対に教えてくれません(笑)。お楽しみに!でございますね。
■脳みそが崩れ落ちている(情報論)
 一昨日の郡上のこと(どこで何を食べたのか)も記録しておかなくてはならない、と考え続けてはいたのですが、なにぶん最近はお酒の席でのことは見事に忘れているわけで、つまり色々な部分を持った脳みそ細胞が破壊され欠落しているわけで、今回の食べ物の白眉は、「豚平焼き」というものなのですが、これを出していた店は・・・???思い出せないでおりました。
一昨日の郡上のこと(どこで何を食べたのか)も記録しておかなくてはならない、と考え続けてはいたのですが、なにぶん最近はお酒の席でのことは見事に忘れているわけで、つまり色々な部分を持った脳みそ細胞が破壊され欠落しているわけで、今回の食べ物の白眉は、「豚平焼き」というものなのですが、これを出していた店は・・・???思い出せないでおりました。
←これが「豚平焼き」(この名前さえうる覚えなのです。本当は違うかもしれません。)
そこで、こうして携帯で撮った解像度の低い画像を、メモ代わりに使ってみるのですが、この記録の断片のようなものもつまりは情報なのであります。
しかし、この情報(画像)からは、味や匂いや、この店の親父の気難しさや優しそうなおかみさん、なんていう店の雰囲気なんかは伝わらないでしょう。
しかし、ここに私が、「豚の三枚肉をネギと卵で包んで焼きあげただけのシンプルな料理なのだが、こういうのは、この店の雰囲気ごと、ものすごく私の好みなのであります。」等と書くと、ちょっとばかり事情が変わってくるわけです。
つまり、この情報は、自分(貴方だね)の脳みその中でなんとか理解されようとします。そこでは、過去の似たような記憶(シンボル)をたぐり寄せるはずです。
貴方は、過去に自分が味わったものの中で一番近いものの味を思い浮かべているはずですがいかがでしょうか。
しかし、ここで似たような経験がないと、本物とはまったく違った味を思い浮かべることになるわけです。
例えばケチャップ味とかね(笑)
だから、情報なんて結構いい加減っていうか、個人の主観(養老孟司のいう「Y=aX (Y=出力
X=入力 a =脳の中で掛け合わせる係数)でどうにでもなってしまうものだ、という話でございます。
この係数 a が、学習を重ねた結果変化するものだとすれば、この係数
a とは、つまりは経験なのです。
人間の解釈を左右する係数としてのミームとは、個々の人間の経験なのだ、と考えていいでしょうし、それこそ「現実の重み」なわけです。
それで、この経験から学ばない方を馬鹿と呼ぶわけですが、この定義に従えば、我が国の首相はびったしこれに当てはまる、と。(まあ、これはどうでもよいのですが・・・)
ここで唐突に、やっぱり「かわいい子には旅をさせろ」ですね。
これは「海馬」の話と合体していくわけですが、脳みそは本当にすごいなぁ、と思いながら、詳しくは後日においておいて、今日はここまでございます。
2003/05/28 (水) ▲ ▼
【@岐阜】
桃知@岐阜県建築士事務所協会です。
今朝は、郡上八幡城下町プラザを 8時5分に出るバスに乗って岐阜まで移動して参りました。
昨日も、この高速バス(逆方向)を使ったのですが、新岐阜からの乗客は3人で、私が降りるまで、ずっと乗客は3人であり、なんともほのぼのとした(?)高速バスに。
今朝は、郡上高校に通う高校生でいっぱいで、私は郡上高校までは立っておりましたが、郡上高校を過ぎれば、残りは10人程度の乗客で、高速道路をのんびりと(?)岐阜まで移動して参りました。
というわけで、本日は岐阜県建築士事務所協会さんでシステムのメンテナンス作業ですが、本日中に浅草へ帰る予定です。
ですので、また夜にでも更新できればと考えております。
では、ごきげんよう。
2003/05/27 (火) ▲ ▼
【新聞読み(しんもんよみ)】
■東北地方で震度6弱
昨夕、お風呂に入っているときに大きな地震がありました。
私の住居はマンションの10階にあるせいか、地震のときは大きく円を書くような揺れかたをします。
これはなかなかに気持ち悪いのですが、それが昨日は結構長い時間ぐるぐると回っておりまして、丁度ゆっくり回る皿回しのような状態なわけで、非常に気持ちが悪うございました。
震源が岩手県沖と聞き、驚きお見舞いの電話をしようとしましたが、案の定、地震直後は電話がかかりにくい。そのためメールを何通か送らせていただきましたが、皆さんご無事なようでなによりでございました。
ただ、被害にあわれた皆様も多いようです。お見舞いを申し上げます。
まだ余震は続いているようですし、ご注意くださいませ。
■ちょっと古い新聞から
日建連会員企業1990年からの受注動向
出典:日刊建設通信新聞2003年5月8日
| 官民構成比(%) |
年度 |
官公庁構成比(%) |
| 民間 |
官公庁 |
国の機関 |
地方機関 |
| 76.9 |
23.1 |
1990 |
42.4 |
57.6 |
| 74.2 |
25.8 |
1991 |
42.2 |
57.8 |
| 64.5 |
35.5 |
1992 |
42.9 |
57.1 |
| 60.3 |
39.7 |
1993 |
43.2 |
56.8 |
| 61.7 |
38.3 |
1994 |
41.2 |
58.8 |
| 58.6 |
41.4 |
1995 |
44.8 |
55.3 |
| 64.3 |
35.7 |
1996 |
43.2 |
56.8 |
| 66.3 |
33.7 |
1997 |
44.1 |
55.9 |
| 61.6 |
38.4 |
1998 |
48.8 |
51.2 |
| 66.0 |
34.0 |
1999 |
50.4 |
49.6 |
| 76.0 |
33.0 |
2000 |
52.0 |
48.0 |
| 67.8 |
32.2 |
2001 |
53.6 |
46.4 |
| 68.7 |
31.3 |
2002 |
51.9 |
48.1 |
この表はなにかというと、日建連会員企業が、地方自治体から受注する割合が、構成比率(受注割合)において1999年から、逆転してしまっており、その結果として、1999年以降は民間依存率が高くなっている、というものです。
一見すると、90年から91年の二年間は、官公庁依存率が二割台であり、それに比べれば、99年以降の民間依存率の向上はまだまだ小さく思えるでしょうが、この表はあくまでも構成率の推移を表したものであり、昨今、全体としての工事量(需要)が少なくなっている中で、この数字の持つ意味は大きいのです。
つまり、1989年がバブル絶頂なのであり、1989年の末には、株価は史上最高値38,915円を記録しています。それじゃ90年からは下落の一途なのかといえばそうでもなく、上昇幅2,676円、上昇率13.24%の記録はバブル崩壊がはじまった1990年10
月に記録されていますから、91年ごろまでは、まだ民間も元気だったわけです。しかし、昨日の終値、日経平均株価は 8,227円だということです。
このように、この表は、その時々の時代背景が読めるところがあり、なかなかに興味深いものがあります。
例えば、1995年の官公庁依存率が高いのは、阪神神戸大震災のためだろうか、とか、1998年にも官公庁依存率が上がるのですが、これは戦後最大の景気対策(小渕さま)の成果だろうね、とかです。
それにしても日建連の会員といえば大手・中手さんです。今のような不景気状態(デフレ状態)では、地方自治体が、地場経済の活性化と雇用の確保にために、地場企業を視野にいれた仕事を出さざるをえないのは当たり前ですから、この時代、日建連会員企業の地方自治体からの受注比率は下がらざるをえないのです。
そして、必然的に民間依存率が高まることになるのですが、その民間工事も全体的な需要減少の中では、競争がさらに激しく、厳しい受注合戦を強いられます。その結果、各社の収益率は下がらざるをえないのですが、つまり、決算内容は悪くなる一方ですから、不良債権はスパイラル的に増えるわけです。
■株安直撃、大手行の株関連損失1.7倍の3兆円に
民間工事に比重をシフトせざるをえない、大手・中手ですが、その肝心の民間需要に元気がありません。
昨日発表された大手銀行の決算報告を見ても、この国の経済的な回復が、自助自立的なもので可能だとは考えられないはずです。
経済を人から切り離せば、市場に任せることで、いつかは、経済も回復する、という言い回しも通用するかもしれません。
しかし、大手であろうが、中小建設業であろうが、企業はモノではなく、ヒトです。
痛みは、結局はヒトにふりかかるものなのです。
問題を人から切り離さない経済政策というものが、すっかり姿を消してしまっているこの国は、政策に人の顔が見えない、なにかがヘンな国なのだと思います。
ということで、今日の私は、郡上建協さんのIT委員会に出席のために、郡上八幡町へ参ります。
では、ごきげんよう。
2003/05/26 (月) ▲ ▼
【法政大学エクステンション・カレッジ第二回】
以下、まにあ・1号さまによる、法政大学エクステンション・カレッジ第二回のまとめでございます。
・岐阜CALSセンター・丸田、新センター長
自治体としてのCALS/ECへの取り組み
・郡上、前田理事長:郡上建協IT化への取り組み
・栃木、八木沢さん:栃木建協IT化への取り組み
●新センター長は4月に着任したばかりという事でまだ、ご自身が勉強中との事。非常に柔和で明るいお人柄のようにお見受け。
●郡上・前田会長は「いつもと同じ話」謙遜されておられたが・・
話す側はそう感じていても、聞く方にとってはとんでもない。やはり、新たな発見と刺激をもらう。
- 団体・グループとしてのIT化にはある程度の成果、実績は出た。(協会としてのリテラシーアップ)
- そこで、次のステップとして今度は個々の企業、より小さい単位の団体・グループ(町村単位)での取り組みの強化(個々の企業としてのリテラシーアップ)
- IT化することの具体的なメリットの享受
というような、ロケットで言えば、2段目に点火したようなイメージ。
具体的にが各種アンケートを行い、個々の会員が「サポート」してほしい部分を明確化して、具体的なサポートを行おうとしている点。
また、各町村ごとにリテラシーを分析して、地区別での課題をも捕らえられようとしている点には本当に感心させられた。
さらには、ISO9000の合同取得第二段、または、14000の全体取得に向けた、「研修・勉強会」をIT/協会イントラをフル活用して行っている。
これはつまり「IT化」しているメリットをフルに使う、費用と時間を大幅に削減してる。ITのリテラシ向上フェーズから、ITを上手に利用、活用するフェーズに入ってしまっている、という点。
そして、とどめは前田理事長の一言
・情報発信の停止は「信頼性の停止」
・メールの停止は「企業イメージの失墜」
・サーバーの停止は協会理事長の責任
これには、一人のITベンダーの営業としてハンマーでアタマを殴られたような気分でした。(笑)
「いつもと同じ話ですまんかったねぇ」などと笑っておられましたがとんでもない、参りましたの気分でした。
●栃木・八木沢さんの事例紹介
約500社にも上る、巨大なイントラネット(私的にはすでに広域WANの世界に入っているとすら思える)だけに、運用がなかなかに大変で苦労している。
各支部単位での運用となり、他支部の細かい運用形態、状態までは補足しにくい。
しかしながら、以下のようにリテラシーレベルは確実に向上しつつある。
14年 6月 3 日以内読了率 58.1%
7月 〃 65.3%
8月 〃 71.6%
9月 〃 75.9%
15年 5月 〃 70.1%
おおむね、3日以内に7割以上の読了率を目標にするが、500社という巨大な単位でのこの数値はすごい。500の7割というと350社である。
350もの会社に3日以内に情報が行き渡ってしまう姿ってなにか想像できない凄まじいものがある。
各支部のうち、徐々にFAXでの連絡を廃止し、イントラでのデジタル連絡のみに切り替えている支部が多くなってきているとの事。
また各支部にITルームが設けられ、おおむね5〜6台のPCが講習・研修用に常設される環境が整いつつあるというのもなかなか素晴らしい。
現状で感じられる効果
・インターネットを利用する会員が非常に増えた
・他支部との交流、意見交換の場として機能してきている。
・協会組織、機能が少しづつOPENな雰囲気になってきた。
課題
・開設当初に比べ、コミュニケーション、情報発信の量が減少する傾向
これは、原因を追求中で課題である。
●そして、桃知さんの補足
CALS/ECの効果として
1.コストが下り、2.品質が上り、3.透明性が上り、4.業務効率上る
という事がよく言われている。しかし、喧伝されている割には「なぜ、これらの効果があるのか?」という根拠的説明・解説には全くお目にかかれない。
これを「解説する」と、性能既定発注方式に代表される「真正のマーケティンソリューションの世界」に行き着くのである。
これはこれで、決して悪い事ではない。(と私(桃知)は考えている)しかし、地場中小建設業はそうは行かない、真正マーケットソリューションの中でははっきり言って、みんな(受講者)全員ぶっ潰れの世界なのだから・・・・
なので事業者団体ベースの取り組みなのである。
発注者(自治体)と建設業協会が共同歩調で地域住民とコミットメントする。
真正マーケットソリューションの世界とは対極をなす、市民コミュニティの構築に向けた取り組み・・・・。
そのための、手段、ツールとしてのIT化があり、それを実践している郡上や栃木の取り組みなのである。
ということで、今日は見事な手抜きでございまして、私は、最初と最後にちょろちょろと書いてお仕舞でございます。では、ごきげんよう。
2003/05/25 (日) ▲ ▼
【今日は休みたい】
今日は休みたいのでございます。
身体がぼろぼろ、といっております。
昨晩も飲みすぎました。
午前中はずっと頭が痛とうございました。
さて、最近この戯言、文体を変えて書いていることにお気づきの方も多いかと思います。
ここのところずっと、である調で書いていました。
しかし、このであるで締める書き方というのは、なにかやっぱりしっくりこないのです。
私の場合、『桃論』を、です・ます調で書いてしまってから、です・ます調の方が書きやすくなってしまいまして、またこうして元に戻そうとしておるのです。
昨日の講座の内容等、本当はここでガンガンと書き込みたいのですが、今日はどうもだめでございます。
それではまた明日ということで、ごきげんよう。m(__)m
2003/05/24 (土) ▲ ▼
【五月病若しくは吸い取られた?】
5月が過ぎていってしまう。
今はなぜか脳みそが不調なのだ。
考えることが持続できないでいる。
五月病でもあるまいし、である。
■うどん星人さまよりのメール
明日は、法政大学ですね。
最近アドレナリン出していないかもしれない私は、大変興味あるところですね。
日々、未だに年度末の仕事や決算の仕事に追いまくられ脳みそもだらけております。
物忘れをすることが増えたとさる場所で話したところ、○○さんに「それは・・・自分の歳を忘れてはいないかぁ〜」といわれましたので「違う、自分の歳を忘れたいの!」と返しました。
参加される方々が羨ましいです。
皆さんが受け身ではない事が素晴らしいですね。
そうして、師匠から力一杯吸収してインプットして咀嚼してアウトプットされております。(師匠がお疲れになるはず!吸い取られているんですからね)
昨日、建協のISOグループ取得のお仲間でちょこっと集まって勉強会を開催して頂きました。
私が行き詰まってイントラ回覧でヘルプコールしたところ、皆さん集まってくださいました。
6社から社長さん3名、事務担当者3名でした。
社長さんグループはそれなりに悩みもおありと見ました。
事務担当者は、責任はあるが権限はないところに悩みが・・・
傍目八目ではないですが、自分では見えないところが皆さんからの指摘で良く解ってとっても幸せな気分でした。おみやげいっぱい貰った気分でした。
取得までの茨の道を歩いた同士で、お互いの痛みが分かり合えて結束感が強いのです。
この繋がりを作ったツールはイントラですね。
もちろん、建協においては(ざっくり)、商売のライバルでもある中での複雑な繋がりがありましょうが・・・そんな中、根底の部分で事務担当レベルがこうやって、お互いを磨きあっている。ってことに今日、お仲間から貰ったメールで改めて感激した次第です。
少なくとも、うわべだけの付き合いではないですから。
自分達の仕事次第で、ISOの認証がかかっている。私達は、真剣ですもの。
たまたま、昨日は少人数が集まりましたが、中にはメーリングリストを作って意見交換したり、回覧板も利用しております。
孤独で(?)苦痛でしかない作業が、「仲間がいる」これが支えになったりします。
少なくとも、建協のイントラがなかったら今の私たちの姿はないでしょうね。
だってそれまで、他の会社との繋がりは金銭絡みしかありませんでしたから。
イントラにより、細かい網が巡らされている感がします。
どんなシステムを生かすも殺すも使い方ですね。
いやぁ〜今日はしみじみイントラに感動しました。
こんな建協でお仕事できて、嬉しいですね。
会社の小さな枠だけで、モノを考えているだけじゃぁつまらない日々だったかもしれません。
と、今日の感激を師匠に伝えたかったです。
では、明日は吸い取られますから・・・気を付けて下さいませ。 |
そういうわけで、今日は法政大学エクステンション・カレッジの2回目である。
今日から新しいメンバーもおひとり増えるし、前回欠席の方二名のうち一名様の初出席もあるので、少し賑やかかなと思う。
今日は、事業者団体レベルでのIT化について(その1)が主題の講義である。
ゲストスピーカーは、岐阜県建設CALS/EC研修センターさまと、郡上建設業協会さま、それに今回の受講者である八木沢さんからは栃木建設業協会に関して。それぞれの立場でのIT化の取組みについての事例発表が予定されている。
当然私も事業者団体ベースのIT化に対する講義を1時間ほど予定している。
■「がらがら」につていのメール
【がらがら】
ピント外れで恐縮ですが、雑感まで。
15年前食品の開発コンサルタントをしていました。
(いわゆるマーケティング崩れです)
当時「規制緩和」じゃないですけど、
マーケティングが遅れていた業界が三つありまして、
「金融」、「運輸」、「農協/漁協」でありました。
要するに政府の保護業界な訳です。
当時記憶している事は、全日空(ANA)が初めて
国際便に進出したんですね。
その時のキャッチコピーが、
「世界品質のマーケティング」。
食品メーカーのマーケティング担当者は一様に
怒っておりました。
「品質などと軽々しく使うな」、
「品質に日本も世界も区別あるか」
「スッチーのパンスト代、キャプテンのハイヤー代、ふざけんな」
桃知先生の【ミーム】×【場の理論】、この辺から
一度○○なりに考えてみたいと思います。 |
このメールは面白いことを教えてくれていて、つまり、「政府の保護業界」・・・その意味でいうと、「公共工事という産業」も、「マーケティングが遅れていた業界」には違いないのだが、ここには「建設業」という名前さえ出てこない。
ということは、そもそもがマーケッティングの専門家からは無視された業界、つまりは商売として認められていない商売が「公共工事という産業」なのだ、ということだろう。
そして、この業界(「公共工事という産業」)も、何に目覚めたと言うわけでもなく、何かの脅迫にでもあったように、昨今一応に「品質」に向かっているのだが、それは「公共工事という産業」も、少しは商売(あきない若しくはビジネス)らしくなってきた、ということだろうか。(というようりも、公共建設市場の強烈なマーケット・メカニズム化がそうさせていると私は思うが)。
この○○さんが「桃知先生の【ミーム】×【場の理論】、この辺から一度○○なりに考えてみたいと思います。」と言われるように、『桃論』とは、じつは、「公共工事という産業」に対するマーケッティングのすすめ、のようなものなのかもしれない。
それは既に実践レベルにあるのであり、例えば、空知建協さんのIT化担当委員会は、「広報・IT化委員会」といって広報とIT化を区別しない委員会なのである。
しかし、他の業界のマーケッティング担当者は、このような建設業界の動きに対してに(ANAに対するように)怒ってくれるのだろうか?
多分、怒る以前に、そんな動きがあることも知らないはずなのだ。
つまり、無視されているのだよ。
「品質などと軽々しく使うな」、
「品質に日本も世界も区別あるか」
「おめかけさんのバック代、社長のゴルフ代、ふざけんな」
・・・という皮肉の一つも言われてみたい。(?)
2003/05/23 (金) ▲ ▼
【がらがら】
月曜日から出かけていたので、久しぶりの自宅での更新である。
昨日の帰り、千歳空港までは、まにあ・1号さんに送ってもらったのだが、その道すがら、私はしきりに「車が走っていないなぁ」ということを繰り返していた。
私には、普段より走っている車の数が少ないように感じたのだ。
そして新千歳空港。
予定よりも早く飛行場についたので、私は、予約より1本早いANA便に搭乗便を変更したのだが、この便の搭乗率は限りなく低かった。この時期、修学旅行の団体にバッティングしなければ、飛行機はガラガラなのだ。
かつて、規制緩和でAirDoができて、羽田−千歳間の運賃は瞬間風速的に下がりはした。
レッセ・フェールの方々の主張によれば、価格が下がれば需要は増えなくてはならない。
しかし、結局はどうだろうか。そうはならなかったのだ。
既に巨額の負債を抱えたAirDoはANAの経営傘下にあり、JASとJAL統合され、国内のメジャー航空企業は二社しかいなくなった。
そして、起きていることといえば、実質的な運賃の値上げなのだ(6月搭乗便からANAは特割の当日買いができなくなった)
そして、運賃ばかり高い(からっぽな)飛行機が空を飛ぶのだ(それは、私たちの主張では当然のことでしかない。レッセ・フェールの結末はこうなのだ)。
疲れていたので(というか習慣で・・・)羽田から自宅まではタクシーを使う。
木曜日というウィーク・ディの夕方にもかかわらず、上野までの高速道路は渋滞もなく快適そのものであった。
これには、プロ中のプロのドライバー(昨日は個人タクシーだった)も正直拍子抜けだったらしい。
「不景気で車も走らなくなってしまったようですねぇ」
「しかし、この不景気、いつまで我慢したらいいんでしょうか」
「まずは、9月には経済白痴の総裁さまを、変えなくてはならないでしょうねぇ」
と私は何気に答えたが、そういえば、そのお方は、米国に(褒めてもらいにか?)お出かけするらしく、政府専用機が二機羽田に停まっておりました。
羽田から、米国に飛べる人はそうはいないのだな、となぜかいまさらながらに感心したりして、30分かからずに自宅に着くも、その後どっと疲れが出て、なぜか「きらきらひかる」(郷田マモラ)の単行本を読みながら寝てしまった。
2003/05/22 (木) ▲ ▼
【怒涛の空知】
■怒涛の焼肉
昨日は、岩見沢での勉強会終了後、高速道路を深川へ移動。
約一時間で南大門というお店に到着。
ここは怒涛の焼肉屋である。
深川では地元の皆さま(深川界隈の空知建協広報・IT委員会の皆さま)のお世話になる。
本当にありがとうございました。m(__)m
さて、地元の皆様に聴くところによると、このお店、いちいちオーダーする必要はなく、黙って出てきたものを食え、というお店らしいのである。それで味はどうかといえば、これが怒涛なのである。
まず最初は名物といわれているタン塩である。
これは、さっとあぶり、細切りにしたネギを巻いて食べる。
昨今目立つ、ネギの細かく刻んだものをのせて焼くような、軟弱なものとは確実に一線を画す。
それで、これも独特なタレ(一見、醤油汁)にこれをつけて食うとまた格別にうまくなる。
このタレはじつに不思議なタレであり、そのまま味見をすると、本当に醤油汁のようなものなのだが、肉をつけるとまったく違うもののなる。まったく不思議なものである。
それから、サガリ。
これも塩コショウで下味がついているが、例の不思議なタレで食すれば、多分日本で一番うまいサガリとなる。
そしてレバ刺し。
これも独特であり、月見レバ刺し。
最初からタレがかけてあり(このタレの正体は不明・・・醤油系+ゴマ油?)、卵の黄身を混ぜて食べる。
東京には存在しないワイルドさというか、存在感がある。
箸休め?のピーマンの中に味噌の入ったものも、焼いて食せば、怒涛のビールのおつまみになる。
この他、ミノ、塩ホルモン、そしてロースと食べまくり、生ビール(これが最近の私の主食である・・・★\(^^;)も沢山いただき、プリン体を体中に充満させながら、その後二軒程はしごをして熱く語り、まにあ・1号さまの運転で、午後11時前に岩見沢のホテルへ戻った。
本当にお世話になりました。
そしてありがとうございました。
深川の街に立って思うのは、私がこの仕事をしていなかったら、私はここに来ることはなかったろう、ということである。それは深川に限らず、何処へいってもそう思うのだが、何かに引き寄せられるように(様々な偶然の結果として)、地に向かう不思議のようなものを、最近富に感じている。
そしてこういう偶然に感謝している。
これも人生なのだ。
■怒涛の床屋
そして、これも忘れないように書いておきたい。
私は、最近旅先で散髪することが多いのだが、昨日は午前9時にホテルの近くの床屋に行った。
そしてびっくりさせられたのである。
9時開店のこのお店、9時に行ったら、5席ある理髪席(というのか?)は既に埋まり、待ち人2名の状態であった。
私は10時からの仕事を控えていたので、時間がかかりますか?と尋ねたところ、10分ほどでご案内できますとのこと・・・。本当に10分程度の待ちで私の番になった。(つまり、恐ろしく回転は速い?)
が、私が散髪している間にも次々と客がくる・・・それも、じじいばっかり。
なんなんだ、この店は?である。
詳しくはまったく知らないので、後で調べてみたいと思う。
そしてさらに不思議なこと。散髪が終わるとなぜか握手をしなくてはならない・・・
なんなんだ・・・?
■怒涛の空知
空知建協のイントラネットのバージョンアップに伴う勉強会は4回を終えて、残すところは本日の午前中の1回となった。
空知建協のITリテラシィの高さは、この二日間で十分感じることができた。手ごたえ十分である。
このまま、何処がどう頑張ろうが、空知には届かない・・・という状況をつくっていこうと考えている。
そして、そのための秘策を今期は準備した。
後は動き出すだけである。
さて、今日の私は、午前中の勉強会終了後、午後3時30分のANA便で帰京の予定である。
2003/05/21 (水) ▲ ▼
【@岩見沢】
昨日から、空知建協さんの、協会イントラネットの模様替え(バージョン・アップ)に伴う勉強会のために、岩見沢へ来ております。
初日の午前中(つまり一番最初は、役員さま向けの勉強会だったのですが、これが素晴らしかった。
この1年間の取組みの結果が見事に繁栄されていたのである。
某MLで交わされていた会話から・・・
役員向GB2研修中です。
昨年4月のGB1.2の研修の時とは脅威的な進歩です。
素晴らしいの一言です。 |
本当に!
役員の方々のリテラシーの底上げはものすごいです。
迫力というか、凄みを感じてしまいます。(笑)
最初、ログインにてこずった時はどうなる事かと思いましたが
ログインが出来てしまえばあとはすんなり・・・ですね。
いや、素晴らしい! |
○○@岩見沢です。
体だるーい。
マスクしてませーん。
サポートほとんど必要なしです。ひまひま |
という具合なのであって、役員さまのリテラシィの向上は素晴らしい。
役員クラスでのリテラシィの高さは、郡上建協に勝るとも劣らず、というところだろう。
相補均衡をまざまざと見せ付けられた。
役員さまがこれだと、当然に会員さまのレベルも高く、午後から始まった会員さま向けの勉強会もスムーズなのである。素晴らしい!
ということで、今日も一日勉強会@岩見沢である。
2003/05/20 (火) ▲ ▼
【@ニセコ】
桃知@ニセコである。
H”は× FOMAは○
FOMAは意外なところで使える(特に北海道)のだが、意外なところで使えない。
しかし、FOMAを4ヶ月程使ってきたが、パケットの従量制というのは、やっぱり割高なのである。
あたりまえだが・・・
さて、なぜ私はニセコにいるのか。
つまりは、ある方々(例えばこの方)のご高配によって、昨日は尻別川でラフティングなるものを楽しませていただき、そのままニセコ東山プリンスに宿泊した、という次第である。ありがとうございます。m(__)m
それで今朝は、午前10時から岩見沢で仕事なので、午前6時30分にはホテルを出発しなくてはなならない。
午前5時30分に起床したのはいいけれども、なにか頭がいたい・・・多分二日酔いである。★\(^^;
ところで、昨日の発見なのだが、水平という言葉があるが、川は決して水平には流れてはいない、ということである。
そして、もう一つ、水温5度というのは、ものすごく冷たい、ということであって、尻別川はとても寒かった。
でも、ものすごく楽しかった。
だいたいだ、川の中から両岸を見るなんてことは、日本ライン下り(岐阜県)(笑)以来である。
とにかく静かな時間がなんともいえない(私は右耳の耳鳴りしか聞こえない、という状態であった)。
アウトドアはあんまり好きではない私が、また来たいな、と思ってしまったのだから、これは素晴らしいということなのである。
では、これから移動です。
2003/05/19 (月) ▲ ▼
【解釈の係数としてのミーム】
今日から北海道へ行きます。
ANA 055 東京(羽田)(0900) - 札幌(千歳)(1035)

『バカの壁』
養老孟司(著)

『場のマネジメント』
伊丹敬之(著)
NTT出版
1999年1月30日
|
■変化する情報としてのミーム
さて、最近のテーマである、人は変わる、情報は変わらない。これの出処は、養老孟司氏の『バカの壁』という本である。
この本は口述筆記のようなもので、書き下ろしのわけでもなく、切れ味は鈍い。
が、内容はそこそこ面白い、というようなものである。
さて、養老氏は情報は変わらない、という。
昨日の戯言にも書いたように、記録された情報は確かに変わらないのである。
通常は、この記録された変わらない情報を「情報」と呼ぶのだが、それはあくまでも静的なものである。
一方、我々は、まるで生き物のように変化する動的な情報(自己複製子=ミーム)を知っている。つまり、養老氏の話も少し物足りなく感じる(というか、養老氏に言わせれば私の解釈が未熟なのかも知れない)。。
ただ、5月15日に書いた、養老氏の提示した方程式は、とてもミーム的である。
Y=aX
(Y=出力 X=入力 a =脳の中で掛け合わせる係数)
この係数 a が、学習を重ねた結果変化するものだとすれば、この係数
a は、ミームだと考えてもよいだろう。つまり人間の解釈を左右する係数としてのミームである。
■解釈の係数としてのミーム
つまり、この係数 a を類似度を高くして共有している人間の場合、同じような入力Xに対して、出力Yは類似性を高くするということである。つまり、あるコミュニティにおける、個々の構成員の行動の同質性の問題である。
類似性(同質性)こそ、文化の遺伝子としてのミームの特徴である。
経営における問題は、会社(企業)という存在と、そのコミュニティにおける競争への適応課題である「差異性」が、このミームが創り出す同質性と、どう折り合いを付けるのか、という問題なのである。
なので、ここのところ、個性というものの本質的な部分を考えていたわけで、その現時点での、最もまともな経営論が、伊丹教授の『場のマネジメント』だと感じているわけだ。
それで、この『場のマネジメント』を、IT化を通して行うこと(企業編)のPPTを、法大セクステンションCの授業向けに作成中であるが、これがまた、全然私自身の解釈がこなれていなくて(つまり係数aが幼稚なわけだ)、かなり、なさけないのである。 |
2003/05/18 (日) ▲ ▼
【記録された情報は基本的には不変である】
■5月4日の疑問への解答
はじめまして。日記を拝見しました某落語ファンです(笑
突然のメール失礼します。
浅草名人伝説の談志師匠の落語は「代わり目」です。
「立川談志遺言大全集」5巻にあります。あの日が
談志初体験の若輩者でして、感激のあまり検索をかけたらそちらの
日記が出てきました。返信は必要ありません。では。 |
どこのどなたかはご存知あげませんが、ありがとうございます。m(__)m
■情報は変わらない
人は変化する、と昨日書いた。でも世の中、人は変わらない(自分はずっと自分じゃないか)、と思っている方が多いのも事実だ。じつは私もそう感じるときが多い。
しかし、よくよく考えてみれば、変わらないのは人ではなくて、情報そのものなのだ。
例えば、私はスカパーでよく古い日本映画を見るが、そこにいるのは若かりし頃の銀幕スターである。
中には死んでしまった人もいるし、今となっては想像もできないぐらい若い方々が沢山いる。
これはどういうことかというと、記録された情報(映画)は、年々たっても情報の内容は変わらないということだ。
まあ、フイルムが劣化するとか、古い記憶媒体では、そういうアナログな変化はあるだろうが、最近のDVDとかになるとこれもほとんどない。
つまり、記録された情報は変わらない。
しかし、我々はあたかも生き物のような情報の存在を知っている。
それが「ミーム」である。
ということで、今日はここまで・・・って、なにかと忙しいのだよ。
2003/05/17 (土) ▲ ▼
【人は変わる】
浅草は、昨日から三社祭が始まっていて、何かと賑やかなのである。
昨晩は宵の宮が出、今朝は子供神輿が出て、午後からは町内引き回し。
本番は明日、しかし雨かもしれない。でも、下町のお祭りは天候には左右されないとのことらしい。
■人は変わる
スーさんFe業界・2号さまより。
(ざっくり)
最近知ったことに非マルコフ過程というものがあり(物理学では過去に起きたことが一回ごとにご破算にされ、過去が未来に関わらない過程をマルコフ過程、
過去の履歴が未来にすべて関わる過程を非マルコフ過程というそうです。
単純に考えると一般的な物理現象は 基本的にマルコフ過程。人間の脳や歴史に関わる現象は非マルコフ過程と捉えられる。)浅い理解ながら因果応報的な現象も物理学的アプローチを通過するとこうゆう風に体系付けられ、解析できるのは非常に面白いと感じました。そして、弊社の思考の道具、経営の道具として活用できたらと思っています。
最後に桃知理論も非常に学際的(ごった煮?)に展開しており毎回非常に楽しみです。
IT、政治・経済はもちろん社会生物学、社会心理学や認知科学・認識論的アプローチは個人的にも大好きでワクワクいたします。
だから私は桃知さんを追いかるのだと思います。
(ざっくり) |
マルコフ過程というのは、数学の集合関係の概念だと記憶しているが、最近どころか、生まれてこの方、こんなものは使ったことがないので、私はよくわかりません。ただ、将来は(確率的には)現在の状況にのみ依存し、現在よりも前の状況には依存していない、ってやつではなかったかと思うのだが、最近の私の思考ともなにか関係があるような感じではある。
さて、人は変化する、ということだが、これは生物学的には当然であって、私たちは常に死に向かって変化しているのであって、人間としての私は、まず生物学的には不変ではない。
今日の私は昨日の私ではないのだ。
その上、生物学的にある程度変化が落ちている状態の脳みそを想定したところで、5年前の私と明日の私は明らかに違う。例えば、5年前のの私は単純な市場原理信奉者だったけれども、今は市場原理は大嫌いである。
それどころか、一月前の私は一日100本を自負していた強烈な愛煙家であったのに、いまじゃ強烈な禁煙運動家(?)である。
これは、つまり、私が変わったというよりも、5月15日に書いた方程式 Y=aX(Y=出力
X=入力 a=脳の中で掛け合わせる係数)の係数aが学習を重ねた結果変化したということである。
つまり、肉体的にも脳みそ的にも人は変わる。
で変わらないもの、それが情報なのである。
ということで、今日は時間がない。
あとは後日。
2003/05/16 (金) ▲ ▼
【シンプルに嬉しい】
午前4時47分のタイムスタンプを付けたメールが届いた。
なによりも嬉しい・・・感謝。
【感動しています】
はじめまして
札幌の○○と申します。
『桃論』よませていただきました。
実は会社の社長に貸してもらって読んだのですが
途中でAmazonにて注文しました。自分の本として読めるのが楽しみです。
HPも拝見させていただきましたが
とても勉強になりました。
桃知先生は講演などでもご活躍のようですが
今度、札幌に来る予定などございましたら
ぜひ、メール等でおしらせください。
必ず行きます。 |
【『桃論』 IT(インターネットの精神文化)に向かって人間を解放する】
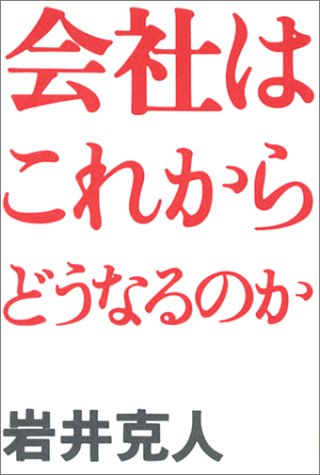
『会社はこれからどうなるのか』
岩井克人(著)
平凡社
2003年2月23日 |
■「個性的な企業文化」は論理矛盾か
『会社はこれからどうなるのか』は、東京大学経済学部長の岩井克人教授が語るポスト工業社会論である。
今という時代をポスト工業社会(岩井氏の言葉では「ポスト産業資本主義」)と位置づけ、そこでは(まあ資本主義ではいつもそうなのだが)利潤の根源は差異性なのだとし、その上で、会社という組織を論じているのは、じつは『桃論』と同じスタンスというかアプローチなのである(岩井先生は迷惑だろうが)。
なので、岩井教授も(私同様)、企業文化としてのコア・コンピタンスを語るのである。曰く、
『(コア・コンピタンスとは)、より正確には、たえず変化していく環境のなかで、生産現場の生産技術や開発部門の製品開発能力や経営陣の経営手腕を集結しいて、市場を驚かす差異性をもった製品を効率的かつ迅速的に作り続けていくことのできる、組織全体の能力と定義しなおしたほうが適当でしょう。それは、特許や製法秘密やブランド名や顧客リストといった、すでにモノの形をした知的資産というよりは、まさにそのような知的資産を生み出していくことのできる組織に固有の人的資産の総体です。それは静態的ではなく、動態的な概念なのです。』(岩井、p258−259)
そして、その結果としてこうなる。
『・・・そして、そのようなプロセスのなかで、企業の中核をなすアイディアやタレントは、創業者個人の頭脳や肉体を離れ、経営者や技術者によって構成される組織全体の知識や能力に転化していくことになります。多少トートロジカルに言えば、企業組織とは、それに参加する経営者の企画力や技術者の開発力や労働者のノウハウといった、組織特殊的な人的資産のネットワークにほかならないのです。』
『ところで、企業のなかで、このような組織特殊的な人的投資が積極的になされればなされるほど、その収益性が高まっていきます。だが、それと同時に、そのような組織特殊的な人的投資によって編み上げられていく「企業組織」は、「文化(CULTURE)」としか言いようのない個性をもつようになります。』(岩井、296-297)
つまり、「個性的な企業文化」こそがコア・コンピタンスである、という論理矛盾(?)に(私と同様に)行き着くのである。
月刊『現代』の6月号で、上野千鶴子氏が、この岩井教授の本の書評を書いているが、そので行われている「個性的な企業文化」ということばへの論理矛盾への指摘こそが、私がここ数日書いている、「個性」を考えることの始まりなのである。
上野教授こういうのだ。、
『「組織特殊的な人的資産」を確保するための戦略として、「企業文化」ということばがでてきたときには、ちょっと待てよ、という気分になった。「個性的な企業文化」とは論理矛盾だ。個人であれ、集団であれ、「文化」は「遺伝子」が伝えるもの。遺伝子は自分をコピーして生き延びるものだから、「個性的な企業文化」は、他に対して「個性的」であっても、会社のなかでは同じ遺伝子を量産することで、「個性」をあっというまに失ってしまうんではないだろうか?』
これはミーム論であり、この指摘はある意味正しいが、ある意味違っている(というかつまらない)と思う。(私もこの罠にはまった)
昨日行き着いた視点、つまり、個性とは、それを認める文化の存在を前提としている、ということ。つまり、個性を個性として認める文化があってこそ個性は個性なのだ、という視点に私は立ちたい。
これは長期的視点では誤っているかもしれない。
しかし、今の私には個性とはそのようなものとしか思えないのだ。
例えば極端な例かもしれないが、自分のウンコで壁に絵を書くのも個性だろうが、それが将来的にどのような芸術的価値を持つかは現時点では不明である。それどころか、通常的にそのような行為を行っていれば、それは個性的ではなく、精神病院行きなのである。
つまり、「個性的な企業文化」というのは、(従業員・構成員)個々の差異(タレント・キャラクタ)を認めることのできる企業文化ということになるだろう。
そこで必要とされる個性は、企業文化というフィルターにかけられるので、当然に「なんでもあり」ではない(ウンコで絵を描く人間はいくら個性的でもいらない)、ということだ。
この感覚は、伊丹敬之教授が「場のマネジメント」でいう「半自律的人間」観のようなものだと感じているが、この「なんでもあり」度によって、それぞれの企業文化の個性の程度というのも違ってくるように思う。
つまり単純な一次方程式で書けば、Y(企業文化)=aX(個性)の変数aが、「何でもあり」度という形で表現できようか。
この変数aはフィルターであり、その値が0の時には、個性は認められないということである。
つまりその組織文化は、軍隊みたいなものか原理主義のようなもじゃないかと考えられるのであって、この場合には「個性的な企業文化」は論理矛盾、というよりも最初から存在しえない。
一方、(認められる個性を)限りなく「なんでもあり」に近づけようとすれば(a=∞)、この場合にも、「個性的な企業文化」は論理矛盾となるどころか、「文化」自体の存在が怪しくなってくる。
つまり、組織としての企業は存在せずに、個々の人間が、砂浜の砂粒のように存在しながら、勝手に活動するようなイメージを想像していただきたい。(これが新古典主義経済学の想定する人間なのだが・・・)
つまり、企業文化という時に、a=0とa=∞の両極端はありえない。
∴そのことで、「個性的な企業文化」はありえる、と私は考えているのだ。
しかし、岩井論文には確かに弱点がある。それは、その企業文化が、従来の日本企業の文化のままでよいように思われるところである。
だから上野教授の以下のような指摘がでてくる。
『でもそこでイメージされている「会社員」はあいかわらずの長期勤続を前提にしたオヤジ社員。この本読んだオヤジが「このまんまでいいんだ」と安心するもとにならなきゃいいんだけれど、とよけいな心配までしてしまう。』(上野、p306)
これは、岩井教授が、ポスト工業社会論を語りながら、その社会的な基盤である精神文化の考察を(わざと?)していないためだと感じている。
(手前味噌)
『桃論』(私)はそこに、インターネットの精神文化を持ってくる。そして、ポスト工業社会=インターネット社会との理解を強調しながら、コミュニティ・ソリューションの考え方を展開するのだが、ここには、IT革命とは精神文化的な革命だ、という私の強い思い入れがある。(笑)
このIT革命=精神文化革命論はミーム論である。
つまり、ポスト工業社会における企業文化の根源とは、インターネットの精神文化なのだ、と主張しているのだが、これがつまり、個性を認めることのできる企業文化なのであり、「個性的な企業文化」の基盤なのだ。
そして、この企業文化は、従来の工業社会で棲息する「あいかわらずの長期勤続を前提にしたオヤジ社員」を想定してはいないのであり、たぶん彼等がなんの変化もなく棲息はできないだろう。(さらりと書いたが、この人間が変化する、という概念は相当に深い。明日時間があれば、これについて書こう)
岩井論文でのIT革命は、グローバル化と金融革命と共に、「ポスト産業資本主義」化に伴う現象との扱いでしかない。そこにインターネットの持つ精神文化がなにものであるのかを語ることもない。
ここで岩井の言う、コア・コンピタンスとしての企業文化は閉塞するのである。
岩井教授と上野教授という東大の先生の議論と、『桃論』を同列に並べるのは身の程知らずであることは重々承知で語れば、この東大の先生方と『桃論』のアイディアには、ほとんど違いはない。
ただ違いがあるとすれば、それは、インターネット、そしてインターネットが支配する社会に対する思い入れ違いなのである。
それは大学の先生と、実際にインターネットの世界で生きている人間との差なのだと感じているのだ。 |
▼
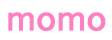
■桃知商店謹製■
(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2003.All
rights reserved.
About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言 | 2003年5月前半へ| 2003年6月前半へ|著作権|店主へメール
![]()
一昨日の郡上のこと(どこで何を食べたのか)も記録しておかなくてはならない、と考え続けてはいたのですが、なにぶん最近はお酒の席でのことは見事に忘れているわけで、つまり色々な部分を持った脳みそ細胞が破壊され欠落しているわけで、今回の食べ物の白眉は、「豚平焼き」というものなのですが、これを出していた店は・・・???思い出せないでおりました。

![]()