

店主戯言0030801 2003/08/01~2003/08/15 "There
goes talkin' MOMO"
About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言 | 2003年7月後半へ | 2003年8月後半へ|著作権|店主へメール
2003/08/15 (金) ▲ ▼
【今日も雨】
今日も雨。
肌寒いという表現を通り越してはっきり言って寒い。
昨日は、仏滅と八方塞と13日の金曜日が一緒に来たような日で、なにもかもうまく行かない日だった。
己の技量でそうなるのであれば諦めも肝心だが、そうでないからストレスもまた溜まるのだ。
■お嬢・2号のホムペ
お嬢・2号からメールが届いていた。
おお、偉いぞ。
私も御不浄には一言ある。
それは、パブリックには肛門を自動的に洗ってくれる便器は今や必需だ、ということである。
それが私の持(痔)病の問題からの願いであることは言うまでもないが、浅田次郎も、今や日本が世界に誇れるものは肛門を自動的に洗ってくれる便器だ、言っているぐらいなのだから、日本は、肛門を自動的に洗ってくれる便器で世界制覇をもくろむべきなのだ。
しかし、まずは国内からなのである。
あせってはいけない。
まだ確認してはいないが、一説には、「はやて」のグリーン車はそうらしいし、鹿児島空港の便器には、ほとんど洗浄器が付いている。
私はホテルを自分で選ぶときには、洗浄器付きトイレであることが第一要件となっている。
ちなみに私が一番好きな御不浄は、自宅のものである。
落ち着く・・・。
■リベラリズムという価値観(その3)
ということで、今日は休み明けの準備をしながら、未読が山となっている日刊建設通信新聞に目を通していた。
そしたら、長野県の田中知事が、公共工事の前払金を廃止する方針だ、という記事が目に止まった(8月11日付)。
成る程なぁ、と思う。
要するに、彼(田中知事)は、(長野県の)公共工事を、市場参入者にとって魅力の無い市場にしたいのだ。
市場になんらかの魅力(産業創出力)があれば、そこには参入者がいる。
しかし、市場自体に魅力(産業創出力)が少なくなれば、参入者は自然と減る。
つまり、魅力とは利潤(儲け)である。
それは適正であるか不適正なのかを問わない(そもそも利潤に適正・不適正などあるのだろうか)。
例えば、前払金の廃止は、前渡金狙いでダンピング入札をするような、不良不適格業者を激減させる効果があることは言うまでもないだろう。
このシステムでの公共工事市場は、基礎体力無き者は存在できないだろう。
これはレッセ・フェールでもなく、市場原理でもなく、ミーム論的な手法なのである。
村上泰亮はミームをもって産業形成を論じていたが、その裏返しの手法なであり(反古典の政治経済学概論)、人為的な産業政策に過ぎない。
彼(田中知事)の政策は、公共工事という市場の魅力(産業創出力)を極力小さくしようという方向に向かう。
それにブレはないようだ。彼の手法は、公共工事の産業創出力(若しくは、産業をまとめる力:ミーム力)を弱体化に向けられている。
そしてそのことによって、「公共工事という産業」が扶養する人間を減らそううとする。
つまり、公共事業の削減をねらう政策となりえる。
しかし、何度も書くが、地方自治体が本来持つべき公共事業の目的とは、第一義的に、地域に密着した社会資本の整備を通した地場経済の活性化と雇用の確保にあり、地方自治体が抱える「公共事業の問題」とは、地方財政の体力的な限界と雇用対策の必要性とのトレードオフの関係にある。
公共工事という産業を、縮小化し、規制をかけ(彼等は規制緩和というが)、魅力の少ないものとすることは簡単なのである。
問題は、公共工事を通して社会的な活動に参加していた多くの県民の生活をいかにに守る(若しくは新たなプロセスにシフトさせる)のか、ということになる。
ここに彼(田中知事)は、レッセ・フェール的思考しか準備できていない。
若しくは、「一人一人の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保される」というリベラリズムの価値観が存在していない。
私は7月の松本講演で「建設産業構造改革支援プログラム」に触れてこう言ったはずだ。
このプログラムには、生活者として建設産業に従事されている一人一人の県民に対する視点がない。
ここに長野県の問題が存在する。
そしてA木さまより。
道庁もついに財政立て直し推進本部(本部長・高橋はるみ知事)を設置し、公共事業の削減策を打ち出しました。
8月8日の初会合で明らかになった「財政立て直しプラン」の数値目標は2005―07年度(集中対策期間)に公共事業を20%削減、道単独投資事業費を40%削減する、という内容です。
長野県の公共事業40%削減、単独事業費50%削減―に比べると、まだ救われますが、先の知事選で本道建設業界が高橋知事を支援しただけに、今後大きな反発も予想されます。
ただ、桃知さんが言われるように…。
地方自治体が本来持つべき公共事業の目的とは、第一義的に、地域に密着した社会資本の整備を通した地場経済の活性化と雇用の確保にあり、地方自治体が抱える「公共事業の問題」とは、地方財政の体力的な限界と雇用対策の必要性とのトレードオフの関係にある。
…だと思います。
破綻寸前の道財政を立て直すためには、歳出カットはやむ得ない措置だと思いますが、きちんとした議論が行われないまま、手の付けやすい公共事業費が狙い撃ちにされる危険性もあります。
地方財政の体力的な限界と雇用対策の必要性…まさに全国の都道府県が直面する問題であり、地場の中小建設業者にとっては時間との戦いです。 |
「公共工事という産業」を利用した、この国の高度産業化と国民総大衆消費者化は、開発主義という政策を用い、戦後40年かけ、極めて政策的につくられてきたものである。
その政策的な限界が、今という時代の閉塞の根源にあることには異論はない。
であれば、問題は、それをどうやって次の時代に移行させるのか、という政策的な手法の問題なのである。
私は、ここに市場原理を持ち込むことには反対する立場であることはご存知のとおりである。
なぜなら、そこにはリベラリズムの価値観が無いからだ。
すなわち、一人一人の人間的尊厳と魂の自立が守られず、市民の基本的権利が最大限に確保されないからである。
必要なことは、まずは、次の時代(例えば金子郁容のいう「インターネット社会」)を理解することから始めなくてはなるまい。
そして、その時代に、「公共工事という産業」が(そしてそこからはじき出された方々が)、どうやって時代に適応していくのかを考える政策があってしかるべきだ、と考えている。
それは、半ば強制的に、「公共工事という産業」(そしてそこからはじき出された方々)が、林業や農業にシフト(従事)せよ、というような押し付けの政策ではない。
どうやって生きるかは、一人一人の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保されながら、自分自身が選べば良いのである。
そこに、私のいうインターネットの精神文化に人を解放する必要性があり、IT化の必要性が存在するのである。
2003/08/14 (木) ▲ ▼
【2000トンの雨】
見えるものは 指の間を
つたって落ちる 雨
道の向こう そびえ立つタワー
もうすぐ空へ 届くだろう
僕の想い何ひとつ
伝える術もないのに
心少し洗われたなら
救われる時 あるのだろうか
今は耳を澄ますだけ
炎と雨の響き
僕の想い何ひとつ
伝える術もないのに
2000トンの雨が降れば
僕は今日も一人
(山下達郎 2000トンの雨)
今朝はこの歌から始めた。
この曲に感情移入ができるとすれば、それは、今朝は朝から生憎の雨が降っていることと、私の目の前には、道の向こう そびえ立つタワーがある(つまり、花やしきのスペースショット)ってことだろうか。
でも、この「2000トンの雨」という歌だが、私は、孤独な青年の放火の歌だと解釈している。
つまり、2000トンの雨とは、消火のための放水である。
そびえ立つタワーというのは、火災によって巻き上がった炎と煙のタワーである。
燃え盛る炎と煙は、もうすぐ空へ届くのである。
僕の想い何ひとつ伝える術もない、孤独な青年が、自分の放火した現場の消火作業を見ている。
放水する水しぶきを浴びるとき、ふと、この水で心が少し洗われたら、放火犯としての自分が救われるのだろうか、と思う。
でも今は、ただ耳を澄ませて(何人だとばれないように)、炎と雨(消火の放水)の音を聞いているのである。
しかし、結局は、己の孤独はそのままなのだ。
だから、僕は今日も一人。なのである。
ということで、今日は雨である。
でも今日は、関与先のサーバー引越し作業をする予定日なので、雨の日というのは、ある意味、仕事には最適な状況なのかもしれない。
2003/08/13 (水) ▲ ▼
【おやすみ】
おやすみ、と書いて終わる13日。
45歳♂。
2003/08/12 (火) ▲ ▼
【今日は熊本県人吉市日帰り】
伊藤さんから、暑中見舞いが届いていて、こう書いてあった。
桃知さん、残暑お見舞い申し上げます。
店主戯言、私にとっては、いつも、琴線にふれることばかりです。何でですかね。
答えの一つは、8月7日の桃知さんが戯言に書かれた姿勢ではないかと思いました。
>少なくても私は藁ではない。
>だから私はこう言うしかないのだ。
>私には答えはない。一緒に考えるだけである。
しかし、一つだけ、私と違うことがありました<(_
_)>。
私は、吉田を応援していたのです。それは5年間柔道をやっていて柔道はたいしたことないと思っていたのを、吉田が見直させてくれたからです。
私もプロレスが好きです。しかし、田村というレスラーは知りません。打撃系のプロレスラーは好きじゃあありません。
これが吉村道明Vs吉田なら、確実にプロレスを応援したと思います。(笑)
|
私もガキの頃、少しだけ柔道をやっていて、帯の色は一応黒である。
それだけに、身体的感覚で柔道(特に組む、投げる、締める)は強い、と思っている。
そして柔道の吉田は強い、さらに金メダリストであり有名人でもある。
一方、Uの直系である田村は、全国区では、無名なプロレスラーである。
ふつう、全国区で田村といえば、それは「やわらちゃん」なのである。
田村は全国的には無名なプロレスラーであり、社長なのである。
つまり、今回の有名人吉田と戦うという、注目を浴びる試合で勝つことは、ビジネスとしては非常においしいのである。
しかし、負けたときのリスクも非常に大きい。
そういうリスクの高い勝負をしてくる田村が私は好きなのである。
すなわちプロレス的なのである。
しかし、故、吉村道明氏の名前は私の琴線に触れた。
くるっと回転えび固めである。
子供の頃、私のプロレスにはいつも吉村道明がいた。
ただ、吉村道明は、じつは柔道の人なのであるなぁ。
ということで、今日は熊建人吉支部のIT化委員会会議に出席。
もちろん(?)日帰りである。
2003/08/11 (月) ▲ ▼
【リベラリズムという価値観(その2)】
■昨日のPRIDE
昨日はペーパービューでPRIDEを見た。
リングサイドが2000円だと思えば安いものだろう。
しかしだ、私の贔屓の田村は吉田にあえなく負けてしまった。
私には、プロレスが柔道に負けた、と思えた。
力道山に木村が負けたリベンジを、なにも、いまごろ埼玉でやらなくてもいいじゃねえか、と、そう思った。
私(45歳♂)は、プロレスが好きである。プロレスの味方なのである。
しかし、正直、吉田は強いと思った。
■リベラリズムという価値観(その2)
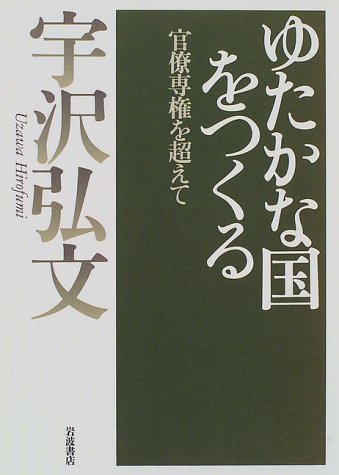
『ゆたかな国をつくる―官僚専権を越えて』
宇沢弘文(著)
岩波書店
1999年3月5日

『ヴェブレン』
宇沢弘文(著)
岩波書店
2000年11月28日
|
私はいつも、己の思うこととはいったい全体なんなのだろうか(世の中のどのような位置にあるのか)、を確かめたい、という衝動にかられている。
そのための方法の一つが、(私が過去に学びきれなかった)政治・経済学を学ぼうとする行動につながっている。
そんな私の、現在の興味の対象であり、己の基本姿勢となっているのが、制度主義派の経済学である。これは進化論的経済学とも呼ばれているものなのだが、その始まりはソースティン・ヴェブレンということになっている。
アーロン・ゴードンはこう言っている。(『ゆたかな国をつくる―官僚専権を越えて』,p12)
「すべての経済行動は、その経済主体が置かれている制度的諸条件によって規定される。と同時に、どのような経済行動がとられるかによって制度的諸条件もまた変化する。この、制度と経済行動の間に存在する相互関係は、進化のプロセスである。環境の変化にともなって人々の行動が変化し、行動の変化はまた、制度的諸条件の変化を誘発することになり、経済学に対する進化論的アプローチが必要になってくる。」(『現在経済学における制度的要素』1963年)
宇沢弘文によれは、ヴェブレンは、制度のもつ経済的意味を解明し、経済的諸活動によって制度自体がどのように進化するかを分析した最初の経済学者である。そしてその基本姿勢はリベラリズムにある。
私の言っているIT化とは、この相互作用の過程でしかない。
そしてここが肝要なのだが、ヴェブレンがリベラリズムというとき、それはデューイ(ジョン・デューイ:哲学者)と同じように、一人一人の人間的尊重と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保されるという視点に立って、経済制度にかんする進化論的分析を展開することを意味している。
私は、IT化になにか特別な意味を持たせようとしているのではない。
私の手法は、IT化に対して進化論的にアプローチすることで(例えばミームがその象徴としてある)、制度と行動の間に存在する相互関係、つまりIT化における進化のプロセスを分析しようと試みているだけなのである。
ゆに問題は、その時に私の立つ価値観となる。
自然科学よりも、社会科学は、分析者が立つ価値観によって見えるもが異なる。
見えるものが異なれば自ずと結論も違ってくる。
つまり、私は常に、どのよな価値観に己が立っているのかを自分自身に問う。
それが、「一人一人の人間的尊重と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保されるという視点」でなくてはならない、と今の私は考えているということである。
つまり、それがリベラリズムという価値観である。 |
■お嬢・2号さまより
本日は、大阪もめちゃ快晴で布団がふかふかになり、ありがたい天気でした。
でも、暑いのは苦手です。
「鍵山秀三郎語録」という本を読みました。
ほんとは鍵山さんの著作物を探したんですが、あいにく店頭になく「語録」というのがあったので、それから読もうと思いまして。
鍵山さんは「イエローハット」の相談役で「全国掃除に学ぶ会」の会長だそうです。
なんで、私が興味を持ったかというと「トイレに関する本」が好きで、その中に「鍵山さん」がでてきたので「いもづる式」で本を読む私は、鍵山さんの著作物を読みたくなったのでした。
で、語録の中に「絶対差」というのがありました。
以下抜粋です。
●物事や世の中を相対主義で見ていますと「どこよりも、誰よりもいくら多かった」「去年に比べてどれだけ伸びたか」など、いつも相手と比べる世界に身を置き、相対差でしか物事を見てないわけです。
●相対主義とは相手と比べる世界のことで、つねに相対差の追求で一喜一憂の世界です。「去年に比べてどれだけ伸びたか」「他社に比べていくら多かったか」というように、売り上げの数字のみに囚われる世界です。
そしてこの相対主義は「終わりよければすべてよし」という結果主義に陥ってしまうのです。
●その比べる世界の相対差に対して、絶対に比べられない世界を、私は絶対差と申しています。比べるのもがない人生、比べるものがない会社、勝ったり負けたりの世界ではなく争わなくていい世界のことです。人間でいえば人格、会社でいえば社風というものです。
私には、まだ勉強不足で、読み解くことがなかなかむつかしいのですが、ひとつ思ったことは、「終わりよければすべてよし」という結果主義について、ふと、そうなっていることがよくあるのかな、(自分自身)と感じました。
というのも、結果がよくてもたぶん、その道程をさぼっていたとすれば、その結果は持続していない気がします。
なんかほんまに、もっと腰をすえて「勉強」せねば、私はただの「にぎやかし」で終わってしまう気がしました。
うぉー、長くなりました。すいません。
読み流ししてくださいね。なんか「にぎやかし」で終わらないように「書きたかった」のかもしれませんね(笑)
ほな、股です☆ |
書くことは、非常に大切な人間の営みだと私は思う。
だから、沢山書け!と言い続けている。
その繰り返しの中からでしか分からないもが、少なからず世の中にはあるからだ。
それは例えば、他人の書いた文章を読む能力である。
分かっていないのに分かっているふりをしている者の書いた文章など、その底の浅さはあっという間に見破れるようになる。
それはどんなに語彙豊かに飾ろうともである。
そしてそれは逆に己に対しても言えるのだ。
書くことによって、己の未熟さに唖然とすることもまた多いのである。
お嬢・2号さまは正直な方だと思う。
ということで、今日はお客様がお見えになるので自宅待機である。
2003/08/10 (日) ▲ ▼
【台風一過】
■台風一過
午前7時30分に目覚める。
昨日は、面談の日ということで、昼から飲んでいた。★\(^^;
ヒューマンモーメントの楽しさを満喫させていただいた。
遠くから、そして雨風強く足下の悪い中、岐阜、熊本、北海道からの来店を深く感謝なのである。
またやろう。
さて、皆さんのところでは、台風の影響はいかがであったろうか。
今日の浅草は台風一過の暑い日になりそうなのである。
雨も嫌いだが暑いのも嫌いなのだ。
我侭なのである。
■リベラリズムという価値観(その?)
(その2)を書こうと思ったのだが、今日は久しぶりの休みだし、それに暑いし、そんなことよりも、今日は「PRIDE」があるしね(田村、吉田を殺してくれ!)、気力が失せるには必要十分な条件が揃いまくっている日なのだ。
それで書くのを止めようか、と思ったのだけれども、それじゃいつもの悪癖を越えられないじゃないか、と内なる己がつぶやく。
それに対して、そんなもの超える必要があるのか、という自問が返っている。
しかし、必要なのか必要じゃないのか、を考えることが必要なのじゃない。
必要なのは、「一人一人の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保される」ってことは、どういうことなのかを考えることだ。
それは、魂の自立の必要性なのである。Soulである。
Seoulではない、それは韓国の首都だ。
君の魂は自立しているか!
Soul of Soul と言えば、これは、「ゲロッパ!」(J・B)だろう。
髪の毛を短くしていたころ、私は何度か、あの井筒和幸監督に似ていると、タクシードライバーから言われた。
けっして嬉しくはなかったのだが、これも何かの縁である。
「ゲロッパ!」はDVDが出てから買ってみようと思う。
私は映画は大好きなのだが、最近、映画館が嫌いなのである。
なぜか、というと、私のお尻の病気は映画館で発病したのである。
ということで、結論である。
今日は書かない。 では、股。(by
お嬢・2号)
2003/08/09 (土) ▲ ▼
【リベラリズムという価値観(その1)】
■日付が変わって目覚めた
自宅に戻った安心感か、それとも岩手県四連戦で疲れ果てたのか、夕食後ソファーに埋もれるように眠ってしまった。
一眠りして目覚めたら既に日付が変わっていた。
今は午前1時を過ぎたところだが、若干風は強く感じられるものの、浅草は、まだ台風の影響は受けていないようだ。
今は、丁度、愛知・岐阜・三重が台風の影響を受け始めたところのようだ。
郡上建協のイントラネットには、八幡工事事務所の河川砂防課長から、台風に対する警戒準備のお願いが回覧されていた。
台風は勢力を落としていないようなので、十分な警戒が必要だろう。
さて、東京もこれから雨が降るのだろうが、中止になった暑気払いに併せて、既に東京に着ておられる方々もいらっしゃる。
なので、今日は一日、面談の日とすることにした。
■リベラリズムという価値観
懐かしい方からメールが届いていた。
ご活躍のようでなによりである。
(ざっくり)
ところで私のCALSセミナーも150回を越えまして、現在では、地域の専門工事業様にまで頼まれて実施しています。
そのときに思うのですが、いまだに業者様が官公庁が何とかしてくれる、何か言ってくるとの「官公庁依存病」的な依頼体質に驚きます。
また、官公庁も「ほったらかし」ですよね。地元の業者様が倒れたら、雇用、税収地域の活性化全ていいことはないと思うのですが、徳島ではご存知と思いますが大手上位2社が会社更生法適用を申請しました。
でも上を下への大騒ぎではないようです(表面上)
きつい世の中です。お体ご自愛くださいませ。
HP読んでますと桃知さん一人の体ではなくなって来ましたね。 |
受注者側は、いまだにヒエラルキー・ソリューションを信じている。
発注者側は、レッセ・フェールに逃げ込んでいる。
こうして「公共工事という産業」の思考は停止してしまっている(旧来の手法を繰り替えそうとして失敗してしまっている)のだ。
これを生み出しているのはリベラリズムという価値観の彷徨なのだろう。
柔軟な思考を生むのは、それを容認する価値観、という環境でしかない。
資本主義の考え方は、すべての希少資源を私有化して、分権的市場経済制度のもとで、資源配分と所得配分を決める、という制度を想定している。
これに対して、社会主義の考え方は、すべての希少資源を公有化して、政府が中央集権的な経済計画を策定して、、資源配分と所得配分を決める、という制度を想定している。
資本主義の考え方も社会主義の考え方も、一人一人の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保される、という、リベラリズムの要請を満たしてはいないのだ。
資本主義も、社会主義も、一つの国あるいは社会の持っている歴史的条件を無視し、その文化的、社会的背景を切り捨て、自然環境に敬意を払わないことは同じなのだ。
これに対してリベラリズム(を基礎に持つ制度主義派の経済学)は、一つの国あるいは社会の持っている歴史的、文化的、社会的、自然的条件に配慮し、現実の経済的制度を策定しようとする。(以上、宇沢弘文)
と、ようやくリベラリズムという価値観について書き始める気になったのだが、今日はここまでだ。
続きは後で(って書いてちゃんと書いたためしがないのも確かだ ★\(^^;)。
2003/08/08 (金) ▲ ▼
【暑気払いは中止】
明日(8月9日)に予定されていた暑気払いを中止とした。
これはは台風10号の影響のためである。
それは台風でビアガーデンが開かない、というのではなく、今回の参加者は、全国各地の建設業の方が多く、今回の台風の通過により、巡回パトロール、緊急事態に対する対応準備等を優先しなくてはならないからだ。
まあ、残念ではあるが、こんなときこそ、地場の建設業の存在意義を確認してもらうチャンスでもあるわけだから、当然そちらが優先となる。
次の機会にお目にかかれることを楽しみにておこう。
ということで、私は帰りの「やまびこ」の車中である。
【台風】
台風がやってきていて、明日の暑気払い、どうものんびりやっているところではないようだ。
午前中に結論(中止するか)をださなくてはならないだろう。
まだ盛岡でした。
2003/08/07 (木) ▲ ▼
【岩手巡業中】
■岩手巡業中
まもなく一お連カウンターが550,000になる。
うまく当った方は、店主へメールをくだされ。何か景品(たぶんポロシャツ)をお送りしたいと思う。
さて、昨日は、予定よりも早く宮古に着いたので、浄土ヶ浜に連れて行っていただいた。
今年は平年よりも3度ほど水温が低いとかの話で、泳いでいる方もおられたが、なにか寒そうであった。
駐車場からは徒歩の移動をしたのだけれども、私は帰りの階段の登りで体力を使い果たしてしまった。
腿が上がらないし、汗っかきの私は体中から汗が吹き出た。そして息も切れ切れ・・・。
そんな状態で、宮古、岩泉支部さま向けのスタートアップセミナーを開始したのだが、これ(講演)用には、私には別エンジンがあるのだ。講演は、どんなに体調が悪くとも、モチベーションさえ落ちていなければ、補助エンジンに点火できる。
というわけで、昨日のセミナーも、上々の反応をいただいた。当初目的はきちんと達成できたと思う。
宮古、岩泉支部の皆様には今後ともご支援宜しくお願いします。(って選挙運動みたいだ)
本日は、午前中は、IT特別委員会、午後からスタートアップセミナーin盛岡支部である。
■苦しい境遇に押し込められた建設業界のひとたちを食い物にしているいかがわしい人
桃論を読んで、目から鱗が落ちるほどのものを私は感じました。
私が探していたものがやっと見つかったと。
あなたはもしかすると、苦しい境遇に押し込められた建設業界のひとたちを食い物にしているいかがわしい人なのかもしれない。
疑えばキリのない話です。読後の私にしてみれば、業界のこと、奇麗事では済まされない世間のことをあまり知らない私にしたら、正しいとはいえない判断なのかも知れないが、今の私からしたら、伝わるのです。何が正しいのか。間違っているのは世間なのかしれません。そのように間違った世間に私は今暮らしていることを享受しなければならないと感じたりもするのです。
桃知さんのおっしゃることは、キツイ。だからこそ現実味があります。
相互理解、相互作用こそ現代において失われつつあることだとも思ったりもします。あらゆる社会問題がそこに行き着くのではないかとも私は思うわけです。「コミュニケーション不足」それが人に不信感を与えているのでしょう。個人主義にあらゆる技術が向かっているのかもしれません。家庭において各部屋にテレビがあって、同居する家族の一人一人が携帯電話を持って、自分の世界にはいってしまうのが現代の姿なのかもしれません。
そのようなものの捕らえ方ができてしまうのであれば、いっそう大事なのが人と人との信頼感なのだと思うのです。この信頼感が、不信感が問題になっているのだと私は考えてしまうのです。
私たちが建設業界において、なそうとしているのは、信頼回復なのでしょうね。松本のときに談合にたいしてソーシャルキャピタルがもてるのであれば、それは肯定されるものと話していただきました。
それを聞いた私は、これから登らなくてはならない山の高さ、険しさを実感したのでした。
例えとして、挙げたいのがプロレスのヤオとジーコジャパンへのベンゲルの評価なのです。
前者は談合で、後者は信用です。
プロレスは人に感動を伝えてくれるものであるのなら、勝者が事前に決まっていても、その感動を与えるという作業はまちがいとは言えないのではないかとおもうのです。しかしながら、今現在のプロレスはとても厳しい境遇のようです。人は夢を信じないし、親は子供に平気でサンタクロースはいないと話す味気ない世の中のようです。
ジーコシ゛ャパンへのベンゲルの評価とは、今は戦績が悪くても、ジーコなら強い日本代表をつくるだろうと判断して、それを信じようということなのです。そのときにアーセン・ベンゲルは真顔でいったそうです
「人生において、信じるというのは大事なことだ」と。
追い込まれた一営業マンの繰言です。
私は信じたいのです。
それだけをあなたに伝えたかった。
ただそれだけのことです。 |
「苦しい境遇に押し込められた建設業界のひとたちを食い物にしているいかがわしい人」か、まあ、いいだろう。
一介のIT屋である私が、そのような評価を受けるとすれば、これは凄いことだろう。
しかし、言っておくが、私は、皆さんが「苦しくない環境」の頃から(むしろそうだからこそ)、ソーシャル・キャピタルを目的としたIT化の必要性を言っているのであり、「苦しい境遇に押し込められた建設業界」では、それは限りなく手遅れだ、と言っているに過ぎない。
そうならないために、自分で(若しくは一緒に)考えよう、そして考え方の基本は、あくまでもIT化に向かう、と言う、ぎりぎりの線が『桃論』のなのある。
なぜ、ぎりぎり、なのか。
現実の「公共工事という産業」の悲しいまでの思考停止状態を垣間見れば、それは、長野の田中知事でなくとも、(私でさえ)己の中のガラポン願望(市場原理主義者的悪意)が目を覚ましかねないからだ。
その感情を、ぎりぎりに抑えながら、私は思考しようとする。
その抑制は、私自身の思考停止への恐れなのだ。
私は、どうしたら、この短い人生に、己が己に納得しながら過ごすことができるのだろうか、と思考する。
私の場合、それは、ミクロ的な(ストイックな)己の心に向かう作業(ウツの原因)と同時に、マクロ的な、己を取り巻く環境を考える作業となる。
つまり、 「私は私と私の環境である。そして、もしこの環境を救わないなら、私も救えない」(オルテガ・イ・ガセット)なのである。
「公共工事という産業」を考えることは、私にとって、すなわち「私の環境」を考えることなのだ。
そして、同じ悩みを持つ友を探そうとする。(デジタルとリアルなコミュニケーションを通したコミットメント)
そして一緒に考えようとする。
つまり、私は「苦しい境遇に押し込められた建設業界」に対する処方箋(答え)を提示しているものではない。
溺れるものは藁をもつかむ、というが、少なくても私は藁ではない。
私も藁にすがりたい溺れるものなのである。
だから私はこう言うしかないのだ。
私には答えはない。一緒に考えるだけである。
そして必要なことは議論であり、答えに従うことではない、と。
答えはあると言い出した途端に、私は巷にあふれる(似非)市場原理主義者か、新古典主義者か、構造改革論者と同じ者となってしまうだろう。
これらは、思考の可能性をあきらめた甘い誘惑なのだ。
(市場原理主義者的悪意)
少なくとも、私は、己の思考のぎりぎりのところで、その誘惑と対等する方法を、『桃論』を書くことで己の中に刻み込んだだけなのだ。
2003/08/06 (水) ▲ ▼
【Thanks! 久慈・二戸の皆さん。(盛岡が混んでいるわけ)】
盛岡のみるきいです。暑気払いには主人のみ参加で私はお留守番なので悲しいです(;_;)
さて、盛岡は8/1から3日までさんさ踊りというお祭りがありました。また青森ねぶたが1日から7日まで 仙台七夕が6日から8日まで(今日5日は前夜祭の花火あり)、秋田竿燈が3日から6日までetc・・・と今、東北は祭りシーズンです。
たいていその祭りだけでなく、その他の場所の観光や「東北三大祭りツアー」などという形で旅行会社はツアーをくみますので、盛岡だけでなく今この時期の東北はかなり宿が混んでいるはずです。 |
どうやらそうらしいのである。(Tnakns! みるきいさん)
昨日の「はやて」も大混雑で、グリーン車は取れず、ようやく禁煙の指定席(通路側)を確保した。
その「はやて」に、上野駅、大宮駅で乗り込んできたのは、ご指摘どおり「東北三大祭りツアー」の方々なのだった。
当然に、いわゆる現役をリタイアした方々の悠々自適の生活の一環である。
おじさんの私からみても、おじさんとおばさん(つまり60歳オーバー)の方々が大勢乗り込んできた(この国の個人消費の多くは、このような現役をリタイアした方々の悠々自適の生活に依存していることを実感させられた)。
そのおかげで、通常のビジネス仕様とは違い、なんとも緊張感のない車両に私は置かれてしまい、普段なら一眠りするところなのだが、前も後も横も、皆さんよくしゃべってくれるものだから、熟睡できずに眠りが浅いまま盛岡到着。
多くの皆さんはここで下車され、車両はようやく静かになったのだが、二戸までは30分もかからず到着。
二戸駅で、同じ新幹線でこられた向井田IT特別委員長と合流。そして、車でこられた下河原副委員長とも合流。
昨日の二戸は、梅雨明けを思わせる晴天であり、暑く湿気も高い(まあ、鹿児島に比べれば空気の比重は10分の1ぐらいにしか感じないけれども)、その暑い二戸で、最初のスタートアップセミナーを暑苦しく行った。
たぶん、出席率は高かったはずである。つまり、予想以上に沢山の方々においでいただき、なぜ、岩手建協がIT化に取組むのか、を話させていただいた。
昨日参加された、一人でも多くの方に、今回の取組み主旨に賛同いただき、各々がIT推進者になっていただければ幸甚なのである。
今日は、陸路片道2時間30分かけて、宮古市へ向かう。
2003/08/05 (火) ▲ ▼
【岩手県巡業(前半)】
■岩手県巡業(前半)
今日は、岩手建協久慈支部さんと二戸支部さんとの合同セミナーのために、上野
8:02 はやて 3号 二戸 10:48で二戸に向かう。
二戸は、私が訪れたところでは、本州最北端になる。
二戸といえば金田一温泉と座敷わらしだろうが、残念ながら、今回回の出張期間中の宿は、ずっと盛岡の同じビジネスホテルであって、温泉でのんびりする、というわけにもいかない。
それにしても、盛岡市内のホテルは大変混んでいて、今回の宿もようやく予約が取れた。
なにかあるのだろうか>盛岡
明日(6日)は、宮古市へ自動車で往復移動し、宮古支部さんと岩泉支部さんの合同セミナー。
7日は盛岡にてIT特別委員会を午前中に行い、午後から盛岡支部さんのセミナーを行う。
8日は、午前中に花巻市にて、花巻支部さんと北上支部さんの合同セミナーを行う。
これははっきり言って体力勝負なのである。
私は沢山のサプリメントを摂りながら、東北の盛夏を乗り切ろうとしているのだが、はたして・・・。
■8月9日の暑気払い
岩手から帰れば、8月9日(土)はささやかな暑気払いを執り行う。
気の置けない方々と、今年の中間報告と、これからの予定を、まったりと語らう予定である。
この戯言に出てくる方々も、大勢いらしゃる。
人員的には、まだ若干の余裕があるので、飲むというよりは語らう暑気払い、時間があれば是非に足をお運びいただきたい。
■本日の講演概要(抜粋:時にはこういう内容もいいだろう)
地方自治体が本来持つべき公共事業の目的とは、第一義的に、地域に密着した社会資本の整備を通した地場経済の活性化と雇用の確保にあり、地方自治体が抱える「公共事業の問題」とは、地方財政の体力的な限界と雇用対策の必要性とのトレードオフの関係にある。
しかし、地方財政の体力的な限界を背景とした「市場原理」への偏重傾向は、各地で、本来の公共事業の目的を無視した入札・契約制度を生みだしている。この事は公共事業の地域満足度を低下させ、それが「公共事業不用論」に結びつく悪循環を招いている、と言えるだろう。
地方自治体による「市場原理」への無防備な信奉は、公共建設市場では「条件付一般競争入札制度」のような、「市場原理」を前面に打ち出したとされる入札制度を採用することに顕著となる。例えば、長野県や宮城県、横須賀市における入札制度にその例を見ることができる。これらは「市場原理」が機能することで、コストの削減と透明性の確保ができる、ということを、そのルールの正当性の根拠としている。
つまり、この制度は、二つの問題を同時に解決できると考えられている。それは、第一には、地方自治体の財政難からの公共事業原資縮減への対応であり、第二には、「公共事業という産業」に内在する不正行為、つまり、官製談合やしゅうあい斡旋のような行為の排除とその撲滅である。しかし、その真意は、発注者としての地方自治体が、市民社会からの公共事業批判に対し、「市場原理」を標榜することで、自己保身的に対応しているに過ぎないのではないだろうか。
ゆえに、発注者の恣意性を極力排除するような形で「市場原理」を前面に打ち出しているこれらの制度も、結局は価格のみをそのメトリックとすることで、経営力と技術力による「公共事業における本当の競争」の必要性を二次的にしか扱わないものとなる。つまり、受注者側の経営努力を積極的に評価しようとする姿勢に欠ける。
既に、地場型中小建設業においては、相当の資本カ・技術力の蓄積があるが、これらの制度は、その蓄積(経営と技術)を「市場原理」で無造作に捨て去るようなものでしかなく、多くの地場型中小建設業は、経営意欲を失うことになるだけだろう。
なぜなら、このような価格偏重の仕組みが支配する市場では、企業が、いかに「技術と経営に優れた建設企業」になろうと経営に取り組んだところで、その努力(投資)が、受注のためのなんの根拠にもなれはしないからだ。
つまり、「条件付一般競争入札制度」という問題解決方法は、個々の中小建設業の経営努力を認める仕組みを内在していない。「技術と経営に優れた建設企業」となろうとする経営努力が「市場原理」を標榜している入札制度の下で、直接受注に結び付く事例を私は知らない。「市場原理」を標榜する公共建設市場は、努力することの質が変わらざるを得ないだろう。それは、終わりのないコストダウンへの努力であり、そこに人材という資産はない。
例えば、「条件付一般競争入札制度」を導入しているある市では、最低制限価格が設けられている工事の平均落札率は、限りなく85%に近い。この落札率の平準化は、予定価格の85%という最低制限価格が設けられているためであり、当然のことでしかない。
この制度では、設計価格があらかじめ公表されており、最低制限価格は改札日当日にくじで決定される算出率によって決まる。であれば、入札者は、積算もせずに最低制限価格を予想するだけである。つまり、この制度では、落札できるのは運まかせであり、入札は最低制限価格を予想するギャンブルと化す。
これは、この事例に限った現象ではなく、設計価格の事前公表+最低制限価格の「条件付一般競争入札制度」においては共通する傾向と言える。このことは、このような「条件付一般競争入札制度」が、実は「指値方式」あることを物語っている。最低制限価格を下げれば、落札率も当然に下がる。
さらに、このような入札制度では、一般競争を強調する余り、受注者の技術的、経営的資質を事前に問うことが少なく、施工能力のない不良不適格業者が受注してしまい、品質の低下や、一括下請け(丸投げ)の問題が起きる。
それでは、最低請願価格を排除すれば良いだろう、という意見もあろうが、実質的に最低制限価格を設けていなと同然の、長野県のような、安く調達できることだけを目標とする入札制度では、結果的に極端なダンピング入札が横行し、品質低下の問題や、不公正な労働条件の助長を生み出す、という問題がある。
公共建設市場で「市場原理」によるコストダウンが可能であるのは、受注者の創意工夫が可能である、という前提が必要なのだ(発注者のモノを買うという視点)。市場原理を言う方々の多くは、これを理解しようともしない。
落札の決定指標として価格だけが重視されるのであれば、人件費が大半を占めるような労働集約型の公共事業(地場型中小建設業がターゲットとする公共工事とはほとんどがこれである)では、最低賃金違反の金額で落札されるケースの増加や、品質の低下という懸念を生み出す。つまり価格偏重の入札が公共事業の不公正な労働条件を助長したり、品質低下の要因になるという問題を生み出す。
また、従業員の働く場所と言うだけではなく、社会人としての自己実現の場でもあった地場の建設業の急激な衰退は、従業員のやりがいや生活満足度を奪い取ってしまう結果をまねくだろう。これは、地域社会のための公共事業としては、本末転倒と言わざるを得ない。
先にも指摘した通り、地方自治体が抱える「公共事業の問題」とは、地方財政の体力的な限界と雇用対策の必要性とのトレードオフの関係にある。それは、地方自治体が本来持つべき公共事業の目的が、第一義的に地域に密着した社会資本の整備を通した地場経済の活性化と雇用の確保であるからである。
「公共事業の問題」を短絡的な「市場原理」の導入によって解決しようとする試みは、多大なリスクを伴う社会的な実証実験に過ぎない。「市場原理」を公共事業に持ち込むことは、経済学に於いても、確立された絶対的な手法ではないのである。
以下延々と続くのだが、前後を書いていないので、市場原理が好きなヒトから見れば、私はただの改革反対勢力にしか思えないだろう。しかし反論は『桃論』を読んでからにしてほしい。短絡的な反論を相手にしている暇はない。勉強してから出てきてほしい。
ということで、こんなはなしを、真っ当に(原稿を読むように)やってしまったら、全員爆睡ものである。
だから私は、これを河原乞食芸として喋るのだ。
芸を磨け>喋る者たち
2003/08/04 (月) ▲ ▼
【奄美のおもひで】
 |
前日はここで郷土料理を楽しみ
花火もみた。 |
 |
そして翌日はここから・・・
この後、車止めに引っかかり、私はおもいきりこけた。
自慢のボルサリーノも、奄美では、がきの麦藁帽子の如し。 |
 |
この船に乗り |
 |
こんなことや |
 |
こんなことをして遊んだ・・・
素晴らしい現実逃避の日だった・・・ |
【寝るしかない】
昨晩から書き物をしていて、今は午前4時。
ついでだから今日の戯言の更新もしてしまおう。
■8月26日桃熊会
まずは、オープンセミナーのご案内に、8月26日の桃熊会の予定を掲載したのでお知らせである。
第一部(13:00~14:30)
大月一浩氏(SGSジャパン㈱教育訓練部コースマネージャーISO9000審査員)
演題「価値あるISOの導入」と「合同認証取得の方法」
第二部(14:40~16:00)
平井道則氏(岐阜県・(社)郡上建設業協会理事)
演題「協会IT化とISOのグループ取得」
第三部(16:10~17:00)
桃知利男氏(桃知商店店主)、田中祐治氏((社)熊本県建設業協会人吉支部IT委員会)
演題「(社)熊本建協人吉支部におけるIT化の取組み」
今回の出しものは以上の三本立てである。
いつもよりはかなり実践的な内容であるので、刺激を受けるにはもってこいだろう。
ただ、これを真似をすればできる、というものではないことも事実ではあるが・・・。
詳しくは、2003年8月26日熊本公徳会カルチャーセンター(桃熊会)を参照されたい。
■明日から岩手連戦
明日からは、岩手建協さんのIT化のためのスタートアップセミナーの第一陣で、岩手県内を駆け回る。
今回は、二戸、宮古、盛岡、花巻にお邪魔する。
予報では、私の訪問中、岩手県内はあまり良い天候は望めないようだが、そんな中、うっとうしいかもしれないが、私は哲学を語りたいと思う。
なぜ、IT化の取組みが今必要なのか、を徹底的に語りたいと思う。
そうして、聴いていただく方の記憶の片隅にでも、私のミームを残したい。
こう書くと、なにやら厳しいはなしのように思われるかもしれないが、私の哲学は、所詮は河原乞食の芸でしかない。
つまり、哲学をおもしろおかしく、やがてしんみりとくるように語ろうとするだけなのだ。
私ができることはそれだけでしかない。
(だから私は芸を磨くのだ)
つまり、事業者団体によるIT化は、私一人の力でなんとかなるようなものではない。
そこには、愚直なまでの、推進者のボランティア精神が必要なのである。
幸いにして、岩手建協のIT特別委員会の方々には、生まれながらにボランティア精神が備わっているようで、今回も大いにお世話になる、というよりならざるを得ない。
この方々なしには、なにもできないのである。
と、ここまで書いてきたが、めまいがしそうなぐらいの睡魔に襲われている。
こうなれば寝るしかない。
とにかく、寝よう。
ということで、午前中は音信不通である。
2003/08/03 (日) ▲ ▼
【休み】
今日は休みである。
仕事として休みである。
お嬢・2号のおとしごである。
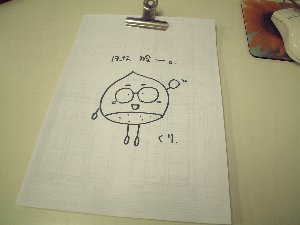
ほな、股。
2003/08/02 (土) ▲ ▼
【奄美はいい】
桃知@名瀬%奄美大島のホテルでエアコンを止め汗を噴出している。
昨晩は、寝不足のため、不覚にも2次会で退散。そのままホテルでエアコンをつけっぱなしにして寝てしまったものだから、水ぶくれ状態。
身体がたっぷんたっぷんしている。
それにしても、奄美は暑い、そしてういまい。
昨日のお昼は、鶏飯(けいはん)を食べる。これは想像を絶したものだったので、後日詳しく書きたい。
夜は、喜多八というお店で、奄美の家庭で食べているような料理を食べたのだけれども、なんといっても、豚足と最後に出てきた「マダ汁(アオリイカの墨汁)」は絶品なのである。
このマダ汁と一緒に出てきたおにぎりは、おにぎりとはいうものの、その姿は小型のオムライスなのだ。
が、それを食べると、カツオ風味のおにぎり、さらには刺身を酢味噌で食べるにいたっては、既に食物トラップ状態なのであった。
ということで、今日はせっかくなので、ちょこと奄美を楽しんで、最終の飛行機で帰る。
では、股。(by お嬢・2号)
2003/08/01 (金) ▲ ▼
【宮崎独演会の一部内容変更のお知らせ】
一応日付は変わったが、今はまだ、昨日の続きの夜中である。
仕事量がとても多くて、予定しただけ仕事を終えることができないでいる。
昨年の執筆モードとは違い、今年の実践モードは、移動とF2Fが多いので、どうしても事務的な仕事が疎かになる。
仕事量と(移動距離+飲酒量)は、完全にトレードオフの関係にあり、私はその蟻地獄の中でもがくでぶな蟻のようなものである。
さて、今日は奄美大島で講演が予定されいるので、JAS
599 便 羽田 09:05 発 → 奄美大島 11:15 着という、東京からの直行便を使う。
このところ遠距離はやたらJALSを使うことが多く、ANAに乗るペースが減ってきている。
まあ、どちらにせよ、私はマイルが溜まれば嬉しいのだけれども、やっぱりANAのプラチナサービスを狙っている身としては、奄美大島にANAが飛んでいないのは、ちょっと悔しい。
それにしても、このところ航空運賃はやたらと高い。
今日の奄美便は、通常運賃だけの設定でWeb割りもなにもない。
最もよく使っている新千歳便なんか、ぼったくりじゃないのか、と思うぐらい高くなった。
規制緩和とかなんとかいっているわりには、結局はこうして大手の寡占状態になってしまうのが、レッセ・フェールの常なのだ。
■宮崎独演会の一部内容変更のお知らせ
さて、宮崎独演会の内容が一部変更となったのでお知らせを。
まず、後援に宮崎県がついて下さった。素晴らしい!
そのため、私の講演の前に、宮崎県技術検査課さんから「宮崎県CALS/EC
について」と題したはなしが追加された。
その他、後援には、(社)宮崎県建設業協会、(社)日本青年会議所建設業部会宮崎ブロック建設クラブ、(社)宮崎県建築士会宮崎支部青年部、宮崎県電気工事業組合青年部、宮崎県畳工業組合さんがついていただいた。素晴らしい!
それから懇親会会場も「ホテル神田橋」と決まった。
真夏の九州シリーズ最後のセミナー。
賑やかにいきたいもので、是非多くの方々に参加していただければ幸甚である。
新しいチラシをここに掲示する。
→  03082702.pdf (pdfファイル)
03082702.pdf (pdfファイル)
■熊本独演会のチラシ
さて、宮崎独演会の前日、8月26日に予定されている熊本独演会の予定が決まり、チラシが届いている。
先にも書いたとおり、事務的仕事は現在大渋滞中で、その内容を皆さんにお伝えする時間がない。
仕方が無いので、取り急ぎここにチラシを掲示する。
→  030826.pdf (pdfファイル)
030826.pdf (pdfファイル)
これも楽しそうである。
Thanks!>桃熊会。
▼
About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言 | 2003年7月後半へ | 2003年8月後半へ|著作権|店主へメール
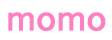
■桃知商店謹製■
(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2003.All
rights reserved.
![]()
03082702.pdf (pdfファイル)
030826.pdf (pdfファイル)
![]()