| ���̐ؔԂ�888888�� |
 |

�X��Y��041102 �@2004/11/16 �`2004/11/30�@"There
goes talkin' MOMO"
�C���f�b�N�X �bSelf Talking INDEX| �����̋Y�� | 2004�N11���O���� | 2004�N12���O�����b���쌠�b�X��փ��[��
�b�������ޒʐM�bAbout���m���j�b�_�E�����[�h�b�ˑ������N�b�X��o���b
2004/11/30 (��) �@�� ��
�y���ӎ��̒m���ցz
6���N���B
�͂�����B�킽���͓�����B
�܂��́A����̃T�C�{�E�Y�E�g�[�N���C�u�Ŏg�p����PPT���_�E�����[�h�̃y�[�W�ɒu���܂����̂ŁA�K�v�ȕ��͂��g�����������B
���āA�uIT���͈��ނ��Ƃ��v�́A����A���q����̌��t�Ƃ��āA���g�ł͂�������蒅���A���H�������Ă���B�i�j
����́A����Ō��Ƃ��ɗN���オ��A�C���X�s���[�V�����̂悤�Ȃ��̂��A�킽����IT���͕K�v�Ƃ��Ă���A�Ƃ������ƂŁA��ӂ�����Ȃɒx���܂łł͂Ȃ���������ǁA�͓؉��Ǝ��i���ŔM������Ă����킯���B
����Ō��Ƃ��ɏo�Ă��錾�t�́A���ӎ�����N���o�Ă�����̂�����(�Ƃ������ӎ��̊֗^�����Ȃ��j�B
����́A�u�������Ă���Ƃ��ɂ�������̂����A�����������t��I��Œ����Ă��Ȃ��̂��ˁB
���t�Ƃ������̂́A�ӎ��I�Ȃ��̂�����ǂ��A�����ɂ͊ԈႢ�Ȃ����ӎ�����p���Ă���B
�g�̂Ŋo�������̂���p���Ă���B
����͘b�����t�ɂ����Ă�苭����p���Ă���B
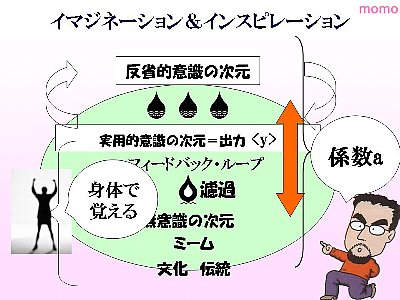
�����������Ƃ��ɂ́A����͋t�]����B
�ӎ������ӎ������߂悤�Ƃ��Ă���悤�Ɋ�����B
���Ȃ̎����������B
���̈ӎ��Ɩ��ӎ��̊W���A�킽���͏�̐}�̂悤�ɍl���Ă���B
�ӎ��Ƃ́A���p�I�ӎ��̎����Ɣ��ȓI�ӎ��̎����Ƃ̃t�B�[�h�o�b�N�E���[�v�ł���B
�A�C�f�B�A���N���o�Ă���Ƃ��A�C���X�s���[�V����������Ă���Ƃ��A����͖��ӎ��̎������傫�������Ă���B
�ӎ��Ƃ��Ă̌��t�ɖ��ӎ����傫����p���Ă���Ƃ��A���̌��t�ɂ͍����h��B
�M���Ƃ��A�����Ƃ��A���i�Ƃ��A����Ȋ�������ӎ��̎�������N���o�Ă���B
��~�A��A�~��B
�R���s���[�^��IT���c�[���ł����Ȃ��A�����ɖ��ӎ��i�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���j�͏h��Ȃ��B
�Ɠ��l�ɁA���{�̗��_�i�����j�́A���ӎ��i�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���j���h�����Ƃ������Ȃ��B
�������A�n��ɍ����������ƂƂ����d���́A�����̌��������œ����Ă�����̂ł͂Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�n��͌����̌����i���{�̗��_�j�����Ő�������Ă�����̂ł͂Ȃ����炾�B
�����ɂ́A���܂��܂Ȗ��ӎ��i�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���j���h���Ă���B
�~�[�����^�Ԋ����ƐM�����R�~���j�e�B�E�\�����[�V�����̔閧�ł���i���q��e�j�̂͊m�����낤�B
����������́A�����̌����Ɍ`����̑��^��g�ݍ��A�{�����e�B�A��NPO��NGO������������̂ł��Ȃ����낤�B
�K�v�Ȃ��͖̂��ӎ��̒m���B
����͏������^�Ƃ����悤�Ȃ��̂Ȃ̂�������Ȃ����A�u���̉x�y�v�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B
����́A���̎�����ɁA�g�̐��������Đ��ݍ���ł���B
�l�i�B
��������B
�킽�����A�uIT���͈��ނ��Ƃ��v�Ō�����Ƃ��Ă���̂́A���́A���ӎ��̒m�Ȃ̂��낤�A�Ƃ����m�M�����悤�ɂȂ����B
�����Ă���͂܂��A���t�̐��E�֕\�o���邱�ƂŁA����̎v����`���A�l���邱�Ƃ���߂����Ă͂���Ȃ��B
�܂�A����Ƃ��Ă̌��t�́A�ӎ��Ɩ��ӎ��̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă���B
2004/11/29 (��) �@�� ��
�y�����͌��j����!!�z
�ߑO5��20���N���B
�́A�܂��^���ÁB
�y�j���ɂ́A�����͋��j�����A�Ǝv������ł��āA�Ȃ��[���̏��Ȃ������Ȃ��A�ƐS�z���Ă�����A�j���Ƃ��������t�̊��o���������Ă��܂��Ă���悤�ŁA��ӂ܂ŁA�����̓I�t���Ƃ���v���Ă����B
�������A����͂Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�ł����āA�C�����A�������T�C�{�E�Y���[�U�[���ōu���̎d�������邶��Ȃ����B
�ߑO11��20������50���Ԃ̍u���Ȃ̂˂��A�Ƃ��������Ƃ���ŁA�ǂ����悤���Ȃ��̂ŁA�{���́A������ł���u�T�C�{�E�Y�̔��������H�ו��v��������Ɩ��߂����Ă����������B
�킽���͌|�l�����́B
�܂����Ă����āA�Ǝ����Ɍ����������āB
���āA��ɂ��m�点���Ă���悤�ɁA12���͎D�y�ƌF�{�œƉ�����������Ă���B
��12�07�D�y�Ɖ���@�w�N�w�̂���IT���x�\�l�b�g���[�N�ƐM���ƃr�W�l�X�Ɓ\
�@12��7���i�j 13:00�`�@���ł�27�ɂ�
��12�14�F�{�Ɖ���Y�N���@�w�N�w�̂���IT���x
�@12��14���i�j 13:30 �`�@�F�{�s�Y�ƕ�����فE6F
�����o���C���ɂ�
�u�N�w�̂���IT���v�ȂǂƂ����Ă݂Ă��A�킽���̂���Ă���IT���́A�܂����t��n�߂��q���̂悤�Ȃ��̂��낤�B
�C���^�[�l�b�g��ɂ�����Ȃ�āA�l�Ԃ̑Ώې��̐��E�́A�ق�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��̂��Ǝv�����A��~�[���ł��邪�䂦�ɁA���t�Ō�肫��Ȃ����̂̂��ǂ������������Ă���̂��������i���t�͂킽���̊O�ɂ���j�B
���������A�������́A�����͂Ȃꂽ���Ȃ��ƁA�܂��݂ʂ��Ȃ��ƁA���t�������ĂȂ��邵�����@������Ȃ��B
�����āA���t���g���Đl�ƂȂ��낤�Ƃ���Ƃ��A����ɂ͌��t���g���čl���悤�Ƃ���Ƃ��A���̈��̌��t�̂��}�e���A���i�����j�ɁA����������A����J�������Ă���B
���̎����Ƃ́A���t�ł͌������Ȃ��q�b�Ȃ̂��A�Ζ،���Y�����]�Ɖ��z�Ō���Ă���u�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���v�Ȃ̂��낤�B
���ꂪ���Ԃ�u���ӎ��v�Ȃ̂��B
����͐l�Ԃ��R�~���j�P�[�V�������n�߂��Ƃ�����ݐϐi�����Ă���u�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���v�Ȃ̂��낤�B
�w�u���v�u���Ȃ��v�u�N�v�u�r�v�u���v�u���������v�u���̂����v�u�N�v�u�����Ă���v�u�������v�c�c�B�x
�w���̂悤�ȁA��������ӂꂽ���t�̈����A���̓s���~�b�h�Ɠ����Ӗ��ł̗��j�̍��Ղł���B�x�i�Ζ��Cp182�j
![�]�Ɖ��z](../04112901.jpg) �]�Ɖ��z
�]�Ɖ��z
�Ζ،���Y�i���j
2004�N9��25��
�V����
1575�~�i�ō��j
�킽���́u�Ȋw�I�v�ł��邱�Ƃ�ے�ł��Ȃ��l������ǂ��A�����̏d�݂́A�Ȋw�I�ł��邱�Ƃ�W�J���Ȏv�l�����Ő��܂�Ă��Ȃ����Ƃ��m�����B
���������邱�ƂŁA�킽���́u�Q���v�u�߂��݁v�u����v���ɂ́u��ԁv�B
�����Ɂu�M���v�����܂�A�u���i�v�����܂��B
�������A���̕��̒�����N���o��悤�ȁu�Ȃɂ��v�͂Ȃ낤�B
�킽���̂�����̒��ɂ́A��̂Ȃɂ��̂�������B
���W�J���Ȃ��̂ƁA�W�J���Ȃ��̂ƁB
�������A��͂茾�t�ł����A������l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���B
�܂��A����Ȃ킽���̂����u�N�w�̂���IT���v�Ȃ킯���B
�����̂悤�ɓ����͂Ȃ��B
�ł��A�Ȃ��킩��Ȃ����̂��A�Ȃ��킩��Ȃ����̂Ƃ��ė������Ă������Ƃ����v�l�̊��e���̂悤�Ȃ��͎̂���������������Ȃ��B
�����̂�������A��₩���̕�������ɂ����ł��������B
�����āA�ł���Ȃ�ꏏ�ɍl���A�����o���܂��傤�B
���R�ɍ��e�������}�X�B
���āA������������A�v���Ԃ�̃��[���������������B
�����A����͂����ˁB
�͉�ʂ��Ȃ��ƁB
2004/11/28 (��) �@�� ��
�y�Q�s���z
8���ɖڊo�߂�B
�͂ǂ҂���B
����A����w�ɂ��鏑�X�ŁA�n���̐M�Z�����V���Ђ��甭������Ă����ꕶ�����̗����������̂ŁA���w���B
�A��̂������ł����Ɠǂ�ł����B
 �ꕶ�����̗�
�ꕶ�����̗�
�M�Z�����V���ЕҏW�Ǖ�
200�N7��27��
�M�Z�����V����
1470�~�i�i�ō��j
����w��3�ԃz�[���ɂ́A���j���h�J���Ƃ����Ă���B

���j�́A�����x�R�[���Y�n�ŁA�ꕶ�̖��́A������V��i�C�t�̂悤�Ȑn���n�̐Ί���������̂��ˁB
����́A�䒌�ՂƂ����ꕶ�̂ɂ����̂��邨�Ղ��c���Ă邵�A�ꕶ�̃r�[�i�X�����邵�ˁA�����q�͓ꕶ�ȂˁB
���N��2���ɖS���Ȃ�ꂽ�Ԗ�P�F���i����V�ꎁ�̏f���ɂ�����j�ɂ��A���{�l�̐e�a�����̂悤�Ȃ��̂́A�_�k�����̂���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����ƈȑO�̐�Z���������Ă������̂ȂA���Ă��Ƃ��B����͓ꕶ�l�́A�ƍl���Ă����낤�B
�܂��A����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A�{�{�����Y���ꂽ���{�l ���v���Ԃ�ɂЂ��ς�o���ēǂݎn�߂���A����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
 �Y���ꂽ���{�l
�Y���ꂽ���{�l
�{�{���i���j
�Ԗ�P�F�i����j
1984�N5��16��
��g����
693�~�i�ō��j
�Ȃ̂ŁA�����A�����̔����܂łЂ��ς�o���Ă��Ă��܂��B
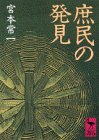 �����̔���
�����̔���
�{�{���i���j
1987�N11��10��
�u�k��
1050�~�i�ō��j
���܂������ēǂ�ł݂�ƁA�ȑO�ǂƂ��Ƃ͊m���ɈႤ����������B
�����ĂȂɂ����A�Y���ꂽ���{�l�ɂłĂ���A�u���������`���ҁv�̎��S���̃G�g�X�Ƃ������A�G�l���M�[�̏������ɐS�ł����̂��B
2004/11/27 (�y) �@�� ��
�y�ɓ߂���A��z
�ߌ�1��25���A�ɓ߂���߂�B
�����̐͐��V�B���w�O�̊ۈ�̉��x�v��19���������Ă��āA�S�Ȃ����킽���̐S����V�C�B
12�24�F�F���̊J�Â����`�������������ޒʐM�s���A���ꂩ�班�����������\��B
�f�����Y��Ă����ʐ^�B
�{��ɍs�����тɐH�ׂĂ���n�{�̒Y�ΏāB
����ƈ��Ē��i20�n�́j�̑g�ݍ��킹�́A�������Ă�ׂ���̂Ȃ낤�ˁB
�킽���������Ԋ���Ă����A�Ƃ������n�}���Ă��Ă���B

����ɂ́A���イ�肪�t���ė��ĂˁA���Ԃ�͒ɕ���ȂƎv���B
���Ĕѓc�ŎU�X��������������Ă��邱��A���イ��͒ɕ���ɂ����̂��A�Ƃ����悤�Șb�������Ƃ��L�����Ă���B
�ɕ��ł��Y�݂̕��́A���イ���H�ׂ悤�B
�y�����̑��������X�z
�ɓ߂ɂČߑO6���ɖڊo�߂�B
�ɓ߂͐��V�B�R���݂����ꂢ���B
�܂��́A12�14�F�{�Ɖ���Y�N��������I
12��14���i�j 13:30 �`�@�F�{�s�Y�ƕ�����فE6F
�����o���C���ɂ�
�u���̉���́@�w�N�w�̂���IT���x�������Ă��悤�Ǝv���B
���e�͏��X�ʓ|�Ȃ̂�����ǂ��A���J�����_���͂̃g�|���W�[�Ɓu���m�̐_�l�v����A���^�|�������^�|�����̃g�|���W�[���l�@���Ă����B
�܂�A�������̔����Ă�����́A�u���i�v�Ƃ͂Ȃɂ����l���Ă����A���Ƃɂ���āA�u�l����IT���v���A���{�̗��_�̒��ŁA�����ł���̂����l�@���Ă������B
�܂��A���ꂪ���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�ݏo�����̂����A���̏��i���}���A�r���e�B�����A�܂�A���ω��ւ̓K���x�������ƂŁA�u�n���I�j��v�ƌĂ����̂Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ��ˁA�y�������b�ł���A�Ǝv���̂��B
�Ƃ������ƂŁA���F���HP�����Q�Ƃ��������B
�� http://www.geocities.jp/momokumakai/
��ӂ̂��ƁA���̓X�́A�X�����Ȃ��Z��X�Ƀ|�c���Ƃ�����A�܂�Łu�����̑��������X�v�i�{���j�̂悤�Ȃ��̂������B

���Ԃ�A����͂ǂ��ɂł�����悤�ȃt�B���s���E�p�u����������ǂ��A�{���͌ς��K�������Ă����Ȃ��̂��A�Ǝv�킹��悤�ȕ��X���A�ƂĂ��y�������Ԃ����o���Ă���Ă����B
�܂��A�ςł��K�ł�������A�Ɓu�����K����ۂ�ۂ��v��낵���A�킽���͂��̋�ԂƓ������Ă����̂�����ǂ��A�ȒP�ɏ����A�y���������A���Ă������Ƃ��ˁB�i�j
���̌�A�s�������[������������A�Ȃɂ��u�|�c���v�Ƃ������͋C�������ĂˁA�킽���̈ɓ߂̈�ۂ́A�u�����̑��������X�v�Ɓu�����K����ۂ�ۂ��v�̃n�C�u���b�h�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��Ă���B
2004/11/26 (��) �@�� ��
�ySense of Wonder�z
�ߑO6���N���B
�͂�����B
�����͎̐O�̓сA��R�̐l�o�ƂȂ邾�낤�B
���āA���A�킽����IT���ɂ��čl����Ƃ��ɁA��ԗ���ɂ��Ă���Ƃ������A�E�C�����������Ă���̂�����V�ꎁ���i����͊�䍑�b���y��ʕ���b�������݂������j�B
���̏o��́A�{���́u�N�w�̓��k�v�����Ƃ��āA���ꂪ���i���������߁A����ɔ������܂����t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�Ɏn�܂�B
 �t�B���\�t�B�A�E���|�j�J
�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J
����V��i���j
2001�N3��10��
�W�p��
2600�~�i�ŕʁj
�����t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�́A�킽���ɂƂ��Ă͖��ɂ܂�Ȃ�����ȑ㕨�ł����āA���ׂ̈ɁA�t���n�I�ɁA�p�������Ȃ���A45���߂��āA�킽���͓N�w�Ƃ������̂ƌ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������킯���B
����ǂ��A�܂�����Ȍo�܂������Ă��A�u�N�w�̂���IT���v�ȂǂƂ����A�܂�ň�ʂɃC���[�W�����IT���Ƃ͉�����������������u�����ł����肵�Ă���̂�����A�C���X�s���[�V���������鍎q�̈ꝱ�͖ʔ����B
�����āA�Ȃɂ������������A�����Ƃ������������Ă邱�Ƃ́A����鍎q�U����y�������Ă���i�܂����̋t�����邪�j�̂������Ȃ̂��낤�A�Ǝv���B
�����Ă܂��A�������������o���E�C�������Ă���B
���ꂪ Sense of Wonder �Ȃ̂��낤�B
Sense of Wonder �Ƃ������t�́A�i���̌��t���ŏ��ɋ����Ă��ꂽ�jR�E�h�[�L���X�Ɍ��킹��ΉȊw����S�Ȃ̂��낤����ǂ��A����V��Ɍ��킹������Ƒ傫�ȊT�O�ɂȂ��Ă��āA�����I�m�����Ώې����ӎ��܂ōL�����Ă���B
����͊���}����������̂��A����Ƃ����̎����������낵�Ă���y��܂Ō���̂��̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂��B
�N�w�i�`����w�j�́A�A���X�g�e���X������I�Ȏv�l�^�p������o���Ă����u��Ώ̘̂_���v�ɂ���čl���邱�Ƃ��K���ɂȂ��Ă���̂ŁA�_���I�Ȗ������N�����Ȃ��悤�ɍl���čs���A�Ƃ����̂��Œ���̃��[���ɂȂ��Ă���B
����ǂ��A�����I�m�����Ώې����ӎ��܂ōL�����Ă��钆��V�ꗬ��Sense
of Wonder �́A�u�Ώې��̘_���v�ł���A�`����w���������낵�Ă���A������x���Ă���u�u���ӎ��v�Ƃ����y��̑��݁A�܂莩���̍����Ƃ̑Ώې����ɂ���B
������A�u�킽���͍��ł���v�I�Ȑ_�b�I�\������n�܂��Ă����܂�Ȃ��̂��B
���ꂪ�A�ŋ߂̔]�Ȋw��Q�m����͂����炩�ɂ��Ă��邱�ƂƖ������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�܂܂��ʔ����̂ł���B
�킽�������܂Ŏ��Ԃ��₵�Ċw��ł����A�o�ϊw��A�����w��A���w��A�~�[���_��A�l�b�g���[�N�_�Ƃ��������Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����̂ł���B
�܂�A�ނ́A�u�Ώې��̘_���v�́A���̉Ȋw�N�w���z���Ă��܂��Ă��邯��ǂ��A�Ȋw���܂�����𖾂炩�ɂ��Ă���悤�Ɏv����Ƃ��낪�ʔ����̂��B
�����Ďv���킯���B
���̃o�C���W�J���I�Ȃ��̂̌������ASense of
Wonder �Ȃ̂��낤�ˁA�ƁB
�����āA����͖ڂ̂��ƂȂ̂��낤�A�Ǝv���B
����́A�Ȋw�Ƃ����A���Ɩڂ̑e���ڂƁA�Ώې��̘_���Ƃ����A����ɂ��߂��܂₩�Ȗڂ̓�d�\���ł���B
�����ĕt��������A����͎����������t�Ō���������ɂ�����̂̂悤�Ɏv����i�����A����͌��t�Ō��O���瑶�݂��Ă͂���j�B
 ���ƌo�ς̃��S�X�\�J�C�G�E�\�o�[�W���V
���ƌo�ς̃��S�X�\�J�C�G�E�\�o�[�W���V
����V��i���j
2003�N1��10��
�u�k��
1575�~�i�ō��j
 �Ώ̐��l�ފw�\�J�C�G�E�\�o�[�W���X
�Ώ̐��l�ފw�\�J�C�G�E�\�o�[�W���X
����V��i���j
2004�N2��10��
�u�k��
1785�~�i�ō��j
���2���́A�J�C�G�E�\�o�[�W���V���[�Y�̒��ł��A���o�ϓI�ȁA�Ƃ����������F�Z���킯�ŁA�킽���̌����E���^�W�̗����́A�����ɑ�������Ă���i���ꂾ���ł͂Ȃ�����ǂ��j�B
�����́A�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�ɔ�ׂ�Ίi�i�ɓǂ݂₷���i�܂��A������t�B���\�t�B�A�E���|�j�J���Ӓn�ɂȂ��ēǂ��ʂ�������Ȃ����j�A�܂�����͍l���邱�Ƃ���߂Ȃ��Ă��悢���Ƃ������Ă���Ă���B
����Ȏv�l�̒B�l�̂悤�Ȑl�����āA���̍l�������킽���́AIT���Ƀ��^�t�@�[�̂悤�Ɏg���Ă���̂�����ǂ��A����͂ƂĂ��K���Ȃ��Ƃ��Ǝv���B
 ���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�
���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�
��䍑�b�i���j
2004�N7��22��
�V���_��
1575�~�i�ō��j
����A�{�肩��A��A������̌��ǂłЂƖ��肵�Ă�����A��䕛��b�̏��������ꍑ�Ƃɂ��ۂ����͂����B
��r�I���߂̖{�������̂ŁA���قǎ��Ԃ������炸�ɓǂݏI�����B
�������A����ł́A��ʂ̓ǎ҂ɔނ̎咣�𗝉����Ă��炤�͓̂�����낤�ȁA�Ƃ��v�����B
����V���ǂ�ł���i���Ȃ��Ƃ���L��3�����j�A�܂������ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤����ǂ��A����́A�\���Ƃ��Ă͂ق߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��悤�Ɏv���B
����́A���܂ł̃p���_�C���Ƃ́A��������l�ςŎ��ۂ����Ă��邱�ƂȂ̂ł����āA�ǂނق������̃��K�l�i��ɏ������ڂł���j�����Ă��Ȃ��ƁA���ꍑ�Ƃɂ��ۂ��́A�g���f���{�Ƃ����v���Ȃ��̂�������Ȃ��B�i�܂��A����Ɠ��l�̊낤���́A�킽���̕\���ɂ��̂���Ƃ������Ƃ��낤���j
�������A���̏�����t�̊�]�̖����ɔ�ׂ�A���ꍑ�Ƃɂ��ۂ��ɂ́A��]�͌�����B����́A���^�Ƃ������̗̂������A�����Ƃ̊�{�p���ł��邱�Ƃ𗝉�����Ă��邩�炾�Ǝv���B
�㓡�V���Ƃ�����茧���������Ƃ������B
�ނ̌��t�B�i�����̎O���j
�l�̂����b�ɂȂ�ʂ悤
�l�̂����b������悤��
�����ďV�������߂ʂ悤
�Ƃ������ƂŁA�����̂킽���͈ɓ߃v�����X�z�e���ōu���ł���B
2004/11/25 (��) �@�� ��
�y���J���[���̂悤�Ȃ��́z
�{��ɂČߑO8��30���ɖڊo�߂�B
�{��͐��B
�����́B
����̋Y���A�ǂ݂܂����B��䕛��b�̃y�[�W�����܂����B
�����{���ɋ����܂����B�{����v�����̂��A���̃|�W�V�����̐l����^���Ă������Ƃ��B�o�g���y���Ă̂��A�u�Ȃ����˂��A���̐l�v�Ɣ������Ă��܂����B�i���A�����̕��В����B�܁A����ƂȂ�����A������ȁB�j
��������
�n�C�u���b�h�v�z�̊m�����`�c粌��̑��l�̓N�w���̂Q�܂ň�����ēǂ�ł݂܂����A���A�d�v�������킩��Ȃ��B
�������Ȃ��ł��B���炭�O����A�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�͐ϓǏ�ԂŖl�̕����ŐQ�Ă��܂��B�u���ÓT�v�͓ǂ�ł��āA�������t�B�b�g�����������̂����ǁA�����́E�E�E�ă`�������W�E�E�E�ӂ��B
���̕��́A�u�����Ȃ̂���l�l�v�������ƂȂ̂�����ǁA���̂悤�Ȏv�z�������n�߂��̂́A���̎��_�������̂ł��傤�ˁB�����m���Ƃ��A���c�m���Ƃ��e���r�Ō�������ƁA���̐l�͖�l����A�ǂ��������Ƃ��l���Ďd�����Ă����낤�H�Ƃ����v���Ă��܂��̂ł��B |
�͂͂ͥ���m���ɁA���ˁB
�킽���̊S�́A�u���Ƃ�������v�ɔ@���Ɂu�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A���̋��ꏊ����������̂��A�Ȃ̂����A���̋��ꏊ���������Â���_���Ƃ͂����Ȃ���̂��낤���A�Ƃ������ƂȂ̂͗������������Ă���Ǝv���B
���̋��ꏊ�̊m�F�͈ꉞ�͂ł��Ă��āA����̓C���^�[�l�b�g�̏ی����͂ł����ƁA�㉺�ł͂Ȃ��A���E�Ɍ����Ƃ��̉E���ŁA����͂ƂĂ��n�C�u���b�h�Ȏ���ȂB
��������E�e�������e�ł͂����\�����Ă���B
------------------------------->8
�����E�ɂ݂�
�ł́A�C���^�[�l�b�g�Љ�̎l�̏ی����͂����E�ɂ݂Ă݂悤�B���E�ɂ݂�Ƃ́A�O���[�o�����ŕ������Ƃ��̍��E�̗̈�ł���B�����͒�R�~���j�e�B���������A�E���͍��R�~���j�e�B���������Ă���B
���ɖ��炩�Ȃ悤�ɁA���̍��E�ɂ݂���@�ł́A����̊S�͉E���i���R�~���j�e�B���j�ɂ����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����i��R�~���j�e�B���j�ɂ́A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̉��l�ς̑���͍ŏ�����Ȃ����炾�B��V�ی��ɂ̓e���g���[���͊ł���A��W�ی��ł́g�ǂڂ�h�Ȃ̂ł���B
�܂�A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv���u���Ƃ�������v�ɁA����̑��݂̎�����u���ׂ����l�ς́A���E�ōl�����Ƃ��̉E���̗̈�i���R�~���j�e�B���j�ɂ���ƍl���������悢�Ƃ������Ƃ��B����͂���Ӗ����R�ł���B�����̂��A�n��Љ���A�������Ƃ��u��v�̑��݂ł���A�e���g���[�����琶�܂ꑶ�݂��Ă�����̂����炾�B
����ɂ��̏ꍇ�A�E���̗̈�̑�U�ی�����������̋��ꏊ�Ȃ̂��ƍl����K�v���Ȃ����낤�B��T�ی����܂߂ĉE���i�R�~���j�e�B�u���j�Ȃ̂ł���B����́A��Ȃ菬�Ȃ�O���[�o�����̉e���͔����������̂��u���Ƃ�������v�̓����ł���Ƃ������Ƃ��B�i�}-6�j
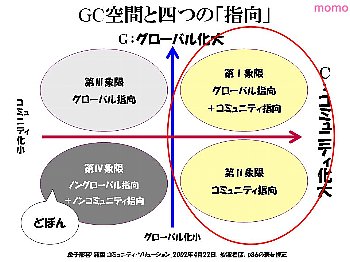
�}-6
�܂�A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A�e���g���[�������Ƃ��Ȃ�����A�O���[�o���̋�C�������u���Ƃ�������v���邵���Ȃ��B�����炱���厖�Ȃ��Ƃ́A������A�e���g���[���ƃO���[�o�����̃n�C�u���b�h�ŗ������邱�Ƃł����āA��T�ی��Ƒ�U�ی��̓�ґ���̂悤�ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�� �L���Ĕ����R��
�ł́A���̉E���i�e���g���[���ƃO���[�o�����̃n�C�u���b�h�Ƃ��ẴR�~���j�e�B�u���j�̗̈���l�b�g���[�N�O���t������Ƃǂ��Ȃ�̂��낤���B���ꂪ�u�L���Ĕ����R�сv�ł���B�i�}-7�j
���́u�L���Ĕ����R�сv�Ƃ́A�Љ�w��M�E�O���m�x�b�^�[�̂����u�ア�R�сv�iweak
ties�j�̂��Ƃ��B�O���m�x�b�^�[�͓]�E���ɂ�����l�ԊW�ɒ��ڂ��A�]�E������ہA�����R�сinarrow
ties�F������l�E�N���X�^�[�^�̃l�b�g���[�N�}�j�����A�ア�R�сi�܂�ɂ�������Ȃ��l�j������ɗ��A�E���Ă��邱�ƁA�l���̊��p���]�E���ɔ�������m�C�Y���������A�M���ł���ǂ����������Ŏ��W���邽�߂̍ł������I�Ȏ�i�ɂȂ��Ă���Ǝ咣���Ă���i�w�]�E�x�CM�E�O���m���F�^�[�C1998�N11���C�~�l�����@���[�j�B
���̃O���m�x�b�^�[�̒����͕č��ɂ����Ă����Ȃ�ꂽ���̂ŁA���\�����A���{�ł͂ނ���A�����R�т̕����]�E�ɗL���ł���Ƃ����ӌ������������̂����A�܂�����́A�N���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N���@�\���Ă����Ƃ����Ӗ��ł͓��R�̂��Ƃ��낤�B
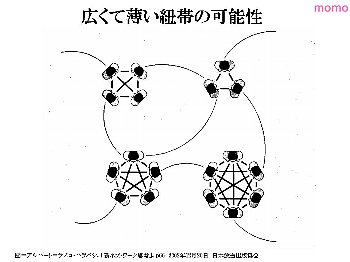
�}-7
�������A���c�L�j���̒����ɂ��A������{�ł��ア�R�т͍K���ȓ]�E�̑傫�ȃt�@�N�^�[�Ȃ̂ł���i���c�L�j�C�w�d���̒��̞B���ȕs���x�C2001�N12���C�������_�Ёj�B
���̂��Ƃ́A���X�N���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N�^�ł��������{�Љ�ɁA�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N���Z�����Ă��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ����邾�낤�B
�܂�A���́u�L���Ĕ����R�сv�̓����́A�N���X�^�[�����ɂ��Ȃ�����A���̃N���X�^�[���z���A�m�[�h�i�j��������n�u�I�ɋ@�\�����A����̃l�b�g���[�N���L���Ă������Ƃɂ���B
�����ł́A�m�[�h�i�j�̓N���X�^�[����ɂ��Ȃ�����A����̃n�u�I�\�͂����邱�ƂɂȂ邾�낤�i���̃n�u�I�\�͂̂��Ƃ����́u�K���x�v�|���ω��K���\�́|���ƍl���Ă���j�B
���̂悤�ȊW������u�L���Ĕ����R�сv�Ƃ́A�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ƃ����_���E�l�b�g���[�N�̃n�C�u���b�h�Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł��悤�B�i�}-8�j
�����Ă���́A�C���^�[�l�b�g�̒��ɂ������ɑ��݂���W���Ȃ̂ł���i�M�҂̎d���̐��������͂܂��ɂ���ł���j�B
�C���^�[�l�b�g�͊m���Ƀx�L�@���Ɏx�z����Ă��邩������Ȃ����A�u�L���Ĕ����R�сv���m���ɂ����ɂ���A�@�\���Ă���B���ꂪ�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̂����Ȃ�IT���̉\���̈Ӗ��ł���B
�䂦�ɁA�C���^�[�l�b�g�̑��݂��������邽�߂Ɂu�ア�R�сv���A�����Ď��́u�L���Ĕ����R�сv�ƌĂ�ł���B����́A�u�L���Ĕ����R�сv��̊����邽�߂ɂ��A�܂��͎�����C���^�[�l�b�g�̒��ɒu���ׂ��Ȃ̂��B
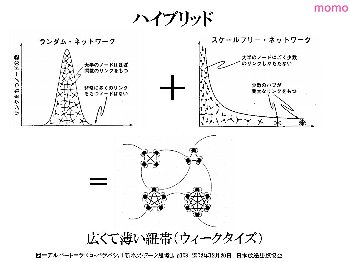
�}-8
���p�I��------------------------------->8
���̌��23���ɏЉ���u�l����IT���v�i�M����IT���j�ւƑ����̂����ǁA�͂����Ă���Ȃ̂ŊF����͗������Ă����̂��낤���B
����Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��Ă��AIT�͂�����IT���낤�A�Ƃ����ӌ����������Ă����������A�ق��Ă��������܂̂������Ƃ��Ă���悢�̂��A�Ƃ����ӌ������������������A�u��[���l���悤�I�����͑厖����I�v�Ƃ������ƂŁA�ݕ��̑��B�ɂ������l�����߂���������̂�������Ȃ��i�܂苦����̔ے�ƃX�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ւ̖ӖړI�]���j�B
�������A�����̍l�������A���������u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̕ǂ̌����ł���A�Ə������Ƃ���ŁA�͂����Ăǂ��܂ŗ��������̂��낤���B
�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A�����������u���^�̗��_�v�i��2�j�����ɂ��đ��݂��Ă���Y�ƂȂˁB�i�z���̌o�ϊw�|�J����`������ח�����j
�������������̎Љ�́A����A�u�����̌����v�i��1�j���x�z�I�Ȃ̂ŁA�����A���l�̑��B�͑��^�⏃���Y�ł͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邵�A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv���g�������l���U�������ƂŁA�i�������Ƃɂ�����j�u���^�̗��_�v�͉v�X�ɂȂ��Ă���̂����A����Ɠ����Ɂu�����H���Ƃ����Y�Ɓv�͕ǂ��Ă����B
�������܂��A�ݕ��̉^�p�����܂��l�����āA����Ŗׂ���l�����邩��Ƃ����āA�Љ�S�̂̑����l�͑����鎖�͂Ȃ��̂����A�d�_��`�҂��咣�����悤�ɉݕ����̂��̂���͉��l�̑��B�͂����Ȃ��̂��ˁB�i����V��j
�Y�Ƃɂ����鉿�l�̑��B�͘J���ɂ���ċN����i�܂��A�}���N�X���w�E���Ă����悤�ɐF�X�Ɩ�肪�Ȃ��킯����Ȃ�����ǂ����J���̑a�O���Ă���B�����獡�̂킽���͐E�l�I�ȘJ���̔閧��T�낤�Ƃ��Ă���j�B
�܂��A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�ɒ��ɂ��A�����Y��Ă�����������̂���Ȃ����낤���A���Ă��Ƃ��B�܂�u���^�v�̂����Ă���Ӗ������B
�����炱���A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�͕ǂ��Ă���̂ɁA������CALS/EC�́A�܂������̌��������ŋ@�\���悤�Ƃ��Ă���킯�����́A�Ȃ�̖�������ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ����肩�A�����v�X��₱�������Ă��܂��Ă���B
����������������悤�ɁA����X���A�܂��ł��邱�ƂƂ��āA�u�l����v�Ƃ����X�p�C�X��IT���ɐU�肩���邵���Ȃ��̂��낤�ȁA�Ǝv���B
�����āA������ǂ������甭���҂��������Ă����̂��낤�A�Ȃǂƍl������́A���炪�u�l����IT���v�����H���邱�ƂŁA�����҂��܂߂��u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�i��j���ω����Ă����A�ƍl���������悢�A�Ƃ����̂����̂킽���̍l���B
�܂�A�u��̘_���v���ˁB
���ꂩ��IT���ɑ���A�����ЂƂ̌���ɂ��ď����Ă������B
�������ƍ�������IT����i�߂Ă����ƁA���̐�ɂ₪�āu�l����IT���v����������Ă���悤�Ɏv���Ă���������邯��ǂ��A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
����͂��Ƃ��A�}���N�X�E���[�j����`���A�ߑ�ȑO�̏W�c�I���^�̉��l�ς��A���{��`���r��̂��Ƃ���̂����ՂɁA�Љ��`�����������A�ƍl���Ă����̂Ɏ��Ă���B
���{�̗��_���R���g���[�����邱�Ƃ́A����ȊȒP�Ȃ��ƂłȂ����Ƃ́A���Ƃ������オ�ؖ����Ă��܂��Ă���ł͂Ȃ����B
���{�̗��_�ɂ��i���^�́j���l�ω�̂ƃR�[�h���͍ی��Ȃ������B
���ꂪ�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�i�C���^�[�l�b�g�ی����㉺�Ɍ����Ƃ��̏�̕����j�̓����Ȃ̂���B
������u�l����IT���v�́A�ŏ�����A�u�����ƍ�������IT���v�Ɓu�l����IT���v�̃n�C�u���b�h�Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ��ƁA�S�Ă��X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N���ɉ����������܂܂ƂȂ邾�낤�B
�����āu�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A���ꂩ�瑶�݂�ے肳��Ă��܂��킯���B
����͂Ȃɂ������^�ł��邩�炾�ˁB
�n�C�u���b�h�Ȃ��̂̌����������́A���Ƃ�����������ʂ���B��̃��K�l�Ȃ̂��Ǝv���B
�Ȃ��Ȃ�A���Ƃ�������̓n�C�u���b�h�ɖ������Ă��邩�炾�ˁB
��1 �����̌���
�E���i�͂��̂ł���i������l��O���L�҂̐l�i�⊴��Ȃǂ́A�܂܂�Ă��Ȃ��j
�E��������������
�E���m�̉��l�͊m��I�ł��낤�ƂƂ߂Ă���B�v���\�B
��2 ���^�̌���
�E���蕨�̓��m�ł͂Ȃ��B���m��}��Ƃ��Đl�Ɛl�Ƃ̊Ԃɐl�i�I�ȂȂɂ����ړ����Ă���B
�E���ݐM���̋C������\�����邩�̂悤�ɁA���Ԃ��͓K���ȊԊu�������Ă����Ȃ��B
�E���m��}��ɂ��āA�s�m��Ȍ���s�\�ȉ��l�������Ă���B
2004/11/24 (��) �@�� ��
�y���̉x�y�z
�ߑO6���N���B
�͂�����B
�܂��́A11�19�{��ł̍u���Ŏg�p����PPT���f�����܂����̂ł����p���������B
��  �@��BD041119s.zip �@�@-zip 2.71MB
�@��BD041119s.zip �@�@-zip 2.71MB
����PPT�́A11�17�����ł̍u���Ŏg�p����PPT�̂��ƂƂȂ��Ă�����̂ŁA3���ԃo�[�W�����ł���i�����ł�1����30���ł������j�B����Ƀ~�[���_����M���̍\���ւ�������4���ԃo�[�W�����ɂȂ�B
 �I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|
�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|
�O������i���j
2004�N9��20��
������
756�~�i�ō��j
���̖{�ɂ͋������ꂽ�B
Sense of Wonder �ł���B
�킽���́A���l�̑��B�i�܂�u�̂��v�Ƃ��Ă̏��i�������ҁ��ɔF�߂��邱�Ɓj�̂��Ƃ��l����Ƃ��A�i���j�̂悤�ȃg�|���W�[���g���Ă��邱�Ƃ͑O�ɂ��������B
����ɂ́A���i�����^�ƌ����̃n�C�u���b�h���Ɨ������Ă��邱�Ƃ��B
�ŋ߂́A20���̋Y���ɏ������悤�ȁA�E�l�����ݏo�����i�̓������l���Ă��鎞�Ԃ������̂����A����͂Ȃ��Ȃ��ʓ|�Ȃ��̂Ȃ̂��B
�Ȃɂ��낻���́A�����̌����z�����^�̌�������荞�݁A�����ď��i�Ƃ��Ďs��ɕ����߂��Ă���i���i�ɐl�i���h���Ă��܂��j���ƂŁA�����̌����Ɋ�Â��Đ��Y���ꂽ���i�Ƃ͂܂����������ȉ��l�ݏo���Ă��邩�炾�B
�����20���ɏЉ���w�H�̒ė����~���x�i���v
�ҁj�ɏЉ��Ă���A�H�́i���y�́j�B�l�����̂��ƂŋC�Â����̂́A�ނ�́A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_�i�Z�p�͏o�Ł|�����炸���̂�I��ɂ����j�Ƃ͈Ⴄ�Z�p�i�A�̋Z�p�j�������ď��i�ݏo���Ă�����Ă��Ƃ��B
���Ƃ��A�ݖ��□�X��݂�́A�����ŏЉ��Ă��鏤�i�́A�X���[�t�[�h�ƌĂ�Ă�����̂ŁA���Y���ł���A����ł���A�������y�̎��Ԃ��o�ď��i�����ꂽ���ƂŁA����ȑ��݉��l�������Ƃɐ������Ă���B
�������͐E�l�I�Ȃ��̂ł��邱�ƂŁA�����̌����̑ɂɈʒu����i���̂��ߑ�ʐ��Y�͂ł��Ȃ��j�̂����A���̐E�l�I�Z�p�Ƃ́A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_�ő����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Z�p�Ȃ̂��i����A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_�����邩�炱���߂܂��邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ����j�B
�܂�A�w�H�̒ė����~���x�ɏЉ��Ă��鏤�i�ƋZ�p�ɋ��ʂ��Ă��邱�Ƃ͈ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ��A�Ǝv���B
�E�����̏��i�́A���R�����R�̖@���i���y�ł���j�ɂ���āA�o�Ł|������̂ł���B
�E�����̏��i��x�Ƃ����Ƃ��A�����̕x�͂Ȃɂ��v�ʉ\�Ȃ��̂Ƃ��������A�p�b�Z�[�W�i�߂��z�����Ɓj������A�ڂɂ݂�����̂Ƃ݂��Ȃ����̂̋��E�Ɍ����悤�ȁA���R�E�Ɛl�Ԃ̑��ݍ�p�ɂ��x�Ƃł���������̂ł���B
���̂��Ƃ��킽���́A���J���̌����E�|�z���E�|�ے��E�̃g�|���W�[�ɂ����邨����A���̉x�y�i���҂̉x�y�j�ɂ�������̂��낤�A�Ǝv���Ă���B
���̉x�y���A�킽���͍H�Ɖ������ȑO�̈��̂悤�Ȃ��̂��Ɨ������Ă����B
����́A�o�Ł|�����炸���̂�I��ɂ����̂ł͂Ȃ��A��̎����R�̗͂����N����悤�ɁA���J�Ɏ��������邱�Ƃł���B�i����Ӗ��l�H�I�Ȏ��R�̎��R���j
���������j���̊W�ł���B
�����������R�ɑ���Z�p�̂�����ł���B
���������A���J���̂������̏��̉x�y���A�킽���͒j�ł��邪�̂ɁA�{���ɗ����ł��Ă���̂��ǂ����͊m�M�������̂��B
�����ɁA�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|�Ȃ̂ł���B
�킽�����A�ŋ߂̃~�[���_�̐����Ŏg���Ă���u�Ȃ��肽�����v�Ƃ������t�������ɂ͂���i���ꂾ���ł����J�����_���͓I�ł���̂����j�B
�����ċ����ׂ��g�̂̃��A���e�B�B
�j���̊W�̕x�B
�킽���́A���̖{��ǂ�ŁA�w�H�̒ė����~���x�ɂ���������E�l�̌��t���v���o�����B
�w�v�w�͈ꏏ�̕z�c�ŐQ�Ȃ��Ă͂��߂��x
�i�킽���͂��̌��t�ɂ��u���̉x�y�v�Ɣނ�E�l�̉A�̋Z�p�Ƃł��ĂԂׂ����̂̓��ꐫ�������Ă���j
���̖{�́A���̉x�y�ɂ��ď����ꂽ�{���A�Ƃ킽���͌������Ă��܂��������A���̖{��ǂ����̈ӌ��������Փ���}�����ꂸ�ɂ���B
����͌��Z�p�i�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�j�ɂ����āA���R�ɑ��鏗�̉x�y�Ƃł��ĂԂ��Ƃ̂ł���Z�p�Ƃ����͉̂\�Ȃ̂��낤���A�Ƃ�������ɂȂ���̂����A���`����Ă���_�Ƃւ̃V�t�g�Ƃ͉������A���̖{���I�ȋZ�p�_�̂Ƃ���Łi�n�C�f�b�K�[�I�ȈӖ��łł���j�₤���ƂɂȂ邾�낤�A�ƍl���Ă��邩�炾�B
�Ƃ������ƂŁA�����̂킽���͋{��֔�ԁB
JAL1883�ց@�����H�c�@9:05���@���@�{��@10:50���ł���B
7��45���ɂ͎�����o�����B
2004/11/23 (��) �@�� ��
�y����ƈ�{�E�e�z
�ߑO5��22���N���B
�͂��ԂB�ł��Â��Ă悭�킩��Ȃ��B
���āA�悤�₭��e���e�̈�{���E�e�ł����B
����͘A�ڂ��̂ŁA���ݕ�����������s���Ă���u���z�R�X�g���v�Ƃ����G�����Ɍf�ڂ���Ă���B
�������F�l�̂��ڂɂ����鎖�͏��Ȃ����Ǝv���B
�Ȃ̂ŁA���܂ł̘A�ڕ��͓��T�C�g�œǂ߂�悤�ɂ��Ă������ƍl���Ă���i�܂Ƃ߂�̂͗������{�ȍ~�ɂȂ邾�낤���j�B
����͘A�ڂ̍ŏI�����̂ŁA�Y�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������̂�����ǂ��A����ȕ��ɂ��Ă݂��B
���l����IT��
���Ă��̘A�ڂ̍Ō�ɂЂƂ����A�u�M����IT���v�̃R�c�������Ă������B
����͂ƂĂ��ȒP�Ȃ��Ƃ��B
����́A���܂ł̌������ƍ������ׂ̈�IT���ɁA�u�l����v�Ƃ����X�p�C�X����U�肷�邱�Ƃ����ł����B
�@
IT���ɂ�������ł��錾�t�i�~�[���ł���j���A�R�~���j�P�[�V�����E�c�[���ł������A����͌������ƍ��������u������B
�������l���Ă݂ė~�����i�����ɋC�����͂����j�B
���t�̓R�~���j�P�[�V�����E�c�[���Ƃ��Ă̖������z���āA�l�ނ̗��j�ジ���Ɓu�l���邽�߂̃c�[���v�ł������Ƃ������Ƃ��B
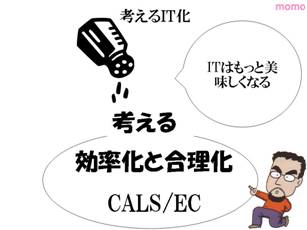
�����IT���ɂ����Ă��u�l����v���Ƃ�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�u�l����v���Ƃ������A�������ɍK���������炷���̂����炾�B
�܂��A����Ȉz�ł���B
���Ȃ�L�����͂��Ǝv���邩������Ȃ�����ǁA�킽���̍��̊����ł́A����͏L�����Ȃ�Ƃ��Ȃ��B
�����āA�킽���̍l�����i���Ƀ~�[���_�Ǝ�̘_���j�����܂藝���ł��Ă��Ȃ����́A���̕������ł͌�����Ă��܂���������Ȃ��ȁA�Ƃ��v���B
����́A�u�����ƍ������v�Ɓu�l����v���Ƃ��Η����Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ��B
���ꂪ�Ⴄ�̂ł���i�����̎v�����݁j�B
�l����IT���Ƃ́A�u�����ƍ������v�Ɓu�l����v���Ƃ̃n�C�u���b�h�ł���B
���̃n�C�u���b�h���ł���v�l�͂������u�N�w�̂���IT���v�̔閧�Ȃ̂��B
�����ăn�C�u���b�h�̎v�z�������A���ƎҒc�̃x�[�X��IT�����\�Ƃ��Ă���B
�ȉ�����̌��e���甲���ł���B
�܂�A���ƎҒc�̃x�[�X��IT���Ƃ́A����Ƃ��ẴN���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N��w�����Ȃ���A�\�����e�Ћy�ъe�Ђ̎Ј����X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ɑΉ��ł���\�͂������Ƃ�ړI�Ƃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����͎��̎O�̈Ӗ��������ƂɂȂ邾�낤�B
1. �u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�ɏ]������S�Ẵ����o�[�̃}���A�r���e�B�i�Y���j�ƐM���̔\�͂̌���
2. ���ƎҒc�̂̐V���������̊m��
3. �����̎��H�ɂ���Đ��܂��u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̐V���������ƐM���̊m��
���̎��A�����҂Ƃ̋����͂ǂ����Ă��K�v�ƂȂ�B
�Ȃ��Ȃ�A�����̂��A�n��Љ���A�������Ƃ��u��v�̑��݂ł���A�e���g���[�����琶�܂ꑶ�݂��Ă��邩�炾�B
�����H���̋@�\�I�{����O��Ƃ������A�s���Љ���A�����҂��A�҂���������ɗ����Ă���̂ł���B
�����Ɉ��ՂɃO���[�o���[�[�V�����i�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ł���ނ��o���̎��{�̗��_�ł���j�������������ނ��Ƃ�A�ނ�݂ɃN���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N����낤�Ƃ��Ă��A�ǂ�������s���邾�����낤�B
2004/11/22 (��) �@�� ��
�y�����z
�ߑO5���N���B
�̓V��͂悳�������i�Â��̂ł킩��Ȃ��j�B
�܂��́A�v���Ԃ�ɎD�y�ł̓Ɖ���J�Â����肵���̂ł��m�点�ł���B
���D�y�Ɖ���@�w�N�w�̂���IT���x �\�l�b�g���[�N�ƐM���ƃr�W�l�X�Ɓ\
�y�����z 12��7���i�j13�F00�`17�F00
�y��u���z 2000�~
�y���z �����27�@940���C��
�D�y�s������k2��7���ړ��������Z���^�[�r��
�d�b�F011-231-4111�@�@http://www.kaderu27.or.jp/ �@
�y����z 45��
�y�T�v�z �u�t�F���m���j
����F�w�N�w�̂���IT���x�\�l�b�g���[�N�ƐM���ƃr�W�l�X�Ɓ\
�E�l�b�g���[�N�_�i���Ƃ�������̌����@�㉺�����č��E����j
�@�X�P�[���t���[�l�b�g���[�N�̗���
�@�����_���l�b�g���[�N�̗���
�@�K���x�i���ω��K���\�́j�Ƃ��ẴE�B�[�N�^�C�Y
�E�~�[���_
�@���m�̐_�l����u�������^�E���^�E�����̃g�|���W�[�v
�@���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�i�̂��j
�EIT���_
�@���̋��L���甽�Ȃ̋��L�ւ̋�̍�
�@��̘_��
IT���̗����Ǝ��H�������A���Ƃ�������̕ǂ��甲���o����@�̂ЂƂł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����A�Z���X�E�I�u�E�����_�[�Ȏ��Ԃ����y���݂��������B
�y��Ó��z ��ÁF���m���X�@http://www.momoti.com
�y���⍇����z
�y�\����z �܂ɂ��1���փ��[���ł��肢�������܂��B
�@ mailto:e-yoshikawa@h7.dion.ne.jp
�@�E�����O
�@�E���
�@�E���[���A�h���X
�@�E���e��Q���̗L���L�̏�A���\�����������B
�y���e��z ���R�ɂ����Ȃ��܂��B
���F5000�~
�D�y�ɂĂ��҂��\���グ�Ă���܂��Bm(__)m
���āA��������q���܂�����ꂽ�̂Œ��Ԃ�����ꌣ���Ă����킯���B
��͕����́B
����i���j�́A������ŁA�����ڂ̓Q���Ⴕ���́��f�����낤���A�r�[���ɂ͂ƂĂ��ǂ������̂��B
�킽���͑��ɁA���D�ݏĂ��Ə����������Ⴊ��������̏Ă����ŁA����3�t�����Ă��܂����B
�����̂͑�D�����B
�b�x��B����́AWeb���������Ă��Ă���Ƃ����������������B
�܂��́i���j��ɓǂ�ł������������B
http://www.kuniomi.gr.jp/togen/iwai/haiburi2.html
�����ɂ͕���������u��̘_���v�ɂ��ď�����Ă���B
�ł́A���̃T�C�g�͂ǂȂ��̃T�C�g�Ȃ̂ł��傤���H
���̕��ł���B��http://www.kuniomi.gr.jp/
������䍑�b���i���y��ʕ���b�j�ł���B
����V�ꎁ���^����Ă���B
���������Ă��܂����B
�����A�w���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�x�𒍕������B
�iAmazon�ł͈����Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��H�j
�킽���́A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�Ɋւ��āA���ɒn��^�������Ƃׂ̊��Ă���ǂ�Ŕj���邽�߂̗��_�\�z�̊���c糌��́u��̘_���v�ɒu���Ă���킯�����A�����悤�ȍl���������Ă������������Ƃ́A��������y��ʕ���b�������ł������Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B
���̍l�����̍���ɂ́A�u�Z�|�F�Z�p�v�i�e�N�l�[�j�ɑ���l����������̂�����ǂ��A���Ԃ�b�Ƃ킽���͓����Ȃ̂��B
�܂�A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_����ˁB
�w�Z�p�͂��������āA����Ɏ�i�ł͂Ȃ��B�Z�p�͘I��ɂ����ЂƂ݂̍���ł���B���̂��Ƃɒ��ӂ���ƁA�����ŋZ�p�̖{���Ɋւ��Ă܂������قȂ����̈悪�������ɊJ���Ă���B���ꂪ�I��ɂ������ƁA���Ȃ킿�^���̗̈�Ȃ̂ł���B�x
�w�e�N�l�[�̓A���e�E�G�[���i�I��ɂ������Ɓj�̂ЂƂ݂̍���ł���B����͎������g�ŏo�Ł|�����炸������O�ɂ͂Ȃ����́A���������ĐF�Ƃ�ǂ�Ȍ��������Ƃ��Č���������ł��낤���̂��A�I��ɂ������̂ł���B�x
�܂�A�Z�p�̖{���Ƃ́A���R�̎��R�I�v���Z�X�������ĘI��ɂ��Ȃ��悤�Ȗ{�����A�w���R�ɑf��Ŏ��g�݂Ȃ���A�������Ď��R�I�Ƃ͂����Ȃ���肩���ŁA�����ꂽ�{�������݉�������B����͐E�l�����������R�̑f�ނ��ł��낤�Ƌ����ł��낤�ƁA�t�̂ł��낤�ƁA�y�ł��낤�ƁA�ς��Ȃ��x�i����V��j
�Z�p�͏o�Ł|�����炸���̂�I��ɂ����A���ꂪ�Z�p�̖{���Ƃ������̂��B
������A�����ɂ͗ϗ����ق����̂��낤���A�_�����K�v�Ȃ̂��B
�Ƃ������ƂŁA�����͂Ђ����猴�e�����̗\��B
2004/11/21 (��) �@�� ��
�y�㉺�����č��E����݂�z
�ߑO8��03���N���B
�͐��V�ł���B
��ӂ����q���܂������Ă����̂ŁA���i�ɂĈꌣ�B
��V�コ�����炢�������Ă������v���ł���ꂽ���Ē������Q���Ĉ��B
����̗[�������肩��悤�₭�A�]���X������Ă����Ƃ������A�V�i�v�X���������܂��ł��Ă���悤�Ȋ����ɂȂ��Ă����B
�����́A�킽���̍��l���Ă��邱�Ƃɂ��Ă̎��ȗ���I�܂Ƃ߁B
����́u�㉺�����č��E����݂�v
���㉺
| ��i�O���[�o�����ւ̎u�����傫���j |
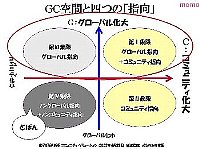 |
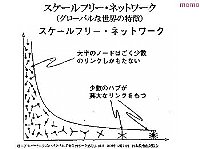 |
| ���i�O���[�o�����ւ̎u�����������j |
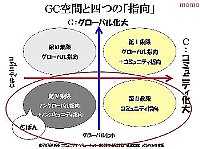 |
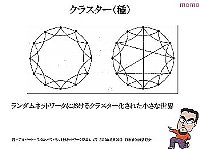 |
 |
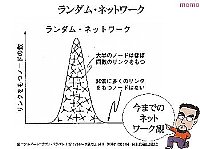 |
�����E
| ���i�R�~���j�e�B���ւ̎u�����������j |
�X�P�[���t���[�Ⴕ���̓h�{���ł���B
�X�P�[���t���[�Ƃƃ����_���̃n�C�u���b�h������B
���n��^�������Ƃɂ͊W�̂Ȃ��̈�B |
| �E�i�R�~���j�e�B���ւ̎u�����傫���j |
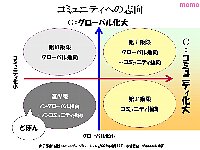 |
 |
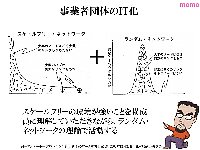 |
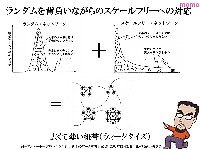 |
���̌����́A�n��^�������Ƃ��A���Ƃ�������i�C���^�[�l�b�g�Љ�j���㉺�ōl����̂ł͂Ȃ��A���E�ōl�����Ƃ��̉E���̗̈�ɋ��ꏊ�����o���������ǂ����Ă��Ƃ������Ă���B
����͂���Ӗ����R�ŁA�n��^�������Ƃ͎�̑��݂ł���A�e���g���[�����琶�܂ꑶ�݂��Ă��邩�炾�B
�������A��Ȃ菬�Ȃ�O���[�o�����̉e���͔����������̂��u���Ƃ�������v�̓����ł���B
�܂�A�e���g���[�����Ƃ��Ȃ�����A�O���[�o���̋�C���������E���邵���Ȃ��B�i�����ő厖�Ȏ��́A����̓e���g���[���ƃO���[�o�����̃n�C�u���b�h�ł����āA��ґ���̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��j
����̓l�b�g���[�N�O���t�ł����A�X�P�[���t���[�ƃ����_���̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̔����čL���R�сi�E�B�[�N�^�C�Y�j�ł���B
����ł��A���̉E���̗̈�Ő�����A�Ƃ������Ƃ��ǂ�Ȃ��ƂȂ̂����A�Ђ�����l���A������\�ɂ��Ă�����̂������A�����ɂ��鐶���̋��ʐ��������悤�Ƃ��Ă���B
���̂ЂƂ��A����������u���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�v�̃g�|���W�[�ł���B
����͑����A�����ɂ�����E�l�I�Ȃ��̂����ݏo�����̂��N���Ɏ����Ă���B
�܂肻��́A���R�I�Ȃ��̂Ƃ́u�Z�|�v�i�Z�p�j��ʂ����v�l�I�ȊW�i�N�w�j�ł���̂����A�悤�₭�����ɗ��āA�킽�����ɂ����Ă��������w�I�Ȃ��̂��Ăш�������o����@��Ɍb�܂ꂽ�킯���B
�Ȃ�ƂȂ��Ȃ����Ă����B
�V�i�v�X�B�i�j
2004/11/20 (�y) �@�� ��
�y���z
�A��̔�s�@�͗\�����30���x��ĉH�c��`�ɓ����B
�^�N�V�[�ŋA�낤�Ƃ�����A�^�N�V�[����͒��ւ̗�B
�Ȃ̂ŁA�v���Ԃ�Ƀ��m���[���ɏ���ċA���Ă����B
�������m���[���́A�������ł��Ă��āA����͉H�c���o��ƁA�V���F�A�C���ƕl�����ɂ����~�܂�Ȃ��킯�ŁA�Ȃ�قǂ���͑����B
�l��������͋��l���k�������ɏ�芷���A���w���ԁB
�Ȃ���A���̎肪���������B
���w����͂����̂悤�Ƀ^�N�V�[�B
�^�]��Ƙb������ƁA10��11���̔���͗����Ă���Ƃ����B
����͌i�C�����Ă���ƌ����Ă��邯��ǁA���ł����Ă�Ȃ��ł����˂��A�Ƃ����b�ɂ͎v�킸���Ă��܂����B
���āA�A��̔�s�@�œǂ�ł����{�ł���B
�{���`�̔��X�ŁA�|�J���X�G�b�g�B������łɔ��������̂��B
�w�H�̒ė����~���x���v�i�ҁj�@2004�N11��1���@�A�ϓ����Ɂ@600�~�i�ō��j
�i���ɔŁFAmazon�̌����ł̓n�[�h�J�o�[�ł��݂��邯��ǂ����ɔł͂܂��Ȃ��j�@
���ꂪ�\�z���đf���炵���{�Ȃ̂��B
���������́u���y�v�Ƃ����L�[���[�h�œ��{�̓`���I�ȐH�����������X���Љ�Ă��邾���Ȃ̂����A���̏Љ��Ă�����X�̌������A���Ɂu��̘_���v�Ȃ̂��B
�܂�e���g���[�Ɠ`������n�߁A�����˂��l�߂邱�ƂŁA�ނ�̍�i�i�[���ł���A�݂��ł���A�ݖ��ł������肷��j���e���g���[���z���Ďs�ꉿ�l�������Ă��邱�Ƃ��킩��B
����́A16���ɏ������A���́i���j��̋��ʓ_�Ɠ��������������Ă���悤�Ɏv����B
����́A���i�ɁA��������̐l�i�̂悤�Ȃ��̂��A���ڂ��Ă�����Ă��Ƃ��B�B
����́u�����̌����ł����A�z���g�͔����Ȃv�Ə���������ǂ��A�u���^�̌����v�i����V��j���ƂĂ����������Ă��邱�Ƃ��킩��B
�E���蕨�̓��m�ł͂Ȃ��B���m��}��Ƃ��Đl�Ɛl�Ƃ̊Ԃɐl�i�I�ȂȂɂ����ړ����Ă���B
�E���ݐM���̋C������\�����邩�̂悤�ɁA���Ԃ��͓K���ȊԊu�������Ă����Ȃ��B
�E���m��}��ɂ��āA�s�m��Ȍ���s�\�ȉ��l�������Ă���B
������Ƃ����āu���^�v�ł͂Ȃ��B
������O��Ƃ��Ă��鏤�i�ł͂��邪���^�̌�����s��ł���A�Ƃ������Ƃ��B
������ŋ߂̂킽���́u���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�v�Ƃ��ł���B
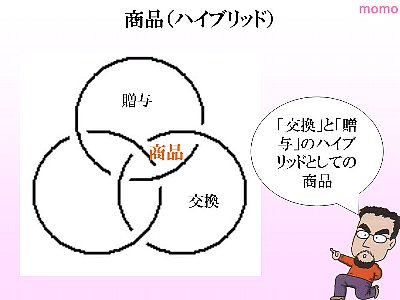
�܂�A�~�[���_�ł����A����Ƒ���̏��̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i���Ă��Ƃ����A����I�Ɨ���I�̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�ł���B
�����������ԓI�Ȑ��i�����������i���A�̍��o�����i�ł��邱�Ƃɂ���āA�t�ɂ���͎�i�e���g���[�j���z���đ��݂ł���̂��낤�B
�y���}���z
�{��Ŗڂ߂�B
�ߑO8���B���V�B
����̓{�E�����O��������A�Ă̒�ؓ��ɁB
������Ղ��g�̂��B
���̃{�E�����O������ǂ��A�Ȃ߂��Ⴂ���Ȃ��B
2�Q�[������������ǂ��A1�Q�[���ڂ͂Ȃ�Ƃ����肪�����ăX�R�A��180����ƁB
�ł�����ŃK�X���ꂽ�B
��Q�[���ڂ͂悤�₭100���z�������x�B
�{�[�����O����đ����ꂽ�B
�G���������������B
�Ȃ����Ȃ��g�̂��B
�Ƃ������ƂŁA���`�����������Ƃ͑�R����̂�����ǂ��A���}���A��̏������B
2004/11/19 (��) �@�� ��
�y�����͋{��ցz
�ߑO6���N���B
�͉J�B
���āA���悢�您�K�ɉ������B
���e�ł���B
����́A�T�C�{�E�Y�g�[�N���C�u��PPT���쐬���A�����̋{��ł̍u����PPT���܂Ƃ߁A���̗]���������̖@���̂悤�ɗ��p���āA�ŏ���2�y�[�W���������B
�Ƃ肠����A�S5�y�[�W�A9000�����l���Ă����̂ŁA���̂܂܂Ȃ�Ƃ����������Ă������B
���A�����͋{��ōu���B
���̌�͑�ȍ��e��܂��Ă���B
�݂邫�����܂���B
�����͊����������l�ł����B
�@���͎��A���m����̂��b��������ƕ����̂͂��ꂪ���߂Ă�������ł��B
�i��������j
�@�ŋ߂̓��m����̓X��Y���̓��e������āA�ǂނ̂ɕK���ł����������̂��b���āA�����Ȃ�ɏ����ł��������ł��܂����B
�@�C���^�[�l�b�g�T�C�g�ɂ����ĐF�X�ȏ��ʼn^�c�҂�Ǘ��ғ��̖��������Ă���ƁA�O���̃n�u��`�̂��b�͐����҂Ɣ��҂̊ԂŒ��Ԃ���̏�Ԃł���䂪�g���ӂ肩�����Ĕ��Ȃ����邱�Ƃ�����ł����B
�@���ꂩ��͂��������������O���[�o���ɐ����邩�A�n�斧���^�ł�����̂��A����Ƃ��S���ʂȌ`�Ői�ނ̂�������ƍl���Ă݂����Ǝv���Ă���܂��B
�@���āE�E�E�����C�Â����̂ł����A���m���b�̓r���ŏ㒅��E����܂������?�@����͂�͂藎��Ƃ���́u�܂��炪�I����Ă��ꂩ��{��ł���v�ƉH�D��E����邱�Ƃ��ӎ����ĂȂ����Ă���̂ł��傤��??
�@�������̎d����q�������Ƃ���A���Ԃ�������u���̏����͐����Ă��܂���v�ƉH�D(�㒅)�������O���Ƃ��Ĉ��������ɂ�������!�Ƃ����Փ��ɂ����Ă��܂��܂���(^^:
�@���̘b����l�ɂ����̂ł����A��������Ƃ��H�D��E����������Ȃ��̂ŗ������Ă��炦�܂���ł������E�E�E
�@���Ђ܂��@�����܂����瓍�m����̂��b����Q���҂Ƃ��Ă�������Ƃ������������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂邫�������� |
�㒅��E���͎̂w�E�̒ʂ�|�̈ꕔ���B
�܂�A������x�́u�v�Z�����v�Ȃ̂��B
������x�Ƃ����̂́A�ŋ߂͂قƂ�ǖ��ӎ��ł�������Ă���킯�ŁA�܂�قƂ�ǖ��ӎ��A�g�̂��o�����^�C�~���O�Ǝd���Ȃ̂ł���B
�V���c�̑����܂���Ƃ��A������|�P�b�g�ɓ����Ƃ��A�܂����̎�̎�@�͐F�X�������ǂ��A�����ł���܂菑���ƁA�������������C�ɂȂ��Ă��܂����낤����A����ȂƂ���ł����ق��B
���ꂩ��A�����ł�PPT������ǂ��A�����̋{��ł̍u���̏k���łȂ̂Łi���͍u�����Ԃ�90���������̂��B���ɏł����j�A�����ɂł�������PPT�͌f�����܂��̂ŁA����ő�p�������������B
O���܂��B
�͂�Ă̎w��Ȏ�����ςł����ˁB
�������D�@���ĊO
�K���Ȃ̂�������܂���ˁB
���t���ԈႦ��
����Ă���ꂽ�Ƃ������Ƃł���
���̗F�l�ɂ������悤�Ȑl������
�P���x��ď���Ă��܂����Ƃ������Ƃł��B
�������ޏ��̏ꍇ
�V�����s�̎����Ƃ�������
�Q�l�ŊԈႦ���̂��Ƃ�����Ă��܂��܂����B
���̌�ǂ��Ȃ������́A�|���ĕ����܂���ł����B
���߉����ɂ����P��
���̌������ɂ�
�P���x��Ď���ɗ��Ă��ꂽ�F�l�����܂��B
�ޏ����킭
�ǂ���ő��}�o�X�����܂ł����Ă�
���Ȃ��Ǝv�����̂�ˁB�E�E�E��
����܂ōs������
�ȏ��\��������ċA���Ă����Ƃ̂��ƁB
���̗F�l�͂���Ȑl������ł��B |
�킽���͎v�킸�����̗\����m�F���Ă��܂����B�i�j
���Ă���i���j�͐���h�����������̃z�e���ł�Sense
of Wonder�ł���B
���C�e�B���O�E�f�B�X�N������z�e���̕������Ă����̂����߂Ă������̂�����ǂ��A�܂�����͋����ɂ͒l���Ȃ��B
���͉E���Ɏʂ��Ă���}�b�T�[�W�`�F�A�݂Ȃ������̂��B

�ł�����}�b�T�[�W�`�F�A����Ȃ��ȁB
���R�Ƀx�b�g�ł��Ȃ���B�x�b�g�̓L���O�T�C�Y�̂ł�����W�x�b�g�������B
�킩��l�͂��邩�ȁB�킽���͐��������ċA���Ă��āA����ŌߑO3���܂ŐQ�Ă��܂����̂��B
�܂��A�C���͈����͂Ȃ������B
�Ƃ������ƂŁA���������̃o�b�N�������ɂł�����B

�q�h�l�nWA
2004/11/18 (��) �@�� ��
�y�x���ڊo�߁z
�x���ڊo�߁B����9�����߂��Ă���B
�͂�����B
��ӂ͋{�肩�炨�q���܂������łɂȂ�ꂽ���Ƃ�ǂ����ƂɁA���i�������؉��ƁA�킽���̐R�[�X�i���A�Ԗ����A�F�����g�����݂܂������B
���ɂ͒��x�A�t�������R�I�����̂����~���������Ă��āA�킽�������́A���~���̃J�E���^�[�ɐȂ����A�ޏ��̌|�������Ŋy���݁A���R�I������Ă��q�l���A��ꂽ��́A���X�̂����܂ŁA�ޏ��ƌ|�ɂ��Ă��ꂱ��b���Ă����B
�ޏ��̌��t�ɂ��Ă��D�~�͂ƂĂ������[���B
����͌|�Ƃ��Ă̌��t�ɂ��Ă��B
���ɁA�킽���̂悤�Ƀl�C�e�B�u����Ȃ����̂��A�]�˕ق낤�Ƃ���Ƃ��Ɋׂ�₷���v�����݂Ȃ͖ڂ�����̂������B
����Ȃ��̂�����A�ˑR�A�ޏ��ɍu�������Ă��炨�����A�ƂЂ�߂����i����1��22���̐V�N��̑O�ɂ��A�V�t�u����̎��̃Q�X�g�Ƃ��Ă��Ăт��邱�ƂɂȂ邾�낤�j�B
���łɁA�����̔ޏ��̃X�P�W���[���ƁA���̗\����m�F���āA12��18���i�y�j�ɁA�����́i��{�I�ɂ́u�@��G�N�X�e���V�����J���b�W�v�̖Y�N��Ƃ������j�����₩�ȖY�N������邱�Ƃɂ����B
���R�ɔ��R�I����͂킽�����炨���~�������Ă������B
�Q�����������炱���A�ł܂�����Ƃ������Ԃ��߂������Ǝv���B
������11��29�̃T�C�{�E�Y�g�[�N���C�u��PPT�̒��ؓ��B
�ߑO���ɂ�����Ă��܂����B
2004/11/17 (��) �@�� ��
�y@�����z
6��45���N���B
�����͂�����B
����̐V�����B���w�������ė���ꂽ�����A�킽���̍����Ă���Ȃ������̐Ȃ��A�Ƃ��������B
�ؕ��������Ă��������ƁA�Ȃ���A������Ԃ̓����Ȃł���B
�ł��ˁA���t���Ⴄ�̂�B
���Ȃ��͖̂����̗�Ԃł���A�ƗD�����w�E���Ă�����ƁA�p�����������ɂ킽���ׂ̗ɍ������B
����Ɠ����o���͈ȑO�ɂ�����������ǂ��A�ǂ��������A����������Ԃ̓��t���ԈႦ��̂��낤���H
�܂��Ă�A�͂�Ă͑S�Ȏw��̂͂��ŁA�������D��ʂ��Ă����Ƃ͎v���Ȃ��̂�������B
���ǁA����̂����́i���j�̖{�ɂȂ����B
�������܂ܖ��ǂ������̂��B
 �{�V�Ўi�́g�t�����K�l�hPHP�V��
�{�V�Ўi�́g�t�����K�l�hPHP�V��
�{�V�Ҏi�i���j
2003�N8��25��
PHP������
714�~�i�ō��j
����́A�{�V���̌��q�M�L�{�̂悤���B
�܂�ōu���̂悤�Ȍ����ŏ�����Ă��邵�A�킽���ɂ͗{�V���̕@�̂̂悤�Ɋ�����B�ړ����ԂɌy���ǂݗ����ɂ͂ƂĂ��悢�킯���B
�킽���͗{�V���������Ă��邱�Ƃ́A�ƂĂ��D�ɗ�����B
����͂����܂ł������̉��ߔ\�͈͂̔͂ł�����ǂ��A������Ă��邱�Ƃ��A�����̌��t�ʼn��߂��邱�Ƃ��ƂĂ��y�ȕ��Ȃ̂��B
���Ԃ��悤�Ȏv�l�̘�ōl���Ă���̂��낤�Ǝv���B
�{�V�t�@���Ȃ̂��A�Ƃ����˂���A�������A�Ɠ����邵���Ȃ��B
�킽���̍u���ł́A�u�o�J�̕ǁv�ɂ������Ay=ax
�Ƃ����]���̈ꎟ��������IT���ɂ������ȃL�[���[�h�Ƃ��āi���f�Łj�g���Ă���B
�܂��A�u���� y=ax ���g���Ă���̂́A�Ղ̈Ђ����悤�Ȃ��̂��낤����ǂ��ˁB
�������10������u�����B
���ꂩ�畗�C�ɓ����āA���т�H�ׂāA���C�ɂ��܂��傤�B
���R�������A y=ax ���g���B�i�j
2004/11/16 (��) �@�� ��
�y�ӂ��ҎႵ���͉ߏ�Ȉ��z
7��35���N���B
�͂�����B
��їl�̂�����V�������̂ƌ��������B
����͂킽����PC�P�[�X�ɂ��Ă�����̂Ȃ̂��B
���܂ł����b�ɂȂ������̂����߂Č���ƁA�����b�ɂȂ����Ȃ��A�Ƃ����L���`�������Ă���B
�����b�ɂȂ������̂͑�ɕԔ[���悤�B

���e���������߂�2�T�ԋ߂����Ԃ��m�ۂ��Ă������B
�ł��A���̎��Ԃ��I����Ă��܂������A�킽���̎茳�ɂ͉����Ȃ��A�Ƃ��������������c���Ă���B
���̌����͏d���B
���Ԃ͂����Ղ肠�����B
�\��̑g�ݕ��͗ǂ������Ǝv���̂����A����Ɖ��̂ɏ����Ȃ��̂��͕ʖ��̂悤���B
�l�^�������킯�ł͂Ȃ��B
���ƎҒc�̃x�[�X��IT���ɂ��ẮA�R���T���e�[�V�����̌o�܂��A�u�����e���A�����������B
��������̂܂����悢�����������B
����Ɍ��e���e���Ċm�F���邽�߂ɁA11�E04�̎����I��������Ȃ����B
�Ƃɂ�����������̑ӂ��҂Ȃ̂��ȁA�킽���́A�Ǝv���B
�܂��A���Ɏn�܂������Ƃ���Ȃ�����ǂ��B
����ł��A����́A������RICOH SolutionWay�@���04�p��PPT�ƁA29���̃T�C�{�E�Y���[�U�[��p��PPT�i18���Y����j�̌��Ă��쐬�����B
����Ȏ��́A�Ƃɂ��������͂��߂邵���Ȃ��̂����������B
�]���X�ɉ�����邱�Ƃ��ˁB
���������A�o���オ����������PPT�Ƃ�����A2���Ԙg���Ƃ����̂�88��������B
���ꂶ��2���Ԃ��Ⴚ�������ɖ�������I
����₱���Ƌl�ߍ��݂����Ȃ̂��B
���̂܂܍u��������Ȃɂ���[�܂邱�ƂɂȂ邾�낤�B
���ꂶ��N�ǂƕς��Ȃ��킯���B
�Ȃɂ��`���Ȃ��B
�����E�E�E�������A�ƍ��v�����B
�Ȃ�ƂȂ��A���e�������Ȃ����R���킩���悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B
�l�ߍ��݂����Ȃ̂��B
�\�z�̒i�K�ŁB
���Ԃ�B
�u���́A�{����PPT�Ȃ��Œ����Έ�Ԃ����̂��낤���B
����͍������ɍčl���낤�B
�`���邽�߂ɁA�Ȃɂ����̂ĂȂ��Ă͂����Ȃ��B
�̂ĂȂ�������̂��Ƃ��A�`���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����ȂƂ��͂Ȃɂ���C���ȁB
�����̍u���A��������Ȃ�������ǂ����悤�Ȃǂƍl���Ă��܂��B
����Ŗ{���ɂ�������Ȃ�������A�h�{�����낤�B
�܂��A�����ǃh�{�����������ǂ��̂�������Ȃ��B
�ł�����������B�i�ǂ����Ȃj
�����͌ߌォ�琷���ֈړ�����B
����Ȏ��ɂ͐l�ɂ����Ɍ���B�F�Ɋ��ӂ��B
�Ƃ������Ƃō����̂����͂���̗\��B
�ł��ς�邩������Ȃ��B
�u�K���́A�l���邱�Ƃ���n�܂�v�̂͏��m������ǁA�킽���ɍ��K�v�Ȃ̂́A����������A�Ƃ����P���ȍs���G�l���M�[������B
 �K���̏����ȓN�w
�K���̏����ȓN�w
�x���g�����E���F���W�F���i���j
���͓�{���{���i��j
2004�N6��18��
���}��
1890�~�i�ō��j
�ł������{����A����́B
�Ƃ������ƂŁA����̑����B
���́i���j��̋��ʓ_�B
����́A���i�ɁA��������̐l�i�̂悤�Ȃ��̂��A���ڂ��Ă�����Ă��Ƃ��ˁB
�����̌����ł����A����̓z���g�͔����ȂB
�����̌���
�E���i�͂��̂ł���i������l��O���L�҂̐l�i�⊴��Ȃǂ́A�܂܂�Ă��Ȃ��j
�E��������������
�E���m�̉��l�͊m��I�ł��낤�ƂƂ߂Ă���B�v���\�B
�ł�������A���h�Ɏs��Ō�������Ă��鏤�i���B
�ł́A������x���Ă�����̂��ĂȂ낤�B
�d���ɑ��鈤���ˁB
�Ƃ���ƁA���e�������Ȃ��킽���͈�������Ȃ��̂��낤���B
�킽�����g�͉ߏ�Ȉ��̂������Ǝv�������̂����B�i�j
��
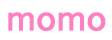
�����m���X�ސ���
(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2004.All
rights reserved.
�C���f�b�N�X �bSelf Talking INDEX| �����̋Y�� | 2004�N11���O���� | 2004�N12���O�����b���쌠�b�X��փ��[��
�b�������ޒʐM�bAbout���m���j�b�_�E�����[�h�b�ˑ������N�b�X��o���b
![]()
�]�Ɖ��z
�ꕶ�����̗�
�Y���ꂽ���{�l
�����̔���
�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J
���ƌo�ς̃��S�X�\�J�C�G�E�\�o�[�W���V
�Ώ̐��l�ފw�\�J�C�G�E�\�o�[�W���X
���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�
�@��BD041119s.zip �@�@-zip 2.71MB
�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|
�{�V�Ўi�́g�t�����K�l�hPHP�V��
�K���̏����ȓN�w
![]()