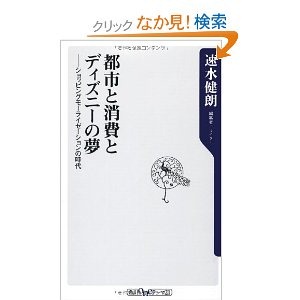 | 都市と消費とディズニーの夢 ショッピングモーライゼーションの時代 (oneテーマ21) 速水 健朗(箸) |
都市と消費とディズニーの夢
午前5時20分起床。浅草はくもり。この本が、『ラーメンと愛国』と間違えた本なのだ(同じ著者なのだ)、と云うと分かってもらえるだろうか。『都市と消費とディズニーの夢』、という立派な題名の割には、あたしの考えていたものとは、内容が全然違うので、ある意味”たまげた”のであり、だいたい、「ショッピングモール」に関したものと云えば、普通、否定的に論じられる、と相場は決まっているのだが、この本は、なんと肯定してみせるのだ。
「過ごしやすい場ができて人が集まる…これはかつて都市のダウンタウンが持っていた機能です。『いかにお金を使わせるか』という消費の論理が、翻って公共性を持つ。ショッピングモールには地域再生のカギが詰まっているように感じるんです。」※1 、と云う、著者の言葉に、あ然としたのが、「買ってみるか」の発端なので、ある意味うまくやられたのかもしれないな、と思っている(合計二冊も買わされたのだ)。
しかし、あたしが問題にしている「ショッピングモール」の問題は、『お金は使いたくない』人たちに向けた公共性の問題だし、そもそも、彼のいう公共性が、あたしの知ってる公共性とは違うような気がする。
そして、「地域再生」の問題とは、北海道の空知の様に、人口が全盛期の半分以下になってしまったような土地で(つまりは人口が減っていく地方で)、どうしたら、「資本の理論」が動くのか、それとも別の理論なのか、という「資本の理論」からも見放された場所の問題なわけだから、この本は最初から、あたしと議論の場所が違うのである。
だからと云って、そのままにしておくこともできずに、こうして書評を書くことにしたわけだが(べつに書かなくともいいわけだが)、ここで、あたしの住む”浅草”のことを書くと、浅草は、全くこの本のいう「ショッピングモーライーゼーション」はないようで、『ラーメンと愛国』と同じ終わり方になってしまうのだ。
仲見世は「ショッピングモーライーゼーション」ではなく、「子宮的構造」で動いているし、その周りの浅草の町内会は、フラクタルの構造なわけで、お金儲けにひたすら忙しい(過去に色々と書いたがこんなんでどうだろう)。
ただ、近くの南千住駅前は、最近綺麗になったよな、と思うが、その綺麗な場所には、どこも同じような味で脚が向かないのも事実だ。しかしだ、この本のピントがあたしとあう頃には、浅草寺は30階立ての高層ビルになっているのだろうな、と思うのだ。
