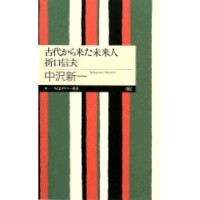
|
中沢新一(著) |
ウソつきとしての中沢新一
中沢新一さんは希代のウソつきには違いなく、折口信夫の紹介文のようなこの新書も、魅力的なウソに溢れている。ただそのウソは、だますこととはちがう。この本で使われている(折口の)語彙を使うのなら、それは中沢さんの優れた「類化性能」(表面的には違うものの間に、同質性や共通性を見いだす能力)による創造物である。だから中沢さんのテクストは、論理的というよりも、むしろ文学的なのであり、ひとつの読み物としてとてつもなく面白い(ものが多い)。
折口信夫
おぼんのような世界の生き方を考えているあたしにとっての折口信夫とは、「まれびと」につきる。
柳田国男は共同体の同質性や一体感をささえるものこそが神だと考えていた。そうなると、神と共同体はある同じ性質を共有している必要がある。柳田の考えでは、先祖の霊こそがそれにふさわしい存在だった。(略)
ところが、折口信夫はそれと反対のことを考えていた。折口は神概念のおおもとにあるのは、共同体の「外」からやってきて、共同体になにか強烈に異質な体験をもたらす精霊の活動であるにちがいない、と考えたのである。(p32)
 柳田的に考えれば、社会は閉じたまま(おぼんのような世界)でいいのだけれども、しかしインターネットが普通にある時代に、それは望んでも無理なはなしなのである。
柳田的に考えれば、社会は閉じたまま(おぼんのような世界)でいいのだけれども、しかしインターネットが普通にある時代に、それは望んでも無理なはなしなのである。
というよりも、そんな社会システムは、著しい社会変化(外部の変化)に適応力を持たないことで存在不可能なのである。
この本で中沢さんは、インターネットが普通にある時代(21世紀の日本)は、「まれびと」のシステムで動かなくてはならない、と言っているのだと思う(たぶん)のだけれども、「まれびと」とは、あらかじめ予測される逸脱のことだ。
それは、システム理論的にいうならば、社会システムが、外側と内側の差異を、システム内に構築しているということであって、これはニクラス・ルーマンなんだわね。
つまり共同体は、クローズド・システムであることを意味しているのではなくて、社会システムは外部からくるもの(社会変化)を、内部にあらかじめ準備されている形式の中で捉え、その衝撃を吸収することができるようにしなくては、共同体としては機能しない(というよりも、存続不可能)だろう、と。
そのような共同体とは、江弘毅のことばなら「街的」であり、あたしのことばなら「町内会」である(たぶん)。
であれば、おぼんのような世界である公共事業という産業の生き方も、「まれびと」的でなくてはならない、というのが、あたしの考え方なんだ(だからこそ、折口信夫の跡継ぎのような中沢さんを読んできた)。ということで、午前7時起床。浅草は雨。今日はさすがに北海道遠征の疲れがでていて、休養日となる予定。

Comments [2]
No.1ちーさん
>あらかじめ予測される逸脱
なるほど~。そういう視線で読んでませんでした。
ちゃんと読んでみます。
(弊社の本、いろいろ読んでくださってありがとうございます!!)
No.2ももちさん
>あらかじめ予測される逸脱
なら、なんとかなるように共同体はできているんですが、予測されない「逸脱」だと、町内会がしっかりしていてもショック(ダメージ)は大きいですね。
ただ共同体の記憶として、類似した経験(逸脱)を伝えておく(蓄積しておく)ことはできるわけで、それが芸能や祭りになっている。それは町内会的な免疫として機能することによって「あらかじめ予測される逸脱」に成りえます。
しかしその蓄積されたものを"読めない""意味がわからない"のが今の状態なのであって、つまり「あらかじめ予測される逸脱」が「あらかじめ予測されない逸脱」になってしまっているように感じています。