2009年3月の記事一覧
午前7時起床。浅草はくもり。午前中WBCを見ながら関与先のサイトリニューアル案を作っていたらはまってしまった。それはもう(案)じゃなくて、これでいってちょうだいになってしまているのであって、あんまりいいことではないなと反省していた。
 さてWBCも明日が決勝で、また韓国戦なのはさすがに飽きたし、調整不足の春先の野球は、やっぱりオープン戦だよな等と思いながら今日のアメリカ戦を見ていたりしたのだけど――あたしはシーズン中は午前中大リーグ中継をみるのを常にしている――、けれど明日はTVに釘付けなはずだ(たぶん)。
さてWBCも明日が決勝で、また韓国戦なのはさすがに飽きたし、調整不足の春先の野球は、やっぱりオープン戦だよな等と思いながら今日のアメリカ戦を見ていたりしたのだけど――あたしはシーズン中は午前中大リーグ中継をみるのを常にしている――、けれど明日はTVに釘付けなはずだ(たぶん)。
やっぱり、頑張れ!ニッポンなのである。
そんな中、世の中にはおもしろいモノがあるものだなと感心したのがこれ。
この箸の原材料は折れたバットで、リサイクルっていえばたしかにそれらしいのだけれども、元は「折れたバット」なわけで、なんか縁起わるそうだなとあたしは思ったりしている。
どんな人が買うんだろう。
日本人は、競争というと本当に典型的な競争をやってしまいます。例えば、英国のような2大政党制にしようという主張が日本でもされました。しかし英国で痛感したのは、英国は極端なコネ社会だということです。労働党と保守党で分かれて対立しているようでいて、実はケンブリッジ大学とオックスフォード大学のカレッジに所属して同じ釜の飯を食ったり、同じボートを漕いでいたりしていた。表面的には論争していても、根底で持っている文化は結構共有している部分が多い。会員制クラブのような社交の世界があって、その部分で繋がっていて裏で話していることがものすごくたくさんある。これは米国でも同じです。
マーケットでも同じで、表面では競争するけども、裏で何らかの関係ができるというのが必要なのです。しかし実は、このことは今の経済学ではうまく描けない。今の経済学では、単純に言ってしまえば裏で談合しているゲームでも、個々のプレーヤーの利益を最大化することですから。
例えば、経済学には「コモンズの悲劇」というゲーム理論の典型的な話があります。広い放牧地で皆が牛を放牧していると、牛が草を食べ過ぎて、しまいにはやせてしまう。しかし実際のコモンズでは、そんなことはあり得ない。本当の共同体や共有地には、実は厳しいルールがきっちりあって、そのルールは皆が試行錯誤しながら作るからです。皆が牛を放牧しすぎたり、1人で大きな牛を飼ったりはできなくても、それなりに大きな牛を維持できるという現象がある。日本の入会地や漁業協同組合なども、そういう構造です。
しかしこうした議論がなかなか経済学でメジャーにならないのは、今の経済学に向いていないからです。それは時間の考え方の取り扱い方が今の経済学にはなくて、極端な話、経済学は時間のある現実世界をどうやって無時間的に扱うかというための努力を100年くらいずっとやってきました。時間のある社会をそのまま書くということをやっていない。 江頭進 小樽商科大教授 from 「小泉構造改革」は誤解の集積だった:日経ビジネスオンライン
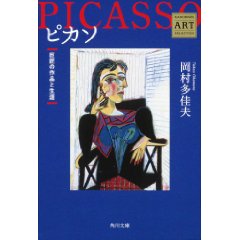
|
ピカソ――巨匠の作品と生涯 Kadokawa Art Selection (角川文庫)
岡村孝夫(著) |



 午前6時起床。浅草は晴れ。昨日は
午前6時起床。浅草は晴れ。昨日は



