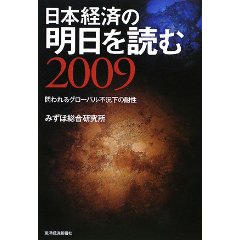
|
日本経済の明日を読む〈2009〉問われるグローバル不況下の耐性
みずほ総合研究所(著) |
人間は予測する
復習と予習のための本であって、読んでいて面白いものではない。それはテクストの快楽からはほど遠く、これを書いた人達の(書く)喜びは微塵もない。けれどこんなつまらないものを読むのも、人間は予測をする動物であるからで、人間は、天候も予測すれば、地震も予測したりする。それらは自然への畏敬のあらわれの延長型だろうが、経済予測ってなんなのだろうか。
市場万能主義の新古典派経済学では、家計、企業、政府という経済主体が、完全予見可能であることを前提としている。すなわち将来のことを完ぺきに予測できるから、家計も企業も政府も、将来のことを見据えて最適化行動=合理的に行動することになっている。つまり市場主義者の云うとおりなら、こんな本はいらない。※1
しかし明日の株価や為替レートさえ予測できないのがあたしらの正体なわけで、世の中は予想範囲-外、想定-外に溢れている。だから骰子一擲、しかし、いかで偶然を破棄すべき。かく云うあたしも、こうして他人が立てた予測を読み、自ら予測を立てたりしているのは、人間は情報がないと身動きできないからでしかない。
みずほ総合研究所がまとめた『日本経済の明日を読む 2009』の予測は、他の予測と同様、暗い予測に溢れている。一般的に不況(景気後退)とは、売れると思っていた楽観的予測が裏切られた結果でしかない。その文脈から予測できることを並べていけば、2009年の予測に楽観性はなくなり悲観だらけになる。つまり2009年の経済予測ほど簡単なものはないのかもしれない。
今発表されている2009年の経済予測の多くは当たるだろう(たぶん)。つまり売れないと予測されたものは売れない。暗いは暗いのである。しかしそんな予測が当たることの何が面白いのか。予測が当たることは景気がよくなるわけではないのだから、この予測が当たることは、あたし的にはつまらないことでしかなくなってしまう。
地域社会をどう活性化するか
~注目される地域金融機関と地方のサービス業
あたしにとっての関心事は地方経済である。本書は地域経済に関する項があるが、それをして他の予測とは違うところと云っても良いだろ。本書は地域間格差はある、という極めて真っ当な前提ではじまる。しかしそれは今更始まったものでもなく、昔からあったものが、小泉構造改革以降、いわゆる中流意識の衰退とともに顕著化してきたものだ。本書によれば地域経済の厳しさは次の2点に要約されている。
- 人口変動の象徴的変化
簡単にいってしまえば、大都市圏では人口の流入が見られるが、地方では人口は減っているということだ。それはイコール消費人口の減少なのであり、それに伴う需要の縮小が地域経済の浮揚を難しくしている。 - 公共投資の減少
90年代には、長引く経済の停滞に対応するように公共投資の増額が行われた。このため地方は建設業への依存度が高まった。しかし小泉内閣の発足以降公共投資は大幅に削減され、現在の公共事業費の水準はピーク時の半分以下にまで減少している。
これに対して、本書は「公共投資で地域は強くなるか」というテーゼを立てる。なぜなら景気対策=公共事業というケインズ的な処方箋へのけん制だろうが(あたしもけん制される側にいる一人だけれども)、それはプライマリーバランスの悪化を招くだけではなく、地方のヘタレ体質が維持されてしまう。つまり小泉内閣以降の公共事業絞り込みの背景は次の2点だとする。
- 主要先進国で最悪である財政の立て直し。
- 長期的視点では、公共投資は地域経済の活性化に本当に結びついたのかという反省。
公共投資の積み増しは短期的には需要の落ち込みを補う効果はあった。しかし地方経済における建設業への依存度が高まり、公共事業で支え続けなければ地域経済が維持できないような体質つくりだしてしまった。
これは開発主義のパラドックスのようなものだ。公共事業で支え続けなければ地域経済が維持できないような体質とはいうけれど、それをつくりだしてしまったのは、他ならぬこの国の政府・政策、つまり政治家と官僚なのである。そして開発主義の日没が難しいのは、本書の処方箋でもある、曰く「地域の個性を伸ばす創意と工夫」が機能しにくいのは、創意と工夫ができないように地方を育ててきたのが「開発主義」であるからでしかなく、創意と工夫する力が地方に蓄積されていれば、小泉さんの時代に地方は活性化しているはずなのである。
つまり小泉さんのやったことを綺麗事で云うなら、開発主義という構造を改革する(終焉させる)ことで、地方に埋もれているいる創意と工夫する力を呼び起こそうとした、ということだろう。しかし現実にはそうはならなかったのは、じつは人間の環境適応能力※2というのは小さいから、ということでしかない。
人間は簡単には変われないのである。だから変革には時間(と教育・訓練)が必要なのであり、公共事業は徐々に減らしても、急激に減らしてはならない。急激な(地方の)公共事業の削減は、地方の創意工夫力=想像力を育てる体力も失うことで、開発主義の負の側面しか表出しない(つまりますますヘタレ体質になる)。だからこそ建設業にIT化を通じた教育を、というのがあたしの主張であり、実践だったわけだ。※3
本書のサブタイトルは「問われるグローバル不況下の耐性」であるが、2009年で云えば、(個人のレベルでも、自治体のレベルでも)「耐性」とは、今いくら現金を持っているのか、でしかない。経済学的にはそういう割り切りで考えるしかないだろうし、そこには創意も工夫も必要はないのである。必要なのは現金である。
しかしあえて創意と工夫を強調するのなら、それにもおカネは必要であることで、本書は地方金融機関の機能を強調している。あたしは、それには賛成の立場だ。パトリを護持できるのは、地域に所在する企業と長い間取引を行ってきた地元の金融機関である。地元の金融機関がしっかりしていなければ町内会もだめなのである。※4
それで本書はサービス業に注目している。たしかにサービス業は公共事業に代わる地方経済の牽引役になれるかもしれない。しかしそこでの問題は、地方では人口は減っているということであり、その一点で地方のサービス業は難しくなる。これには地方分権のあり方、地方の人口の集約化等が含まれてしまうことで、本書の議論はそこまでは及ばない。
※注記
- 1991年度の『経済白書』は、情報処理関連の技術革新が人々の予想能力を高めて、その結果、景気循環はもはやなくなった宣言したが、今から見れば笑い話でしかないIT幻想である。
- マリアビリティ(malleability : 可鍛性、可塑性、適応性がある、融通が利く、従順な、という意味)のこと。構造改革派の論点は、このマリアビリティが全ての人間に完璧に備わっていることを前提としている。つまり、構造改革は500万人の雇用を生み出すとか、公共工事のソフトランディングといわれている農業や林業やサービス産業への転業というのは、人間は簡単に職業を転換できる、という視点にあるのだ。しかし、人間はそのようなものではないことは証明の必要はないだろう。特に「公共工事という産業」に従事する方々のマリアビリティは低い。この視点に立つとき、社会資本整備と公共事業ということばのもつ意味の差は歴然となる。ゆえに、この「公共工事という産業」のマリアビリティをどう高くしていくのか、というところにわたしのいう「ひとを育てるIT化」(マリアビリティを高める=キャパシティを大きくするためのIT化)を持ってくるということは、産業構造の変革という長期的な視野の中で、公共建設政策、雇用政策等々、「公共工事という産業」が越えなくてはいけない「公共工事という問題」を、IT化がどこまで解決できるのだろうか、という、自治体の行うCALSが電子入札と電子納品だけだと思っている人には、まずは考えもつかない政策的な、そして本音のIT化のはなしとなる。2003年11月29日の店主戯言より。
- つまり「考える技術」のことであり、「頭のよくなるブログの書き方」のことなんだけれども、これを建設業協会という紐帯をベースにして行う必要性を理解していただくだけでも困難なことなのであるし、即効性を求める「交換の原理」に浸食された心象では、これは永遠に理解できないものだろう。
- 2008年9月中間期地銀決算ランキング。 なんていうのをわざわざ書いているのは、その関心からだ。信用金庫はどうなっているのかは知らないのだけれども。
